こんにちは!しょーてぃーです!
今回は、西原 亮さんの
『コンサル時代に教わった 仕事ができる人の当たり前』について紹介をしていきます!
『コンサル時代に教わった 仕事ができる人の当たり前』について
本書の概要
本書はひとことで言うと
仕事ができる人が当たり前にしていることが書かれた1冊です。
本書をオススメしたい人
・仕事ができる人の当たり前を知りたい人
・仕事ができるようになりたい人
・仕事をするうえで大事なことを知りたい人
入社して2.3年くらい経てば残酷なくらい
その人が仕事ができる人かそうでない人かが分かります。
著者自身も慶應大学を卒業後、ニューヨークにあるコンサル会社に入りましたが
社会人経験がない上、英語でコミュニケーションを取らなければならないため
当初は、最も仕事ができない人として扱われていました。
ただ幸運なことに、周りに仕事のできる優秀な人が多かったので
できる人の仕事のやり方を間近で見て学ぶことができました。
その経験から分かったことは、仕事ができる人は
誰でもできる当たり前のことを徹底的にやり続けているからこそ
周りから信頼され、チャンスを掴んでいるということです。
そこで著者は、仕事ができる人たちが
当たり前にやっている行動や立ち振る舞いを真似することで
コンサルタントとして昇進することができ
現在は父の後を継いだ会社でも売り上げが好調です。
本書では、そんな著者によるコンサル時代に学んだ
仕事ができる人が当たり前にやっていることを知ることができる1冊です。
『コンサル時代に教わった 仕事ができる人の当たり前』のまとめ
分かったふりをしない
仕事ができる人は、話を聞いてなんとなく分かったふりをしません。
なぜなら、本当は分かっていないのに分かったふりをすると
分からないことを放置し続けることになるからです。
さらに自分は上手く誤魔化しているつもりでも
分かったふりは相手に見透かされているものですし
「本当にわかっているのか?」「この人に任せて良いのか?」と
相手に不安を与えることになります。
特に仕事で分からないことを放置したまま進めると
完成した後でトラブルになりかねません。
そのため著者は
「仕事において分からないことを放置し続けることは完全なる悪です。」と言い切っています。
実際に著者がコンサル時代に
なんとなく上司の話に対して「そうですね」と返事をしたところ
「具体的に何を理解したか説明してください」と問われ
明確な答えができずに注意された経験がありました。
仕事での会話は、自分と相手が頭の中で思い描いている
イメージのズレを無くすことが目的なので
素直に分からないことは「分からないので教えてください」と言うことが大事になります。
曖昧な表現を使わない
仕事ができる人は、曖昧な表現を使いません。
仕事でコミュニケーションを取るときに
「少し」「できるだけ早く」「多めに」といった曖昧な表現を使うこともあります。
ですが、曖昧な表現をしてしまうと
自分と相手の中で、物事の認識にズレが生じてしまい
ミスにつながってしまうことがあります。
なので、仕事のできる人はそのような曖昧な表現を避けて
具体的に説明するようにしています。
例えば、仕事の締め切りを伝えるときに
「できるだけ早く仕上げてください」と言われた場合
2時間後なのか、1週間後なのか具体的な期限がわかりません。
他にも「すごい、たくさん、かなり、もっと、早い、遅い」なども
全て曖昧な言葉であり、誤解を招く表現になります。
そこで仕事のできる人は、自分と相手の間で誤解が生まれないように
「数値」や「固有名詞」を活用して、具体的に伝えようとします。
例えば「資料は今日の17時に提出します。」といったイメージです。
また仕事ができる人は、相手が曖昧な言葉を言ったら
「具体的にいつになりますか?」というように
曖昧な情報を具体的な情報に直すように工夫しています。
事実と意見を切り離して伝える
客観的な事実と自分の主観を混同せずに
切り離して伝えることが大事になります。
仕事において、事実よりも自分の意見や感じたことを伝える人は結構います。
例えば、上司から営業の成果を聞かれたときに
「好感触なので期待できそうです。」というのが、主観であり自分の意見です。
ですが、ここで上司が知りたいのは
「契約できたか、できていないか」という事実です。
そこで仕事ができる人は、事実と自分の意見を切り離して
まずは「契約はまだもらっていません。」と事実を先に伝えた上で
「ただ私の主観として、好感触だったので次の商談で期待できると思います。」と
自分の意見を付け加えます。
このように誰かに情報を伝えるときは、主観と意見を切り離し
まずは客観的な事実を正確に伝えた上で
その後に少しだけ自分の主観を付け加えるように意識することが大切です。
悪い知らせを最初に伝える
言いづらい悪い知らせを早く伝えると改善策をすぐに打てますが
ギリギリになってから伝えても、打つ手が無くなってしまうことが多いです。
誰しもが悪い知らせやミスを伝えたくないです。
だからこそ、悪い知らせを誤魔化さずに、すぐに伝える勇気のある人は信頼されます。
逆に、悪い知らせを隠そうとする人は信頼されません。
人はどうしても良い情報だけを伝えたくなりますが
悪い知らせほど早く伝える癖をつけると、仕事で信頼されるようになります。
すぐに手を動かさない
仕事のできる人は、いきなり手を動かしません。
なぜなら、物事をうまく進めるには
いきなり手をつけることよりも、まずは情報収集をしっかりして
無駄なものを削ぎ落とした方が、早く仕事を終わらせることができます。
例えば、家電を買うときに、いきなり店舗に行くのではなく
先にネットで評価や機能、値段などを調べた上で行動した方が
いきなり店舗に買いに行くよりも短時間でいい買い物ができます。
仕事でも同じように、資料作成をするときに
最初から手を動かして作成すると、スライドを作ったり消したりを繰り返してしまい
結果的に、時間がかかりすぎてしまいます。
なので、まずはフォーマットを調べたり
自分が思い描いている完成系と上司が思い描いている完成系に
ズレがないかを細かく確認し、無駄な作業が発生しないように下調べをします。
心地良いことではなく、1番価値を出せる仕事に集中する
人が1日に高い集中力を維持できる時間は、3〜4時間程度です。
だからこそ仕事のできる人は、集中できる3、4時間を
1番価値を出せる仕事に一点集中させます。
一方で、仕事ができない人はその時間を
重要ではないメールをチェックしたり
後でやればいい資料作成や事務作業に浪費します。
特に著者は、仕事ができない人は
成果が出ないのに、自分が心地よく感じる作業に時間を使いがちだと指摘します。
仕事は細かく分解して、いつまでにどこまで終わらせるかを明確にする
まず、仕事を細かく分解するということについてですが
これは今自分がやっている仕事を小さなタスクに分けるということです。
例えば、カレーを作るのであれば、以下のように小さなタスクに分かれています。
- じゃがいもとにんじんを洗う
- 野菜を切る
- 鍋に油を入れて肉と野菜に火を通す
- 水を鍋に加えて沸騰させる
- 15〜20分位混んでルーを入れる
同じように、どんな仕事も小さなタスクの集まりなので
必ず分解することができます。
なので、自分がやっている仕事を小さなタスクに分解して
メモなどに書いて、見える化することが第一にやるべきことです。
次に、小さく分解したタスクを見ながら
「いつまでにどこのタスクまで終わらせるのか」と
具体的な締め切りを決めて仕事を進めていきます。
例えば「今週までにタスク3まで終わらせる」と決めて
作業を進めていくようなイメージです。
いちいちタスクを書いていくのはめんどくさいですが
それでも、書き出すことで仕事を早く終わらせることができます。
なぜなら、やることを小さく分けて書き出して
見える化しておくと、やるべきことが明確になるので
「この後何をすればいいのか?」と迷う時間を減らせますし
今週までにここまで終わらせると決めておけば、仕事にメリハリが出ます。
また、仕事を細かく分解し期限を明確化しておくと
今の進捗が予定よりも遅れているのか進んでいるのかが分かりますし
遅れていれば、なんとか期限内に終わらせようとします。
また、自分が決めた期限内に仕事を終わらせられると
達成感もあり、気持ちよく休日に入ることができます。
見た目に気を遣いつつ、笑顔を絶やさない
仕事ができる人は、笑顔を絶やしません。
笑顔でいることは相手に好印象を与えますし
結果として仕事がスムーズに進みやすくなります。
仕事ができる人は、相手に会うと
嘘でもとりあえず笑顔を作るという所作が身についていることが多いです。
なぜなら、笑顔でいた方が合理的に得だからです。
一方で、仕事のできない人はいつも不機嫌そうだったり
暗い表情をしているので、相手に気を遣わせたり声をかけづらくさせています。
特に新入社員をはじめとする、仕事を教えてもらう立場の人は
話しかけやすい雰囲気作りとして、笑顔を心がけておくことが特に重要です。
同期で群れない
会社の同期は自分と同じような視点や経験しか持っていないので
一緒にいても成長がなく、傷の舐め合いやマウント合戦をするケースが多いです。
だからこそ、自分とは異なる視点を持つ人との交流を
積極的に持つことが大切になります。
例えば、上司や別の業種の人、自営業者などです。
また著者は、陰口を叩く人の近くにいかないこともオススメしています。
仮に自分が悪口を言っていなくても、
陰口を言っているグループの中で話に相槌を打っているだけで
陰口グループの一員にされ、結果的に自分の評判を大きく下げてしまいます。
最後に
ここまで本書について紹介してきました。
仕事をができるようになるために大事なことが、多数解説されているだけでなく
当たり前のことを徹底的にやることの重要性を知ることができました!
本書が気になる方は
是非本書を手に取ってみてください!
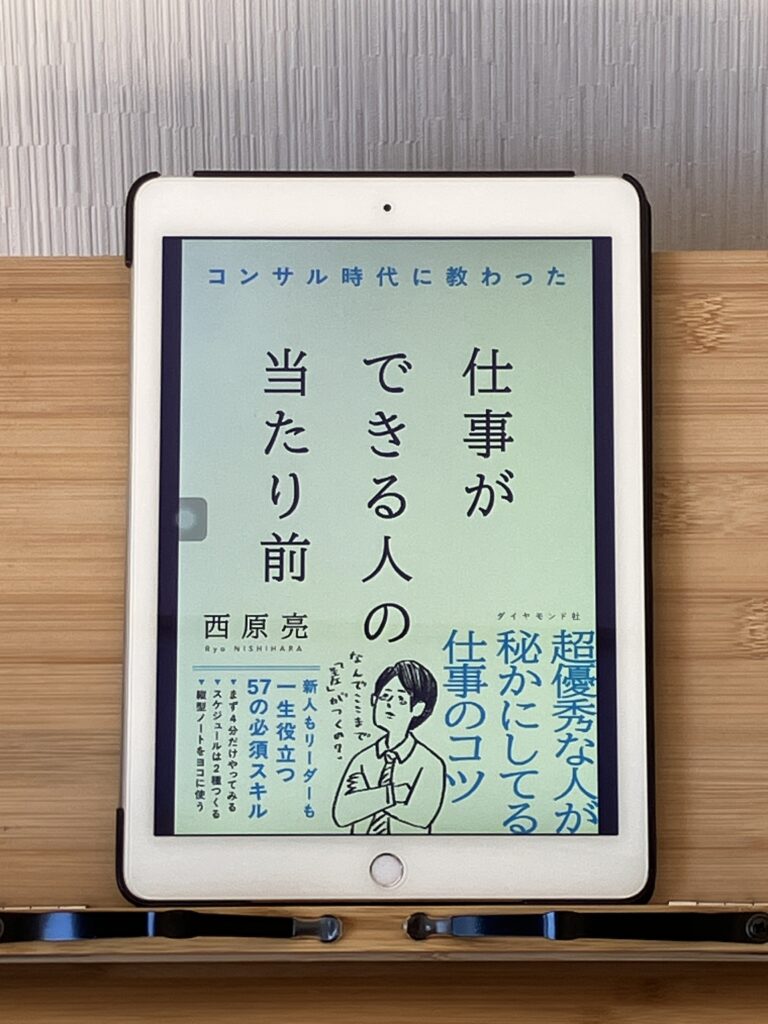

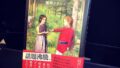
コメント