こんにちは!しょーてぃーです!
今回は、阿部 暁子さんの
『カフネ』について紹介をしていきます!
『カフネ』について
本書の概要
本書はひとことで言うと
愛する人の不在を抱えながら、生きる意味を探す物語です。
本書をオススメしたい人
・人間ドラマが好きな人
・食と人とのつながりに興味がある人
・じんわりと心が温まる作品を求める人
本作は、喪失と再生、人とのつながりをテーマにした感動作です。
法務局に勤める40歳の野宮薫子は、
12歳年下の弟・春彦を溺愛していましたが、彼は突然この世を去ります。
さらに夫からの一方的な離婚宣告も重なり、薫子は喪失感に打ちのめされます。
そんな中、弟の遺言書をきっかけに、彼の元恋人である小野寺せつなと出会います。
せつなが働く家事代行サービス「カフネ」の活動を手伝うことになった薫子は、
最初は彼女に対して複雑な感情を抱きますが、次第に心を通わせていきます。
「カフネ」はただの家事代行ではなく、孤立した人々に寄り添う存在であり、
食事を通じて心を癒す場でもありました。
本作は、悲しみの中で新たなつながりを見つけ、
人がどのように前を向いて生きていけるのかを温かく描きます。
『カフネ』のあらすじ
あらすじの概要
☆2025年本屋大賞ノミネート☆
【第8回未来屋小説大賞】
【第1回「あの本、読みました?」大賞】
一緒に生きよう。あなたがいると、きっとおいしい。
やさしくも、せつない。この物語は、心にそっと寄り添ってくれる。
法務局に勤める野宮薫子は、溺愛していた弟が急死して悲嘆にくれていた。弟が遺した遺言書から弟の元恋人・小野寺せつなに会い、やがて彼女が勤める家事代行サービス会社「カフネ」の活動を手伝うことに。弟を亡くした薫子と弟の元恋人せつな。食べることを通じて、二人の距離は次第に縮まっていく。
カフネ より
喪失の先にある、再生の物語
物語の主人公、野宮薫子は法務局に勤める40歳の女性です。
彼女は12歳年下の弟・春彦を溺愛していましたが、
その春彦が29歳の若さで、一人暮らしの自宅で自害して亡くなります。
さらに、夫からの一方的な離婚宣告も重なり、薫子は生きる気力を失いかけていました。
春彦の遺言書には、彼の元恋人である小野寺せつなへの
遺産分与が記されており、薫子はせつなと会うことになります。
せつなの変わり者な感じに戸惑いますが、
彼女が働いている家事代行サービスの「カフネ」で、薫子はその活動を手伝うことになります。
当初は反発し合っていた二人ですが、
「カフネ」の活動を通じて次第に心を通わせていきます。
「カフネ」は、単なる家事代行サービスではなく、
様々な事情で日常生活に支障をきたしている人々を支援する役割を果たしています。
特に、「お試しチケット」というシステムを通じて、
無償で支援を必要とする家庭を訪問します。
この活動を通じて、薫子とせつなは多様な人生の苦悩に触れ、
自身の成長にもつながっていきます。
『カフネ』の感想
料理と絆が紡ぐ、やさしい再生の物語
本作は、主人公・野宮薫子が大切な存在の喪失と向き合いながら、
新たなつながりを見つけていく過程を描く作品 です。
弟・春彦の死という大きな喪失を経験し、
その悲しみの中で、彼の元恋人である小野寺せつなと出会い、
家事代行サービス「カフネ」の活動を通じて、
人とのつながりを再構築していくというストーリーが展開されます。
この作品の大きな魅力は、喪失に対する描き方がとても丁寧でリアルであること です。
薫子は春彦を心から愛していましたが、
死後、彼が自分に隠していた遺言書の内容を知り、せつなの存在を知ることで、
「本当に自分は春彦のすべてを知っていたのか?」という葛藤を抱きます。
大切な人を亡くしたときに「自分はあの人のことを本当に理解していたのか」と感じるため、
個人的には非常に共感を得ました!
また、せつなもまた、春彦の死を受け入れつつも、
彼の姉である薫子と向き合わざるを得なくなります。
当初は互いに距離を置きつつも、「カフネ」の活動を通じて
次第に心を通わせていく二人の関係性の変化が
自然に描かれており、とても感情移入しやすくなっています。
本作の中核をなすのが、せつなが働く家事代行サービス「カフネ」 です。
しかし、このサービスは単なる「掃除や料理の代行」とは異なり、
社会的に孤立した人や困難を抱えた人々をサポートする役割も担っています。
特に、作中で登場する「お試しチケット」のシステムは印象的です。
これは、支援が必要な人が無料でサービスを受けられる制度であり、
経済的に苦しい人や、家事をこなすことが難しい高齢者などを対象にしています。
この「カフネ」の存在が、単なる物語の背景ではなく、
薫子やせつなの再生の場になっている という点が、本作の大きな魅力のひとつです。
薫子は、春彦の死を受け入れられずにいた自分が、
「カフネ」の活動を通じて他者と関わることで、
自分の喪失の痛みを和らげていくことを実感します。
また、せつなも、薫子との関係を通じて、
自分自身の過去や春彦との関係を整理していきます。
特に印象的なのは、「カフネ」がただの支援の場ではなく、
「食」を通じて人をつなげる場として機能している点です。
せつなの料理の腕前は作中で何度も強調されており、
彼女が作る食事が登場人物たちの心を解きほぐしていく様子が描かれます。
さらに本作の魅力の一つは、登場人物たちの関係性が非常に繊細に描かれていることです。
特に、薫子とせつなの関係性の変化 は、最も見どころのあるポイントのひとつです。
最初の頃の二人は、互いに相手を受け入れられず、ぎこちない距離感を持っています。
しかし、「カフネ」の活動を通じて、互いの苦しみや悲しみを知るうちに、
次第に理解し合うようになっていき、この変化が、とても丁寧に描かれているため、
二人の関係性にリアリティを感じることができます。
また、登場人物それぞれが持つ過去や背景も魅力的です。
薫子は「仕事に生きる女性」としての一面を持ちつつ、
夫との関係が崩れ、人生の再スタートを余儀なくされています。
せつなは、過去にさまざまな苦労を経験しながらも、
「カフネ」での仕事を通じて人々を支える役割を担っています。
こうしたキャラクターの掘り下げがしっかりしているため、
物語全体に深みが生まれています。
そして本作は、喪失と向き合う物語であると同時に、
「生きること」の意味を問う作品でもあります。
春彦の死は、薫子やせつなにとって大きな衝撃でしたが、
その死をどう受け止めるか、どう乗り越えるかが物語の中心にあります。
また、「人が亡くなっても、残された人々の中で生き続ける」というテーマがあります。
春彦の存在は消えてしまったものの、彼が遺した遺言書、
そしてせつなとの関係を通じて、薫子の中には確かに彼の思いが残っており
「大切な人を失っても、その人の記憶は消えない」という温かいメッセージとして伝わります。
最後に
ここまで本書について紹介してきました。
喪失と向き合いながらも、人とのつながりを通じて前に進んでいく本作は
温かくも切ない、心に染みる作品でした!
本書が気になる方は
是非本書を手に取ってみてください!
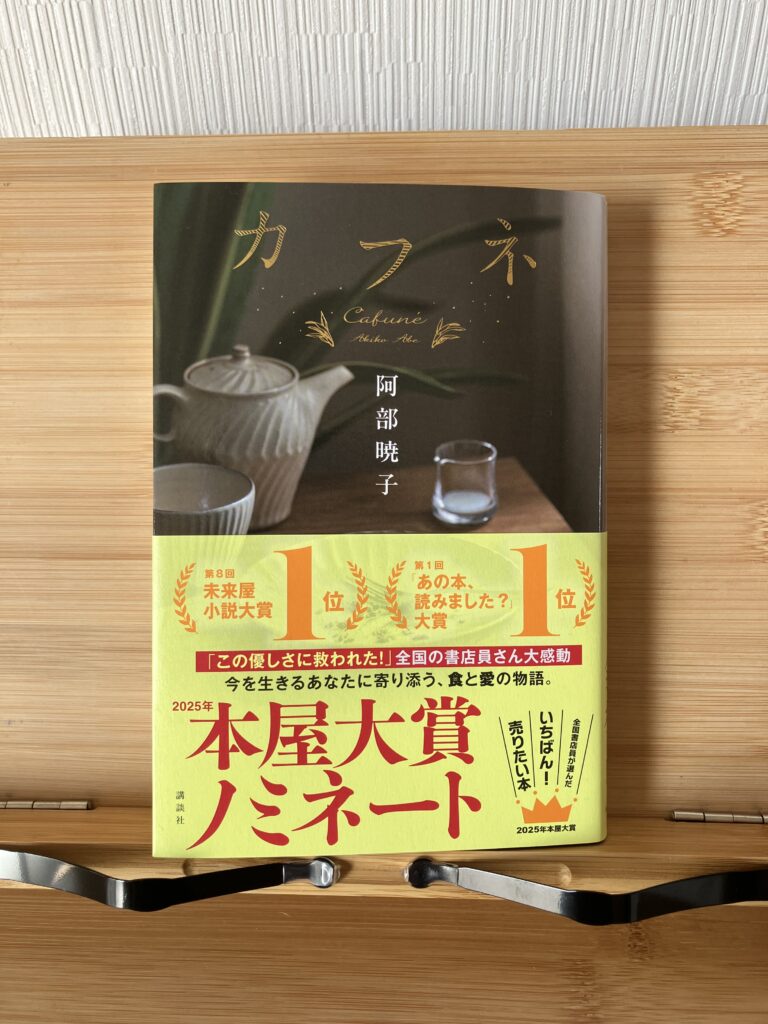
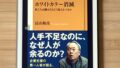

コメント