こんにちは!しょーてぃーです!
今回は、海老原嗣生さんの
『静かな退職という働き方』について紹介をしていきます!
『静かな退職という働き方』について
本書の概要
本書はひとことで言うと
世界標準の働き方を示す新視点の1冊です。
本書をオススメしたい人
- 新しい習慣を始めても、いつの間にかその存在すら忘れてしまう人
- 三日坊主で終わってしまう人
- 習慣化のコツを色々試しても、毎回挫折してきた人
本書は、出世を追わず最低限の仕事しかしない
「静かな退職(Quiet Quitting)」という働き方がなぜ生まれ、
広がっているのかを解説した1冊です。
この新たな労働観は2022年頃に米国で注目され始め、
日本でも若者世代を中心に密かに広まりつつあります。
著者の海老原嗣生氏(雇用ジャーナリスト)は豊富なデータをもとに、
日本で「静かな退職」を生み出した社会構造の変化を分析し、
欧米ではそれが当たり前の働き方である実態を示しています。
さらに、各企業や管理職がこの現象にどう向き合うべきかを考察するとともに、
静かな退職を選ぶ個人が組織のお荷物にならず
価値を維持しつつキャリアと生活を充実させるための指針を提案しています。
単なるサボりではなく、無駄を省いて生産性を最大化する
合理的な働き方だと位置付けられており、
日本の従来の働き方への新たな提言となっています。
『静かな退職という働き方』のまとめ
静かな退職とは何か
まず、静かな退職とは、会社を辞めるつもりはないものの、
出世を目指してがむしゃらに働くことはせず、
与えられた最低限の業務だけをこなす働き方を指します。
いわば「働いてはいるけれど、仕事に積極的な意義を見出していない」状態であり、
それを退職と同じだと見なしているのです。
この概念は2022年に米国のキャリアコーチが提唱し始め、
日本でも若い世代を中心に浸透しつつあると言われています。
静かな退職の具体的なスタイルとしては、
「言われた仕事はやるが、会社への過剰な奉仕はしない」
「残業は最小限にとどめ、有給休暇もしっかり取る」
「上司や顧客の不合理な要求は受け入れない」といった姿勢が挙げられます。
このように最低限の業務だけをこなす社員に対し、
旧来型の「モーレツ社員」世代の上司たちは納得がいかず、
「会社へのコミットメントが下がれば生産性も下がり、
業績目標に支障が出るのではないか」と不安を覚えることもあるようです。
実際、静かな退職が職場にもたらす世代間の軋轢が指摘されています。
しかし著者は、視点を世界に広げれば状況は一変すると説きます。
欧米諸国では、一部のエリート層を除けば
「残業をせずに最低限求められた業務を遂行する」という働き方はごく当たり前に行われており、
むしろ「手を抜けば抜くほど、労働生産性は上がる」という
意外な真実さえ浮かび上がってくるといいます。
つまり静かな退職は決して「サボり」や「怠慢」ではなく、
国際的に見れば合理的で効率的な働き方の一つだと言えるのです。
日本型働き方への問題提起
日本企業ではなぜ「静かな退職」のような働き方が
これまで受け入れられにくかったのでしょうか。
本書では、その背景に日本独自の雇用システムと職場文化があると分析しています。
著者は豊富なデータを示しながら、日本人が長年信奉してきた
「仕事に積極的な意義を見出し、顧客に真摯に向き合う働き方」の裏には、
実は生産性を下げる無駄な業務、いわゆる「ブルシット・ジョブ」の積み重ねが
隠れているのではないかと問題提起します。
丁寧にきっちりと仕事をするほど、かえって労働生産性は下がり、
逆に手を抜いた方が生産性が上がる。
これは日本の常識からすると皮肉な現象ですが、
著者はそれこそが日本の働き方の抱える大きな矛盾だと指摘するのです。
ではなぜ私たちは本質的ではない仕事にまで忙殺されてしまうのか。
本書によれば、その一因は日本の評価制度や同調圧力にあります。
上司からの評価につなげたい、何か問題が起きたとき
「自分はやるだけのことはやった」と言い訳できるようにしたい
そんな思惑から、多くの社員が「やっている感」を演出する過剰な業務に手を出してしまい、
その結果として不要な残業が増えて生産性が下がり、
私生活を犠牲にせざるを得なくなっていると指摘されています。
言い換えれば、「長時間働いている姿」を示すこと自体が目的化し、
本質的な成果よりも努力アピールが評価される風潮があるのです。
さらに日本企業の人事制度も、この「忙しい毎日」を拡大再生産する温床になっています。
昇給と能力評価が年次で紐付いているため、
与えられた新たな仕事を断りづらく、同期から遅れまいと無理を重ねてしまう
そうしたメカニズムが働き、常に忙しさが自己増殖する構造があるのです。
また、日本企業が社員に求めがちな過度の協調性や積極性には、
実質的に無償のサービス残業を強いる危うさがあるとも著者は警鐘を鳴らしています。
こうした構造的問題にメスを入れない限り、
静かな退職をめぐる世代間の対立は根本的には解消しないだろう、と本書は述べています。
静かな退職者の戦略
では、「静かな退職」を選んだ個人は組織の中でどのように立ち振る舞えばよいのでしょうか。
本書は、静かな退職者が自らの価値を維持しつつ職場で生き残り、
キャリアと生活の両方を充実させるための具体的な指針を提示しています。
第一に強調されるのは、
静かな退職者といえども決して組織のお荷物になってはいけないという点です。
最低限の業務しかしないとはいえ、自分に与えられた責任範囲の仕事には
しっかり成果を上げ続けることが重要だと説きます。
本質的な業務さえきちんと遂行していれば、
上司や周囲もその人を「怠慢だ」とは非難できないからです。
著者は実際、「静かな退職者」こそ高みに昇らず実務をこなし続けている分、
安いコストで会社に貢献する存在であり、
リストラにもなりにくく転機にも有利になり得ると述べています。
同期で管理職になった人より年収が低く抑えられている分、
会社にとっては人件費の負担を増やさずに済むありがたい人材だとも言えるでしょう。
次に、職場での立ち居振る舞いにも工夫が必要です。
最低限の仕事しかしないからといって、普段の態度まで投げやりになれば、
「やる気がないダメな奴だ」という烙印を押されかねません。
そうならないために、本書では身だしなみや言葉遣い、
職場でのマナーに人一倍気を配えるよう助言しています。
同じ業績でも日頃の振る舞いがきちんとしていれば
「できる人」という良い印象を与えられ、多少業務範囲を絞っていても
周囲から大目に見てもらえることが多いからです。
また、不用意に上司や同僚に反論しないといった処世術も推奨されています。
何でも「NO」と言って対立を生まず、表向きは協調的な姿勢を保ちながらも、
自分が引き受けたくない過剰な仕事は上手にかわすような
バランス感覚が静かな退職者には求められます。
さらに、本書は定時退社後の時間を有効活用することも提案しています。
無理な残業をせず時間に余裕を確保することで、
副業や自己研鑽に充てるチャンスが生まれます。
著者は、静かな退職者が定時で仕事を切り上げ、
その分残業代以上の副業収入を得て「生き伸びる」キャリアモデルも示しています。
終業後にスキルアップや趣味のビジネスに打ち込むことで、
会社一本では得られない収入源や充実感を手に入れることができるでしょう。
そして将来の生活設計については、WPP理論という考え方が紹介されています。
WPPとは「Work Longer(長く働く)」
「Private Pensions(個人年金)」「Public Pensions(公的年金)」の頭文字を取ったもので、
公的年金に早期から頼り切るのではなく私的年金を活用しつつ、
無理のない範囲でできるだけ長く働き続けることを推奨する戦略です。
例えば、公的年金は受給開始を1年繰り下げるごとに8.4%ずつ増額され、
70歳まで開始を遅らせると月額受給額は約1.4倍にもなります。
静かな退職を選ぶ人は早期リタイアで悠々自適……とはいかないまでも、
仕事量をセーブしながら70歳前後まで働き収入を得ることで、
経済的な安定と社会とのつながりを維持できると著者は述べています。
また、公的年金の繰下げ受給による増額分と私的年金を組み合わせれば、
仮に想定以上に長生きした場合でも経済的に困窮せずに済む
「おいしいとこ取り」の生き方ができるとも説いています。
以上のように、本書では個人が静かな退職を実践する上での心構えから
キャリア構築、資産設計に至るまで多角的なアドバイスが提示されています。
企業・社会への提言
本書が特に力を入れているのが、管理職や企業側への提言です。
著者は静かな退職という新たな潮流に企業が柔軟に適応することで、
むしろ組織運営の改善につながる可能性があるとも示唆しています。
まず企業や上司の視点では、静かな退職者を
頭ごなしに否定するのではなく上手に活用する発想が重要です。
たとえがむしゃらに働かない社員であっても、
必要な成果さえ出していれば組織に貢献できますし、
人件費の面でも大きな負担にはなりません。
実際、本書では「一定の成果を挙げつつ人件費の増加を回避できる人材は
企業にとってありがたい存在だ」と述べられており、
具体策として人事制度に「静かな退職コース」を組み込んではどうかという大胆な提案も提示されています。
全員がリーダーとなって突き進むことだけがキャリアの正解ではなく、
フォロワーに徹する社員にも居場所を用意すべきだというメッセージとも言えるでしょう。
また、働き方の多様性を受け入れることは、
社員個々人の幸福だけでなく組織全体の生産性向上にもつながると本書は示唆します。
例えば欧米では職務の分担が明確で、誰が何を担当するかがはっきりしているため、
自分の仕事に集中しやすい環境があります。
日本でも一人ひとりの役割と責任範囲を明確にし、
社員同士が必要以上にカバーし合わなくても済むようにすれば、
「静かな退職」を選ぶ人とも十分共存できるでしょう。
要は「頑張る人ばかりが損をする」状況を是正し、
各人が自分の役割を全うすれば、正当に評価される仕組みへと改めていくことが求められるのです。
そして社会全体・政策の視点では、「忙しい毎日をもっと頑張らせる」方向ではなく、
「無駄に頑張らないほうが生産性は上がる」という前提に立った
大胆な発想転換が必要だと著者は指摘しています。
家事・育児・介護といったプライベートの事情と
仕事を両立する人が今後ますます増えていく中で、
「静かな退職」はマイナスではなく
当たり前に市民権を得ていく働き方になるだろうとも予測しています。
静かな退職という一見ネガティブに映る現象を肯定的に捉え直し、
それを可能にする職場環境や社会制度へと舵を切ることができれば、日本の働き方は大きく変わり得る
本書はそのような未来像を提示しているのです。
最後に
ここまで本書について紹介してきました。
「静かな退職」という言葉には当初ネガティブな印象があるかもしれませんが、
本書を読むとそれが決して単なる怠惰ではなく、
現代に合った合理的な働き方であることが分かります。
従来の「長時間働いてこそ貢献している」という価値観だけでは
立ち行かなくなった時代において、
必要なところにのみ力を注ぎ自分の人生も大切にするという本書の提案は、
多くのビジネスパーソンに新たな視点を与えてくれるでしょう。
本書が気になる方は、是非手に取ってみてください!
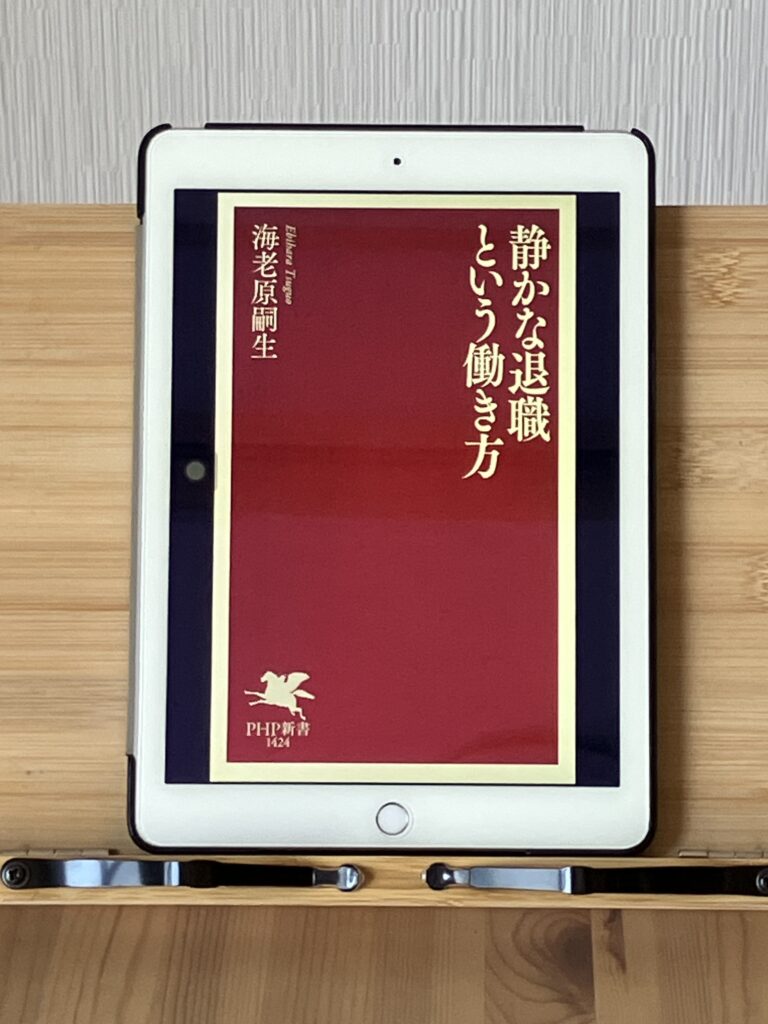
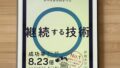
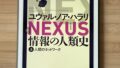
コメント