こんにちは!しょーてぃーです!
今回は、小野一起さんの
『よこどり 小説メガバンク人事抗争』について紹介をしていきます!
『よこどり 小説メガバンク人事抗争』について
本書の概要
本書はひとことで言うと
メガバンクで繰り広げられる仁義なき権力闘争を描いた1冊です。
本書をオススメしたい人
- 銀行や企業内部を舞台にした経済小説・企業小説が好きな人
- 組織内の派閥争いや出世競争のリアルな描写に興味がある人
-
裏切りや駆け引きなど緊張感ある人間ドラマを読みたい人
本書は、メガバンクを舞台に
日本の「失われた30年」の真因に迫る緊迫のエンタテインメント小説です。
主人公は大手銀行「AG住永フィナンシャルグループ」の広報部長・寺田俊介。
彼は社長(頭取)である竜崎太一郎の何気ない一言から
出世の兆しを嗅ぎ取り、竜崎に傾倒していきます。
竜崎は「部下の手柄は自分の手柄、自分の失敗は部下の失敗」と公言する人物で、
その信条の下、寺田は巨大銀行内での権力闘争という陰謀に巻き込まれていきます。
寺田の前には、経営不振に陥った不動産会社を巡る情報戦、
大手証券会社との合併劇、バランスシートに潜む不良債権処理、
さらには竜崎と筆頭相談役・栗原による次期頭取の座を巡る人事抗争など、次々と難題が降りかかります。
組織の野望と暗闘が渦巻く中、寺田は掟破りの手段にも手を染め、
メガバンクを覆う深い闇へと足を踏み入れていくことになります。
『よこどり 小説メガバンク人事抗争』のあらすじ
あらすじの概要
自分を見失った男たちへのレクイエム
組織は、あなたからどこまで奪うのか!メガバンクを舞台に「失われた30年の真因」を問う、緊迫のエンタテインメント。
「細部の圧倒的なリアルさ。銀行小説の新たな金字塔だ」――楡周平
【プロローグより】
「まず、君の手柄は、すべて私の手柄にする。いいな」
「はっ」
「それから、私の失敗は、すべて君のせいにする」
竜崎はおおきな執務机の前に寺田を立たせたまま、椅子の背に悠然と身体を預けていた。
「ただ、心配する必要はない。
君も、君の部下に同じようにやればいい。
それが銀行だ」
(引用ここまで)舞台はメガバンク、主人公は広報部長――
裏切り者は、中(なか)にいる!元共同通信日銀キャップが書く
巨大銀行の仁義なき権力闘争
息をのむ裏切りの連続
最後に立っているのは、誰か――【ストーリー】
AG住永フィナンシャルグループの広報部長、寺田俊介は記者とのインタビュー中に
社長の竜崎太一郎が漏らした一言から、自らの出世の可能性を嗅ぎ取る。
吸い寄せられるように竜崎に服従する寺田は、経営難に転落した大手不動産をめぐる情報戦や大手証券との再編、バランスシートの膿、竜崎と相談役の人事抗争…と次々に訪れる難題に直面。掟破りの手段へと手を染め、メガバンクを覆う深い闇へと足を踏み入れていく。
野心と派閥が交錯するメガバンクの舞台裏
物語の舞台は日本一のメガバンク、AG住永フィナンシャルグループです。
主人公の寺田俊介は同社の広報部長を務める銀行員。
彼の上司にあたる頭取(社長)・竜崎太一郎は強烈な信念の持ち主で、
冒頭から寺田に「まず、君の手柄は、すべて私の手柄にする。いいな…
それから、私の失敗は、すべて君のせいにする。それが銀行だ」と言い放ちます。
さらに竜崎は「君も、君の部下に同じようにやればいい」とまで部下に命じ、
功績の横取りと失敗の押し付けを当然とする銀行の論理を体現しているのです。
この冷徹なトップの下、寺田は組織内で生き残るための
厳しいゲームに巻き込まれていくことになります。
きっかけは、寺田がある記者とのインタビュー中に耳にした竜崎の一言でした。
竜崎が漏らした何気ない発言の中に、
自分が将来出世できる可能性を寺田は嗅ぎ取ります。
普段はリスクを避け堅実に仕事をこなす真っ当な銀行マンだった寺田ですが、
その瞬間から竜崎への忠誠と自らの野心に火が付きました。
寺田は「トップから差し出された出世の餌に食いついてしまう」形で
竜崎の腹心として動くことを決意するのです。
しかし、寺田を待ち受けていたのは次々に押し寄せる難題の連続でした。
まず、メガバンクを揺るがす経営危機に陥った大手不動産会社を巡り、
銀行同士や社内外で繰り広げられる熾烈な情報戦に直面します。
さらに、グループ傘下の大手証券会社との合併再編話では、
社内の派閥間で思惑が飛び交い、主導権争いが起こります。
不良債権で汚れたバランスシートの膿を出す経営改革では痛みを伴う決断が迫られ、
銀行内部に渦巻く隠蔽体質との闘いも浮上します。
こうした経営上の課題の裏側では、常に権力闘争が絡んでいました。
頭取・竜崎と、かつての頭取で現在は相談役の栗原との間で
次期トップの座を巡る人事抗争が水面下で進んでおり、
双方が社内の勢力を巻き込んだ暗闘が繰り広げられていたのです。
寺田もまた広報という立場を駆使し、情報操作や根回しなど裏舞台で竜崎を支えるべく奔走します。
寺田は上司である竜崎に従いながらも、
自身の出世のためなら手段を選ばなくなっていきます。
時には社内規定や銀行マンの倫理を逸脱するような“掟破り”の策にも手を染めていき、
清濁併せ吞む覚悟でこの権力ゲームにのめり込んでいきます。
自分の部下や周囲の人間さえ駒として利用し、敵対勢力を出し抜く寺田。
しかしその過程で、かつての真面目で良識的だった彼の姿は少しずつ歪んでいきます。
組織内の人間関係は常に疑心暗鬼で、信用できる者は誰もいません。
「裏切り者は、中にいる!」というコピーのとおり、
味方だと思っていた同僚が内部で情報を漏らすなど、敵は常に身内に潜んでいる状況なのです。
寺田自身、上司の信頼に応えるために奔走する一方で、
最後にはその上司からも疑念を持たれたり、自らの立場が脅かされたりする危機にさらされます。
追い詰められた寺田は、生き残りを懸けてある「切り札」を手に入れるに至ります。
それは竜崎と栗原、両陣営の命運を握るような極秘情報でした。
自らが握ったこの一手を武器に、寺田は社内抗争を終局へと導こうとします。
果たして最後に権力の座に立っているのは誰なのか。
『よこどり 小説メガバンク人事抗争』の感想
銀行小説が描く人間ドラマの真髄を描いた物語
まず本作は、バブル崩壊後の停滞期におけるメガバンク内部の栄枯盛衰が、
生々しい筆致で描かれていると感じました。
冒頭に示される竜崎頭取の信条である
「部下の手柄は上司のもの、上司の失敗は部下のせい」からして衝撃的ですが、
この昭和の論理とも言える価値観がまかり通る銀行社会の実態が物語の骨格になっています。
上司が部下の功績を横取りし失敗の責任を押し付けるという不条理なヒエラルキーが公然と語られ、
それに従わざるを得ない部下たちの苦悩が伝わってきました。
派閥争いに敗れて一度失敗すれば出世コースから外れるという銀行特有の厳しさや、
幹部が自分の子飼いの部下だけを引き立てる体質などもリアルに描かれており、
「銀行の常識は世間の非常識」とも揶揄される閉鎖的な企業文化がひしひしと伝わってきます。
著者の小野一起氏は元共同通信の経済記者という経歴を持ち、
本作でも銀行業界の内幕が細部までリアルに再現されているのはその経験ゆえでしょう。
こうした実社会に根ざしたディテールは、本作に重厚な説得力を与えていると感じました。
また人間関係のドラマという点でも、本作は非常に読み応えがあります。
登場人物たちの野心と保身が渦巻く心理戦は緊張感たっぷりで、手に汗握る場面の連続です。
とりわけ主人公の寺田の変貌ぶりには目を見張るものがありました。
物語当初の寺田は慎重で良識的な銀行マンでしたが、
出世への欲に目がくらみ徐々に自分を見失っていく様子が痛烈に描かれています。
上司に従順だった男が、権力闘争の渦中で信念をねじ曲げ、時に裏切りすら辞さなくなる。
その過程は決して一夜にして起こる劇的な転落ではなく、
少しずつ倫理観が侵食されていく様として描かれており、
「自分ならどうしてしまうだろうか」と読んでいてゾッとさせられるリアリティがありました。
社内では誰を信じていいか分からない疑心暗鬼の連続で、
味方だと思っていた人物に後ろから刺されることもある。
まさに「敵は身内にあり」です。組織内の裏切りと報復の応酬には背筋が寒くなる思いでしたが、
その一方でスリリングで物語に引き込まれる魅力にもなっています。
劇中ではまさに上司が飼い犬に手を噛まれるような場面もあり、
裏切りに次ぐ裏切りの展開から目が離せません。
本作は銀行を扱ったフィクションとして、
どうしても池井戸潤氏の『半沢直樹』シリーズなどと比較して語りたくなります。
痛快な勧善懲悪で知られる『半沢直樹』に対し、
本作『よこどり』はもっと地に足の着いた渋いリアリズムがあります。
主人公が「やられたらやり返す」といった決め台詞を放ったり
劇的な逆転劇を演じたりするような派手さはありません。
そのぶん、物語は淡々と現実に即して進行し、
読後には「本当にありそうだ」と感じさせる重みが残ります。
派手な演出がないことで逆にリアルな銀行員たちの姿が浮き彫りになっており、
静かな迫力がある作品だと思います。
もちろん内部告発的な要素や権謀術数の駆け引きは十分にスリリングなので、
エンターテインメント小説としての面白さもしっかり兼ね備えています。
派手さはなくとも銀行という世界の暗闘をここまで丁寧に描いた作品は貴重であり、
その点で本作は大人向けの社会派金融ドラマと言えるでしょう。
また、本書は単なるフィクションの枠にとどまらず、
日本経済が長期停滞に陥った「失われた30年」の本質にも鋭く切り込んでいると感じました。
作中では、古い体質の銀行ビジネスに見切りをつけ
「銀行ビジネスはもうオワコンだ」と言い放つIT企業の経営者・木谷という人物も登場します。
彼はテクノロジーの力で金融を再生しようという意気込みを語り、
旧態依然とした銀行幹部たちと対照的な存在として描かれていました。
これは現実においても、既存銀行がイノベーションの波に乗り遅れ
内部抗争に明け暮れていたことが経済停滞の一因だったのではないか、という問いかけにも読めます。
実際、竜崎と栗原といった権力者たちが派閥争いに明け暮れる一方で、
銀行の業績そのものは悪化し深刻な不良債権を抱え込んでいたという状況が描かれています。
内部で足の引っ張り合いをしている間に時代に取り残されていくという皮肉が、
本作の底流には流れているように思いました。
エンタメ性の高い権力ドラマとして楽しませつつ、
読み終えた後には社会への洞察をも感じさせる点で、
単なる銀行内幕小説に留まらない深みを持っていると評価できます。
全体として、権謀術数渦巻く金融業界を舞台にした骨太の小説であり、大変満足度が高かったです。
息詰まるような社内抗争の描写に引き込まれつつも、
ふと「組織とは何なのか」「出世とは何のためか」といった根源的な問いも
突き付けられるような読後感がありました。
野心と器は別物だというメッセージがラストで示唆される点にも考えさせられます。
野心だけで突き進んだ人間が必ずしも報われるわけではなく、
組織の論理の中では個人の人生があまりにも無力である
そんな現実を突きつけられる結末には、ある種の虚しさも感じました。
しかし同時に、それでも組織の中で
自らの意義を見出そうともがく人間のドラマには強い共感も覚えます。
善悪がはっきりしないグレーな世界で、
それでも必死に足掻く登場人物たちの姿は、現代の働く人々にも通じるものがあると思いました!
最後に
ここまで本書について紹介してきました。
銀行というクローズドな組織社会を舞台に、
人間の欲望と裏切りをこれでもかと描き切った本作はフィクションでありながら、
私たちが日々身を置く組織生活の現実とも地続きに感じられるリアリティがあります。
本書が気になる方は、是非手に取ってみてください!
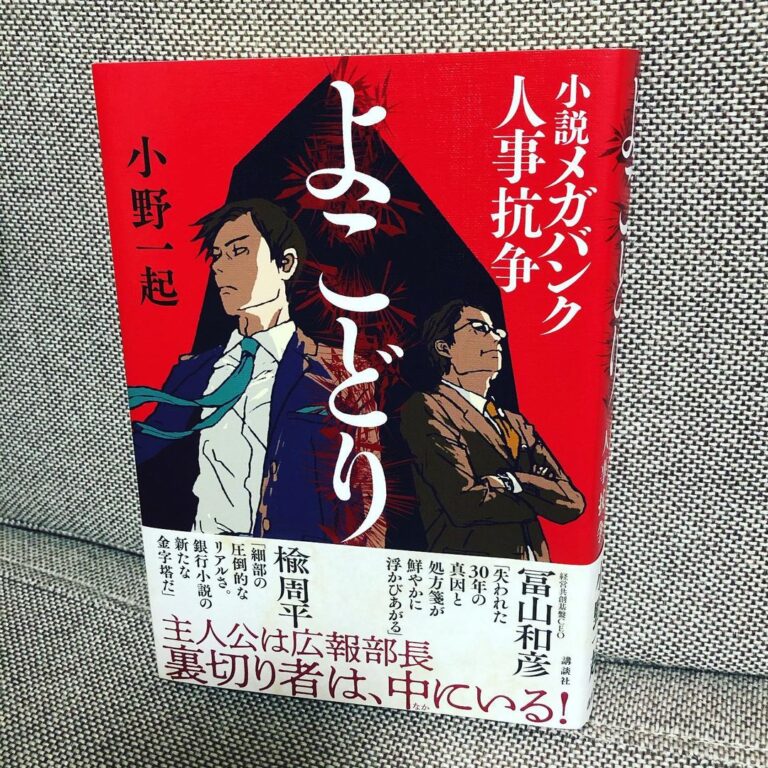
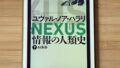
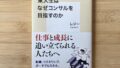
コメント