こんにちは!しょーてぃーです!
今回は、レジーさんの
『東大生はなぜコンサルを目指すのか』について紹介をしていきます!
『東大生はなぜコンサルを目指すのか』について
本書の概要
本書はひとことで言うと
仕事と成長に追われる現代人に問いを投げかける1冊です。
本書をオススメしたい人
- 常に「もっと成長しなきゃ」と自分を追い立ててしまうビジネスパーソン
- コンサル業界に興味がある人
- 若手エリート層のキャリア観や、現代の働き方における「成長」ブームの流れを理解したい人
本書は、東大生の就職人気トップをいつの間にか独占するようになった
「コンサル」という職業を題材に、現代ビジネスパーソンを取り巻く
「成長しなければ」というプレッシャーの正体を解き明かした1冊です。
就活ランキングの上位にコンサルティングファームがずらりと並ぶ時代、
その背景に著者は「転職でキャリアアップ」「ポータブルスキルを身につけろ」といった
勇ましいスローガンの裏側に、「仕事で成長し続けよ」と課せられ
不安を募らせる人々の姿があると指摘します。
本書ではコンサル業界の台頭を切り口に、現代の成長至上主義を批判的に分析し、
「我々が本当に向き合うべき成長とは何か」を鮮やかに描き出します。
最新の就職動向や若者のホンネ、さらにはマンガ・音楽・お笑いといった
ポップカルチャーの事例まで引用しながら、
働くことと成長することの意味を問い直す内容になっています。
『東大生はなぜコンサルを目指すのか』のまとめ
東大生がコンサルを目指す時代背景
本書の発端となる問題意識は、
「なぜ優秀な東大生たちがこぞってコンサルを志望するようになったのか」という疑問です。
実際、近年の東大・京大生の就職人気ランキングでは
トップ10社中7〜8社がコンサルティングファームやシンクタンクという状況になっています。
かつて官僚やメガバンクが定番だった高学歴層の就職先は、この10年ほどで様変わりしました。
本書ではこの現象を一つの入口として、
現代社会に蔓延する「成長圧力」の実態に切り込んでいきます。
著者によれば、コンサル人気の根底にあるのは
「安定したいから成長したい」という逆説的な心理です。
終身雇用制が崩壊した今、もはや一つの会社にしがみつけば安泰という時代ではなくなりました。
代わりに「どこに行っても通用するスキル」を身につけて自分で稼ぐ力をつけること、
すなわち成長し続けることこそが新しい安定の形になっていると本書は指摘します。
実際、34歳以下の若手の8割以上が「終身雇用を期待していない」とする調査結果も紹介され、
誰も自分を守ってくれない時代においては
自分の身は自分で守るしかないという認識が広がっているといいます。
そのためにはビジネスで通用する実力=ポータブルスキルを身につける必要があり、
「成長できる環境」に身を置きたいと願う若者たちにとって、
コンサルティングファームが最適解に映っているのです。
具体的にコンサルファームが人気な理由として、本書ではいくつかの特徴が挙げられています。
第一に、年功序列ではなく若いうちから大きな意思決定に関われる機会があることです。
メーカーなどでは経営全体を俯瞰できるポジションに就くまでに何十年とかかるかもしれませんが、
コンサルなら新卒数年目から経営戦略や企画に近い仕事を任される可能性があります。
実際に東大卒で大手コンサルに新卒入社した若手へのインタビューでも、
「20年かけてようやく得られる立場を、若手のうちに経験したかった」という声が紹介されています。
第二に、都市部で高収入を得られるという現実的な条件も魅力です。
東京で働けて年収も高いとなれば、他業種と比較して
「総合的に考えると結局コンサルになるよね」というのが
学生たちの率直な感覚だと本書は伝えています。
さらに第三の理由として、「一度コンサルで働けばどこへでも転職できる」という
汎用性への期待があります。
コンサルティング業界で数年修行すれば、
次のキャリアの自由度が増す、安全な選択肢だと見なされているのです。
本書のタイトルにある「東大生はなぜコンサルを目指すのか」という問いに対する一つの答えは、
「将来の安定のために今はコンサルで成長する」という選択だと言えます。
しかし著者は、東大生に代表される“肉食系”に見える若者たちの内面は
実は非常に保守的であり、「安定したい、だから成長したい」という
切実な思いから動いているのだと分析します。
そしてこの傾向は高学歴層に限らず、
現代の多くのビジネスパーソンにも共有されている価値観だといいます。
「現状維持は後退である」というメッセージがあらゆる場所で飛び交い、
常に自己研鑽とスキルアップを求められる風潮。
就職や転職の場面でも「成長できること」が最重視され、
「成長こそ正義、それを目指さないのは敗北」といった
極端なメッセージが氾濫している現状に、著者は強い危機感を示しています。
例えばNewsPicksなどスタイリッシュなビジネスメディアが煽った上昇志向礼賛の空気もあり、
若手は否応なく「成長し続けないと生き残れない」という
終わりなき競争に駆り立てられているのではないか。
本書は、そうした成長信仰に囚われた時代の空気を徹底的に検証し、読者に問い直します。
「そもそも、そんなにまでして追い求める“成長”とは何のためのものなのか?」と。
コンサル思考の背景とその功罪
本書の中盤では、コンサルという職業が
若者だけでなく社会全体に浸透させつつある思考様式にもスポットが当たります。
著者は「コンサル的な思考・文化を至上視する言説」が
不安定な時代にうまくはまっていると指摘します。
終身雇用崩壊による「確かなスキルを身につけよ」というムード、
旧来型の日本企業(JTC)的な動きの遅さ・あいまいさへの嫌悪感、
迅速で論理的な解決策を求める空気
そういった背景がある中で、ファクト(事実)重視やフレームワーク活用といった
「コンサル思考」が理想のスタイルとしてもてはやされているのです。
ではそのコンサル的思考法とは何か。
本書によれば、一言でいうと「ファクトベース」と「フレームワーク」の徹底重視です。
コンサルタントは新人であっても大企業の経営陣に提案を行う厳しい現場に立ちますが、
そこで戦う武器になるのが客観的な数字などのファクトと、
物事を構造的に整理するフレームワークです。
例えば「MECE(モレなくダブりなく)」「結論から話せ」「3つにまとめろ」といった
お馴染みのコンサル流の思考術・伝達術があります。
本書でも「PowerPointやExcelで事実を正確に整理し、
そのデータから結論を導き出す一連の所作」こそがコンサルで身につく思考の型であり、
それ自体には確かな価値があると述べられています。
このような論理的思考法や問題解決のフレームワークは、
ビジネスのみならず日常生活でも有用な場面が多いでしょう。
以前なら感覚や属人的に決めていたことも、
客観指標で大局的に判断できるようになるのは確かです。
しかし著者は、「コンサル思考で成果を上げること」よりも
「コンサルっぽく振る舞うこと」自体が目的化してしまう危うさも指摘しています。
ファクトやロジックを絶対視し、
それに当てはまらないものを論破で“叩きのめす”ような振る舞いがもてはやされると、
コミュニケーションから人間的な温かみが失われてしまうのではないかという懸念です。
いわゆる「論破至上主義」の風潮であり、著者はそれがビジネスの場だけでなく
日常にも支配的になることに警鐘を鳴らしています。
実際、昨今はSNSやテレビでも論理で相手を打ち負かすスタイルが注目されがちですが、
著者は「それで本当に幸せになれるのか?」と疑問を呈しているのです。
コンサル的発想の広がり
本書ではコンサル的な発想が
ビジネス以外の領域にも広がっている実例が豊富に紹介されています。
たとえば、ポップカルチャーの世界に目を向け、
漫画・小説、音楽の歌詞、さらにはお笑い芸人の漫才に至るまで、
その中に「数字で成果を測りPDCAを回す」ような
コンサル的発想が見いだせることが示されています。
著者はエンタメ作品の中に散りばめられた“努力・成長”の物語を分析し、
現代社会の空気を別の角度から照射することで理解を深める仕掛けをしています。
具体例として本書で言及されるのは、近年流行した「タワマン文学」や、
お笑いコンビ「令和ロマン」のネタ分析、
さらには人気アイドル宮脇咲良さんの自己プロデュース論などです。
中でも興味深いのは、著者自身がサッカー日本代表選手たちの著書を比較検証している箇所です。
長谷部誠・本田圭佑・長友佑都といった一昔前の選手の本では
「メンタル」「フィジカル」といった要素が語られていたのに対し、
三苫薫・遠藤航といった現代の選手の本では、データ分析やビジネス思考が前面に出ており、
内容が自己啓発書・ビジネスハック本に近づいているという指摘には思わず唸らされます。
エリートアスリートでさえ「効率的な成長」の文脈で語られる時代
まさにコンサル思考が優秀さの証とみなされる風潮そのものです。
最後に
ここまで本書について紹介してきました。
本書を通じて浮かび上がるのは、
「成長し続けよ」という見えない圧力に現代人がどれほど晒されているかという事実です。
流行や周囲の価値観に流されず、自分なりの軸でキャリアを選ぶことが、
長い目で見て本当の安定と納得感につながるという
当たり前だけれど大切なことに気づかせてくれる1冊でした。
本書が気になる方は、是非手に取ってみてください!
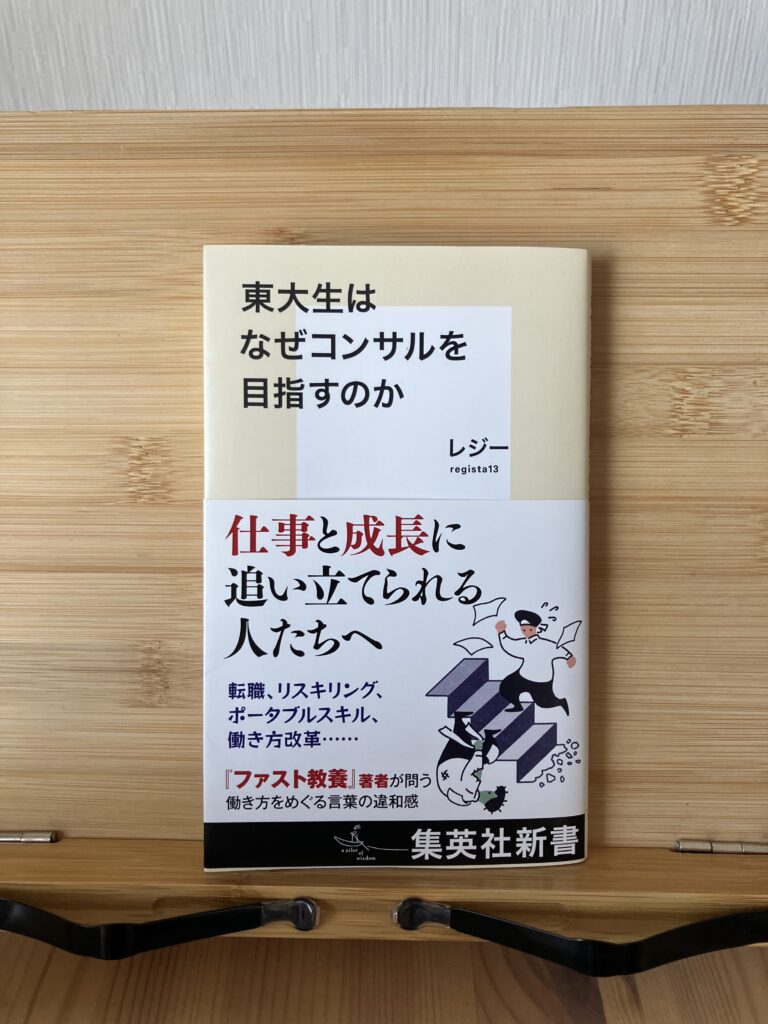

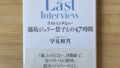
コメント