こんにちは!しょーてぃーです!
今回は、小泉悠さんの
『情報分析力』について紹介をしていきます!
『情報分析力』について
本書の概要
本書はひとことで言うと
情報分析の精度を高める方法を紹介する1冊です。
本書をオススメしたい人
- 情報収集の精度を上げたい人
- 分析をきちんとしたい人
- 正しい情報を識別したい人
本書は、膨大な情報から精度の高い知識を生成するための
思考法と技術を体系立てて紹介する書籍です。
本書は、国家安全保障分野で培われたオープンソース情報(OSINT)の手法を
ビジネスにも応用できるよう翻案したもので、
単に情報を集めることと分析することの違いを繰り返し強調します。
分析は料理に例えられ、良い材料を集めることに加えて、
食べる人のニーズに合わせて加工しなければ情報は価値を生みません。
著者は「意図」よりも「能力」に注目し、相手が何を考えているかを憶測するよりも、
現実に何ができるかを基盤に仮説を立てることを勧めます。
また、情報収集は背景情報・コア情報・現場情報の三層で構造化し、
OSINTだけでなく現地取材や専門家との交流による
「足で稼ぐ情報」の重要性を強調します。
分析過程では仮説を立て、データ整理やグラフ化を通じてパターンを見出し、
執筆によって思考の偏りや欠落を自覚しながら
何度も循環させる姿勢が推奨されています。
情報の受け手や目的に応じて解像度や論点を調整し、
偏見を避けるために対象の思考様式を頭の中に再現することの必要性を説き、
自らの判断力を高める手引きとなっています。
『情報分析力』のまとめ
情報とインテリジェンスの違い
本書の中心にあるのは、「情報」と「インテリジェンス」の違いを理解することです。
情報とは単なる断片的な事実やデータであり、
インテリジェンスとはそれらを分析・統合して、判断や行動に役立つ形に加工したものです。
著者は、情報は誰でも手に入るが、
それを目的に応じて調理する能力こそが欠けていると指摘します。
同じ素材を使っても、経験豊かな料理人ほどおいしい料理を作るように、
分析者は情報を整理し、受け手が理解しやすい形に加工しなければなりません。
著者は国家安全保障分野で培った経験から、
公開情報の収集であるオープンソースインテリジェンス(OSINT)の重要性を説きます。
しかし、OSINTだけでは限界があり、「既知の未知」や「未知の未知」を補うためには
現場取材や専門家のネットワークが必要だと述べています。
また、人工知能(AI)も既存の情報を再編成するに過ぎず、
新しい情報を生み出すことはできないと警告し、
情報源への疑問を持ち続ける姿勢を求めています。
意図ではなく能力を読む
多くの情報分析は相手の“意図”を読み解こうとしますが、
著者は「意図はつかみどころがなく推測でしかない」と述べ、
代わりに“能力”を見ることを提案します。
能力とは、人や組織が実際に持っている資源や技術、法制度などであり、
それを基にして相手が取り得る行動の範囲を推定することができます。
例えば軍事面なら装備や兵力、経済面なら資金調達力や工業力が能力です。
意図は時間とともに変わり、表面的な発言で隠されることもありますが、
能力の変化は資料や統計から追跡できます。
著者はこの視点を通じて、噂や憶測に振り回されることなく、
中長期的な予測を立てる重要性を強調します。
三層の情報収集:背景情報・コア情報・足で稼ぐ情報
情報収集を始める際には、まず「目的」と「解像度」を明確にします。
何を知りたいのか、どの程度の精度で知りたいのかを決めることで、
収集すべき情報の範囲と深さが定まります。
本書では情報を三層に分類し、
それぞれの役割を理解することで効率的な収集を提唱します。
背景情報(バックグラウンド)
対象となる国や業界の歴史、制度、文化、思想など幅広い基礎知識を指します。
この層は、異常な事象に気づくための“平常時の地図”として機能し、
経験則や一般的なデータを蓄積します。
コア情報(データ)
具体的な統計や数字、映像、文書など一次資料を指します。
公的報告書や政府統計、企業の決算報告などが含まれ、
これらは比較的容易に入手できますが、
自身にとって重要な部分を抽出しなければ意味がありません。
著者は数値データを単に眺めるのではなく、
表やグラフに整理することで隠れた傾向や変化を掴むことを推奨します。
足で稼ぐ情報(フィールドワーク)
現地取材や専門家へのインタビュー、SNSやコミュニティなど、
紙面では得られない一次情報を指します。
著者は、OSINTに依存しすぎると公開情報の枠内で思考が固定化され、
未知の未知に気づけないリスクがあると警告します。
フィールドワークでは、インタビュイーの背景や文化を理解する“エミュレータ”を構築し、
相手の目線で状況を解釈することが求められます。
仮説を立て、分析し、文章にするプロセス
本書は、分析を単発の作業ではなく循環的なプロセスとして位置づけます。
まず、限られた情報から仮説(予測シナリオ)を設定します。
その仮説を検証するために必要な情報を収集し、分析ツールを使って整理・加工します。
分析結果からさらに仮説を修正し
結論を文章や図表としてまとめることで思考を可視化します。
この一連のプロセスを繰り返すことで
精度の高いインテリジェンスが生まれるのです。
分析ではまずデータをタグ付けし、課題ごとにフォルダやデータベースを作って整理します。
著者は「本を一冊書き終えるとカードボックスが残るように、
情報を分類しておくと後で組み合わせやすい」と述べています。
整理したデータを表やグラフに起こすと、
思いもよらないパターンや変化が見えてきます。
例えば、ある国の装備の更新時期と輸入品の動向をグラフ化すれば、
戦略的な優先順位が見えるかもしれません。
こうした作業はExcelやBIツールなどで誰でも始められます。
仮説とデータを突き合わせた結果をまとめる際には、
結論から先に述べ、理由と根拠、
さらに代替シナリオや条件の変化を明示するフレームワークが役立ちます。
著者は文章を書くことの効用を強調し、
アウトプットすることで自分の思考の欠点や偏りに気づくと述べています。
途中経過でも構わないので、仮説とデータ整理の結果を文章にまとめることで、
次の調査でどの情報が不足しているのかが明確になります。
また、執筆は他者に伝えるためだけでなく、
自分自身へのフィードバック装置でもあります。
エミュレータとバイアスの意識
著者は分析者が持つバイアスについて何度も警鐘を鳴らします。
人間は自分の見たいものだけを見る傾向があり、
相手の意図や性格を無意識に自己投影してしまいます。
このため、相手の文化や常識を理解するための
「エミュレータ」を自分の頭の中に構築することが重要だと説きます。
エミュレータとは、対象国や組織の歴史、政治制度、社会規範、日常生活を徹底的に理解し、
その人々の視点で物事を考える仮想モデルです。
例えば、ペンタゴンの中央庭園にあるホットドッグスタンドを
ソ連の偵察衛星が「機密施設」と誤認した事件は、
アメリカの昼食文化を知らなかったために起きたとされています。
文化的背景を知らずに衛星画像だけを見ても誤解が生じることから、
情報は文脈とセットで解釈しなければならないことが分かります。
エミュレータは単に情報を集めるだけでなく、
その社会の映画や文学、新聞、SNSなどを広く読み、
相手がどう考え、どう感じるかを感覚的に理解することで作られます。
著者は自分の研究対象であるロシアの歴史や文化に浸り、
自分の思考回路とロシアのそれとの間に、橋を架ける努力をしていると述べています。
バイアスを減らすためのもう一つの手法は、異なる視点や反論に耳を傾けることです。
自分の分析が正しいと思い込みすぎると、
異なるデータを無視する「確証バイアス」に陥ります。
本書は、分析結果はあくまで仮説であり、常に修正の余地があると認識するよう促します。
特に安全保障のような複雑な分野では、
複数の専門家や関係者と議論し、異なる仮説を比較する姿勢が重要です。
ケーススタディと「クリスマスツリー現象」
本書ではロシアによるウクライナ侵攻などの
具体的事例を通じて分析手法を示しています。
例えば、侵攻前に公開された情報からロシア軍の配置や演習の規模を分析し、
持続能力を判断する過程が紹介されています。
ここでも意図や威勢の良い発言に注目せず、
兵站や装備の補充状況という「能力」に着目する姿勢が貫かれています。
さらに、情報の提示方法として「クリスマスツリー現象」が紹介されます。
これは、米国のスリーマイル島原発事故でアラームが次々に点灯し、
運転員が重要な異常に気づけなかった事例を指します。
分析者は情報をただ羅列するのではなく、
受け手が理解しやすいように重要度に応じて整理しなければ、
かえって判断を誤らせる恐れがあります。
ビジネスの世界でも大量の指標やチャートを提示しすぎると
経営者が何を重視すべきか分からなくなるため、核心を絞り込む必要があります。
生成AIと情報分析の未来
近年は生成AIが発展し、情報分析にも利用され始めています。
著者はAIの利点を認めつつも限界を指摘します。
AIは既存の情報を再構成して提示することは得意ですが、
未知の状況から新しい知見を生み出すことはできません。
また、AIの出力は参照元を明示しないため、
誤情報やバイアスが含まれている可能性があります。
分析者はAIを道具として使いながらも、
自ら情報の質を判断し、裏付けを確認する姿勢が不可欠です。
特に「未知の未知」に対処するためには、
人間が現場に足を運び、一次情報に触れることが欠かせません。
ビジネスへの応用
本書は国家安全保障の事例から出発していますが、
その原理はビジネスにも十分応用できます。
市場動向や競合分析では、企業の発表やニュースに頼るだけでなく、
財務データやサプライチェーンの構造、人材の流動性といった“能力”を読み解くことが重要です。
例えば、ある企業が新規事業に参入する意図を推測するよりも、
研究開発費や人材採用の変化から実際の準備状況を把握した方が確実です。
背景情報としては業界の歴史や規制、過去のトレンドを学び、
コア情報としては決算や市場データを分析し、
現場情報としては展示会での会話やSNS上のコミュニティから
得られる細かな情報を取り込むことができます。
レポート作成では経営層が限られた時間で全体像を掴めるように、
結論を先に示し、根拠となるデータや想定シナリオを整理することが大切です。
また、仮説を複数立て、ベストケース・ベースケース・ワーストケースなどの
シナリオ分析を提示することで、不確実性に備えた意思決定が行えます。
個人の情報収集装置を作る
本書が強調するもう一つのテーマは、
「自分の頭の中に情報処理装置を作る」ことです。
情報は人によって解釈が異なり、
同じ素材でも見えてくるものが変わります。
著者は、関心を持つ分野について日頃から本や論文、
ニュースを幅広く読み、自分なりの分類体系やタグ付けを行うことで、
頭の中に検索エンジンのような装置を育てることを勧めています。
この装置が発達すると、新しい情報を得たときに関連する過去のデータが
即座に呼び出され、分析の深度が増します。
装置作りの第一歩として、まずは関心のあるテーマを一つ選び、
その分野の背景書や専門書を読み込むことが推奨されます。
次に、ニュースやSNSをウォッチし、
興味を持った記事やデータをメモアプリやノートに保存します。
その際、日付や出典、キーワードを必ず記録し、後で検索しやすいようタグを付けます。
集めた情報を定期的にレビューし、
仮説を立てたり他の情報と結びつけたりする習慣をつけると、分析能力が格段に向上します。
執筆も装置の一部です。
著者は、「アウトプットできないのはインプットが足りないからではなく、
途中の思考が見えないからだ」と述べ、書くことによって自分の頭の中を可視化し、
足りない情報や矛盾を発見できると説明します。
初めは短いメモやブログでも良いので、
定期的に文章にまとめることで、分析の解像度が上がります。
最後に
ここまで本書について紹介してきました。
情報収集・分析・執筆というサイクルを何度も回しながら、
仮説を更新し続ける姿勢が重要だと教えてくれます。
本書が気になる方は、是非手に取ってみてください!
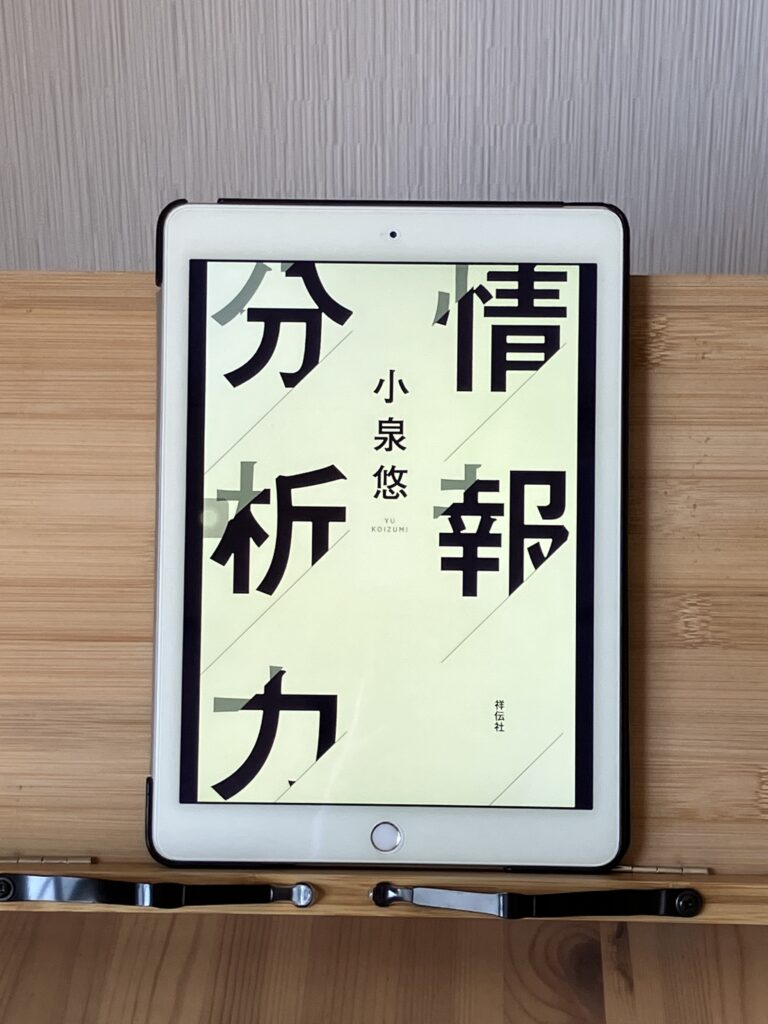

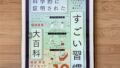
コメント