こんにちは!しょーてぃーです!
今回は、高杉康成さんの
『キーエンス流 性弱説経営』について紹介をしていきます!
『キーエンス流 性弱説経営』について
本書の概要
本書はひとことで言うと
人間の「弱さ」を前提に組織を強くする経営哲学が紹介されている1冊です。
本書をオススメしたい人
- マネジメント層で組織改革に悩んでいる人
- 業務効率や営業力を高めたい人
- キーエンスの企業文化や成功要因に関心がある人
本書は、世界有数の高収益企業キーエンスの
成功の原動力となっている「性弱説」いう考え方を、あらゆる角度から解説した1冊です。
著者の高杉康成氏(元キーエンス新商品・新規事業企画担当)は、
「人は善でも悪でもなく弱いものだと捉える」性弱説を経営の前提に置くことが
キーエンスと他社との決定的な違いだと指摘します。
本書では、この性弱説の概念とキーエンスが採用する
具体的な仕組み・制度の成り立ちや役割を学びながら、
自分自身の働き方や組織マネジメントを改革するヒントが紹介されています。
例えば、顧客対応、商品開発、営業手法、人事評価など企業活動のあらゆる場面で、
性弱説に基づいた独自の取り組みがなされていることがわかります。
キーエンスは売上高約1兆円・営業利益率50%超という驚異的な実績を誇りますが、
その陰には「人間は本来弱い生き物である」という前提に立った緻密な仕組み作りがあります。
『キーエンス流 性弱説経営』のまとめ
性弱説とは何か?従来の性善説・性悪説との違い
本書のキーワードである「性弱説」とは、
「人は善人でも悪人でもなく、本来弱い生き物である」とする考え方です。
古代中国の孟子の性善説(人は本来善である)や
荀子の性悪説(人は本来悪である)になぞらえた表現ですが、
高杉氏はこれを現代の経営に再解釈して適用しています。
性弱説のポイントは、人間は意思が強く完璧ではないゆえに
「放っておけばミスをするし、楽な方へ流されてしまう」という前提に立つことです。
決して「人を信頼しない」という意味ではなく、
「うまく目的を達成するには人間の弱さを織り込んだ仕組みが必要だ」という発想です。
この視点に立つと、経営者やマネージャーは
「マニュアルを作ったから大丈夫」「任せればきっとやってくれる」という楽観に頼らず、
想定外のミスや抜け漏れをカバーする体制を用意するようになります。
本書では、性弱説という一見ネガティブにも思える前提が、
実は組織の慎重さ・協調性・リスク管理意識を高め、
結果的に強い企業を作る原動力になることが示されています。
性弱説経営が生み出す具体的な仕組みと文化
著者によれば、キーエンスの社内制度や文化でこれまで語られてきたものは
すべて「性弱説」を基点に整備されていると言っても過言ではありません。
本書ではその具体例が各所で紹介されています。
徹底した事前・事後フォロー(外報の活用)
キーエンスでは営業担当者が顧客と面談する際、
上司と事前に打ち合わせ(外報)を行い、終了後にも振り返りミーティングを徹底します。
人は経験や立場によって「当たり前」と思う基準が異なり、
放置すると上司が期待した伝達事項を部下が伝え漏らすことも起こり得ます。
そこで事前に面談シナリオや提案資料を上司とすり合わせ、「抜け漏れのない準備」を行います。
また面談後は上司がフォローの電話を顧客に入れる文化もあり、
担当者が聞き出せなかった課題を掘り起こすなど万全を期す仕組みです。
「顧客の声」を額面通り受け取らない商品開発
一般的な企業では顧客要望を聞いて新商品開発に生かしますが、
キーエンスは顧客自身も気づいていない潜在ニーズを重視します。
人は新しいことや難しいことを敬遠しがちなので、
顧客の要望通りの製品を作っても本当に売れるとは限らないという考えです。
代わりに、顧客の業務フローや社会環境の変化まで踏み込んで課題を発見し、
「お客様が本当に望んでいた価値」を提案するよう努めます。
例えば「顧客の要望や意見をそのまま製品に反映させるだけでは不十分で、
隠れた不満を先回りして解決する発想」が重要と説かれています。
この視点に立つことで、競合他社が気づかない革新的な商品アイデアを生み、
高付加価値製品として高い利益率で販売することにつなげているのです。
著者も「大きな困りごとを解決する商品を作り、それをしっかり顧客に伝えれば高く売れる」と述べています。
実際キーエンスは「世界初」「業界初」の製品を次々と市場に投入し、
高価格でも顧客に選ばれる戦略を取っています。
属人化させない営業力と仕組み化
キーエンスの営業と聞くと個人の頑張りやスキルが突出しているイメージがありますが、
本書を読むと誰でも成果を出せるよう工夫された仕組みが存在することがわかります。
たとえば新人でも即戦力となる徹底した研修とOJT、
ロールプレイングによる営業トークの事前練磨、
さらには営業プロセスを細かく数値管理することで「うまくいかない要因」を潰していく手法です。
具体的には、「ニーズの構造化」のために
「誰が」「現状どのように」「何が問題で」「どれくらい困っているか」という
4要素でヒアリング内容を整理するフレームワークを使い、提案精度を高めています。
また、営業現場では「営業情報(いつ・誰に・いくらで)」「仕様情報(どんなサイズ・特長か)」
「開発情報(どう使えるか、なぜ今ではダメか)」の3種類の情報を必ず揃えるよう指導し、
顧客への提案に漏れがないようにしています。
これらはトップ営業だけのノウハウではなく、
仕組みとして全員が実行できる形で平準化されている点がポイントです。
人頼みではなく仕組み頼みで営業力を底上げしているわけです。
厳格かつ公平な目標設定と評価
性弱説の視点では「人は放っておくとサボりがち」であるため、
組織には適切なプレッシャーが必要になります。
しかしプレッシャーのかけ方を間違えると士気が下がるため、
キーエンスは高い目標と高い報酬を両立させる独自の評価制度を敷いています。
例えば、営業目標については「12カ月連続で目標達成できるようなら、その目標設定を疑え」とし、
安易な目標引き下げによる形だけの達成を良しとしません。
もし実力以上に低いノルマを与えて達成させ、
それを称賛するようでは真に頑張っている社員が報われず不公平になってしまうからです。
そこで、KPIから逆算した納得感ある高い目標を設定し、
達成して初めて正当に評価する文化があります。
また成果に対しては業界でも突出した高インセンティブを与え、
社員のモチベーションを最大限引き出しています。
「頑張る人に損をさせるな」という考え方が徹底しており、
社員同士で不公平感が生じないよう評価制度を設計している点も印象的です。
反面、成果が出なければ容赦なく昇給・昇格に差がつくため、常に緊張感もあります。
この飴と鞭のバランスこそ、性弱説経営における
「恐怖とモチベーションのあいだ」をマネジメントするポイントといえるでしょう。
緻密な業務管理と生産性意識
キーエンスでは日報を1分単位で付けるような
徹底した時間管理・業務報告の仕組みがあるとも紹介されています。
一見やりすぎにも思えるマイクロマネジメントですが、
こうした管理が社員一人ひとりの仕事の「密度」を高め、高収益体質を支えているのです。
実際、本書ではキーエンスの付加価値生産性(= 売上総利益÷総労働時間)は
時間あたり3万円という驚異的な数値が示されています。
これは一般的な企業と比べても圧倒的に高い水準で、
短い時間で大きな付加価値を生み出していることを意味します。
これを可能にしているのが、全社員の徹底した効率追求とムダ排除の習慣です。
例えばクレームが発生すれば原因を最後まで究明し再発防止策を講じる、
ノウハウはマニュアル化して誰でも再現できるようにする、といった
継続的な業務改善も性弱説に根ざした文化と言えます。
「人間は放置すれば怠けるかもしれないが、
データで現状を見える化しフィードバックすれば必ず改善できる」という信念があり、
PDCAサイクルを高速で回し続ける企業風土が築かれています。
これは決して精神論ではなく、
科学的かつ論理的に人間の行動特性に向き合った経営スタイルなのです。
パートナー企業とのWin-Win関係
性弱説の視点は社内だけでなく社外との関係にも現れます。
キーエンスは創業以来自社工場を持たないファブレス経営を貫き、
製造は協力会社に委ねています。
協力会社も人間の集まりであり、無理難題を押し付ければ
関係が悪化しビジネスが破綻する恐れがあります。
そこでキーエンスは協力会社と共存共栄するための仕組みを構築しています。
その一例が「仕様の見切り」と呼ばれる方針です。
例えば他社が「最新機能も盛り込み、サイズも小さく、でも価格は安く」と
無理な要求をする状況でも、
キーエンスは「最新機能は盛り込むがサイズは現行品と同じで構わない、
できる範囲でコストダウンしてほしい」と依頼するのです。
サイズを妥協することで生産は格段に楽になり、
結果的に協力会社は利益を確保しつつ他社より安い価格で提供できます。
要するに、自社の要求を少し抑えることで相手にもメリットを与え、
長期的な信頼関係を築く戦略です。
人間は目先の損得で動きがちという弱さを見越し、
短期的なコスト削減より長期的な安定供給と品質確保を優先するように
ビジネスに関わる全ての人の弱さと向き合い、仕組みで支えるのがキーエンス流なのです。
以上のように、本書ではキーエンスの具体策が多面的に紹介されています。
それらは一貫して「人間は完璧でない」という前提から生まれた創意工夫であり、
弱さを責めるのではなく弱さを補う仕組み作りにフォーカスしている点が特徴です。
性弱説経営は単なるスパルタ式の管理強化ではなく、
社員全員が成果を出せる環境を整備することで
結果的に組織全体の力を引き上げるアプローチと言えます。
一般企業への示唆と応用
「とはいえ、うちの会社でキーエンスの真似なんてできない…」と
思われる方もいるかもしれません。
しかし著者は、「キーエンスと同じ水準で実践する必要はない」と強調します。
本書の終盤では、中小企業や他業種でも
一部分から性弱説のエッセンスを取り入れる方法が議論されています。
たとえば先述の仕組みのうち、
取り入れやすいものから試してみるだけでも効果は大きいといいます。
実際、「キーエンスの半分程度の密度で働ける仕組みを一部でも持てれば、
その時点で一般的な会社では間違いなく優秀な社員になれる」という
前向きなメッセージが綴られています。
これは裏を返せば、どんな職場でも
人間の弱さを補完するちょっとした工夫で生産性や業績が大きく向上し得るということです。
特に日本企業のこれからの組織作りにおいて、
性弱説的な発想(謙虚にリスクに備え、仕組みで人を活かす)が
競争力強化のカギになるかもしれないと本書はそう示唆しています。
最後に
ここまで本書について紹介してきました。
論理的な分析と具体例を通じて
「人間の弱さを前提にした経営」というユニークな視点を提示してくれる1冊でした。
読後には、「なぜキーエンスがあれほど高い業績を維持できるのか」の理由に
深く納得すると同時に、私たち自身の働き方を見直すヒントも数多く得られます。
人を性善説でも性悪説でもなく性弱説で見る発想は、一見すると厳しいようですが、
実は部下や自分を責めるのではなく支えるための智慧であると感じました。
本書が気になる方は、是非手に取ってみてください!
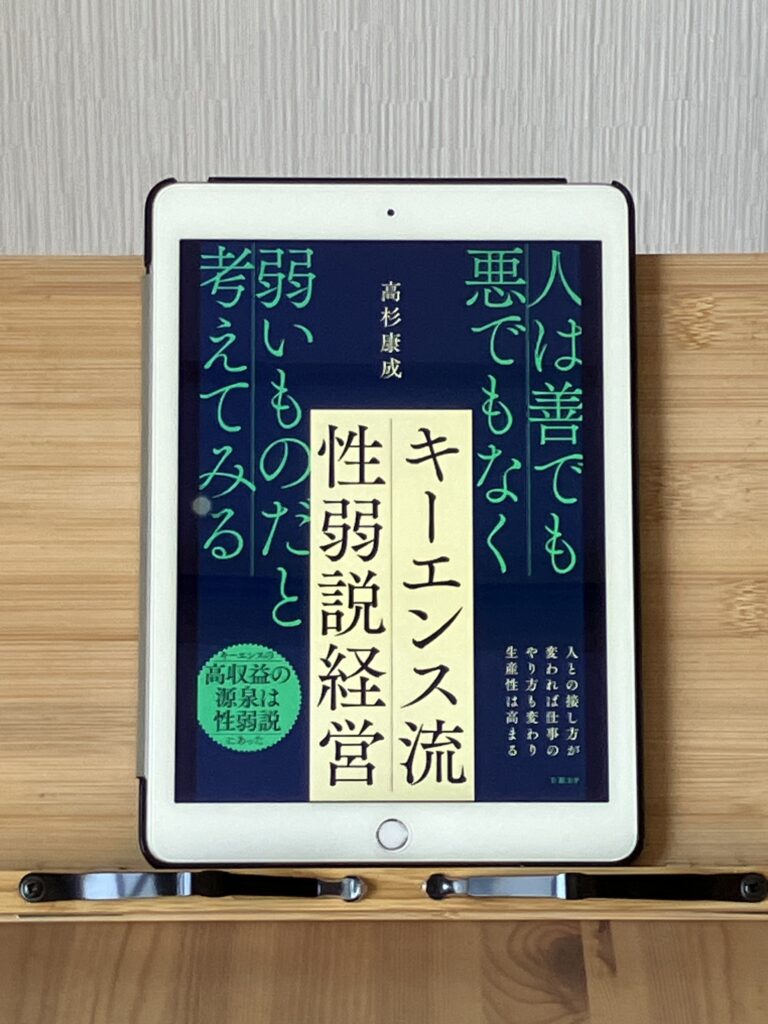

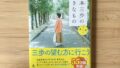
コメント