こんにちは!しょーてぃーです!
今回は、中村文則さんの
『逃亡者』について紹介をしていきます!
『逃亡者』について
本書の概要
本書はひとことで言うと
歴史の闇を走り抜ける、魂の逃亡劇を描いた物語です。
本書をオススメしたい人
・歴史の陰にある社会問題に興味がある人
・哲学的なテーマが好きな人
・ダークな社会派ミステリー・文学作品が好きな人
本作は、愛する人を失ったジャーナリスト・山峰健次が、
「悪魔のトランペット」と呼ばれる戦時中の遺物を巡って逃亡する物語です。
舞台は現代のヨーロッパからアジア、そして日本の長崎へと広がり、
山峰はトランペットにまつわる忌まわしい歴史や、
隠された戦争の記憶と向き合うことになります。
物語は逃亡劇の体裁をとりつつ、戦争、宗教、差別、監視社会といった
社会的テーマを鋭く描き出します。
追跡者・Bの存在は暴力や権力の象徴であり、
現代社会の不条理や正義の不在を浮き彫りにします。
多層的な構成、緊迫感ある文体、美しい筆致に支えられた本作は、
フィクションと史実、個人と社会、罪と赦しが交錯する重厚な文学作品です。
読む者の倫理観や想像力を揺さぶる、現代の「問いかける小説」です。
『逃亡者』のあらすじ
あらすじの概要
「一週間後、君が生きている確率は4%だ」
突如始まった逃亡の日々。
男は、潜伏キリシタンの末裔に育てられた。第二次大戦下、”熱狂””悪魔の楽器”と呼ばれ、ある作戦を不穏な成功に導いたとされる美しきトランペット。あらゆる理不尽が交錯する中、それを隠し持ち逃亡する男にはしかし、ある女性と交わした「約束」があったーー。
キリシタン迫害から第二次世界大戦、そして現代を貫く大いなる「意志」。中村文学の到達点。信仰、戦争、愛ーー。
この小説には、
その全てが書かれている。いつか書くと決めていた。ーー中村文則
逃亡者 より
悪魔の楽器が導く逃避行の果て
フリージャーナリストの山峰健次は、愛するベトナム人の恋人・アインを
ある事件で失った深い喪失感から人生に倦み、ヨーロッパを放浪していました。
山峰はひょんなことから、
第二次世界大戦中に従軍した楽隊員が遺したトランペットを手に入れます。
このトランペットは、かつて日本軍の作戦を成功に導いたとされる
悪魔の楽器と呼ばれる代物で、世界中の組織や個人が
喉から手が出るほど欲しがる伝説の品でした。
やがて山峰の元に現れた謎の男「B」と、
新興宗教団体「Q派の会」の一団がこの楽器を奪おうと襲来し、
山峰は命からがら街から逃亡を図ります。
こうして彼の長い逃避行の日々が始まるのでした。
追っ手から逃れ各地を転々とする中、
山峰は悪魔のトランペットに纏わる忌まわしい過去を徐々に知ることになります。
それは歴史の闇に埋もれた、日本が引きずる暴力と狂気の記憶でした。
物語は現代と過去を行き来し、
ヨーロッパからアジアへと舞台を移しながら進行します。
逃亡の途上、山峰はトランペットの来歴を追って日本の長崎へ辿り着き、
この地に刻まれた史実と向き合うことになります。
長崎では江戸期の潜伏キリシタン迫害から原爆投下まで、
土地が抱える痛ましい歴史が浮かび上がり、
奇しくも山峰自身のルーツもそこに繋がっていることが明らかになります。
実はアインの遠い先祖にも、長崎で日本人とポルトガル人の間に生まれた女性がおり、
山峰の先祖もまた長崎で迫害を受けた隠れキリシタンだったのです。
山峰と亡き恋人アインは、知らず知らずのうちに
同じ歴史の痛みを背負っていたのでした。
一方、逃亡劇はますます異様さを増していきます。
超人的な謎の男Bは執拗に山峰を追い詰め、
その行く先々に不気味な影を落とします。
Bは山峰を苦しめるために、狂気じみた3つの選択肢を突きつけました。
選択肢1は「拷問の果てに殺す」という死、
2は「山峰が今後人生で幸福を感じた瞬間に殺す」という呪い、
3は「この世界で山峰が最もなりたくない存在」、
すなわち差別主義者に「生まれ変わらせる」というものでした。
祖国を強国に翻弄されてきたベトナム出身のアインを愛した山峰にとって、
「差別主義者になること」が何よりも忌まわしい罰となるのです。
冷酷非道なBの言動に、山峰は絶望的な追いつめられ方を感じ、
自分自身の生にすら執着を失いかけます。
しかし物語の中盤、山峰は長い逃亡に観念して過去と向き合う決意を固めます。
ただ逃げ回るだけではなく、自らトランペットに秘められた真実を解き明かし、
その歴史の呪いと対峙しようと考えたのです。
トランペットの由来を探る中で、
山峰の脳裏には大戦末期のフィリピン戦線の情景が蘇ります。
それは、トランペットの元の持ち主である鈴木という
日本兵の従軍手記を通じて描かれる、血生臭くも悲痛な戦場の記憶でした。
鈴木は軍楽隊の一員として極限状態の戦場を進み、
仲間が次々と無残に散る様や、自らも加担した非道の数々を目撃します。
飢えと恐怖、暴力が支配する戦場で、
彼は愛する女性「ヨシコ」の存在を心の拠り所に生き延びようとしていました。
やがて鈴木は自らの最期を悟り、愛するヨシコに宛てて、当
時演奏していた未完の旋律の続きを譜面に起こし、
戦場での日々を記した手記とともに託す決意をします。
現代の山峰はその手記を読み解き、
長崎でついにヨシコ本人と出会うことになります。
ヨシコは鈴木の想い人であり、戦後を生き延びて歳月を重ねた女性でした。
山峰は命懸けで守り抜いた悪魔のトランペットと、
そこに隠されていた鈴木の手記と譜面をヨシコに届けます。
遠い昔に引き裂かれた恋人たちの物語が、
時を超えて今ようやく完結した瞬間でした。
ヨシコは鈴木の遺した旋律に耳を傾け、彼の残した言葉に触れて涙します。
歴史の悲劇に翻弄された一組の男女の愛が、形を変えて現代に救いをもたらしたのです。
こうして山峰は、トランペットにまつわる長い逃亡の果てに、
過去から託された愛と記憶の遺産をしかと次代へ手渡しました。
しかし物語はそれで終わりではありません。
現実の史実とフィクションが入り混じるラストは、
読者に大きな余韻と問いを残します。
すべての出来事が本当に起こったことなのか、
それとも山峰が背負った罪悪感と悲しみが生み出した幻だったのか
謎めいたBの存在も含め、その真相は明確に語られません。
ただ一つ確かなのは、山峰が直面したこの世界の理不尽な真実と、
それでもなお人々を繋ぐ希望の光です。
歴史の闇に飲まれそうになりながらも、
山峰は逃亡者として走り抜いた末に一筋の救いを見出し、物語は静かに幕を閉じます。
『逃亡者』の感想
暴力と権力が映す社会的テーマと文体の魅力
本作は、エンターテインメント性の高い逃亡劇でありながら、
現代社会への鋭い問題提起に満ちた社会派小説でもあります。
物語を貫く大きなテーマの一つは、暴力と権力による抑圧です。
作中には、歴史上および現代における
多様な「加害/被害」の構造が浮き彫りにされています。
第二次大戦下のフィリピンで日本軍兵士たちが行った狂気的な残虐行為や、
従軍慰安婦(性奴隷)問題といった史実がリアルに描かれ、
戦争というシステムそのものが人間を狂わせ、
無慈悲な加害者に仕立て上げる様が克明に示されています。
同時に、原爆投下や江戸時代のキリシタン迫害によって
日本人自身が被害者となった歴史にも踏み込み、
加害者と被害者の立場が時代や状況で、入れ替わる複雑さを浮かび上がらせます。
こうした残酷な歴史に正面から向き合おうとする姿勢は、
本作全体に貫かれており、「過去を直視しなければ改善も成長もない」という
作者の強い信念が感じられます。
現代パートでも、暴力と権力の問題は様々な角度から照射されています。
たとえば、主人公・山峰が深く関わることになる移民・労働搾取の問題です。
恋人アインは留学生として日本に来たものの、
過酷な労働搾取に遭い命を落としました。
これは近年クローズアップされている外国人労働者や技能実習生の
人権問題そのものであり、本作はフィクションを通して
読者にこの社会問題への目を向けさせます。
さらに物語の中核には新興宗教「Q派の会」の存在があり、
これは権力と狂信の危うさを象徴しています。
カリスマ的なQ派のリーダーは、
「差別主義者や排外主義者だって本当は幸福になりたいだけなのだ」と語り、
弱者や憎悪に囚われた者たちさえも包み込もうとする独特の思想を持った人物です。
彼は狂信的でありながら、一面では救済者として描かれ、
宗教が持つ正と負の両面性を体現しています。
このように本作では、宗教と政治、偏見と救済といった
対立する要素が綿密に描き込まれ、
単純な善悪では割り切れない社会のグラデーションが浮かび上がるのです。
また、謎の男Bが示すものも無視できません。
Bは山峰を常に監視し、逃れても逃れても影のようにつきまとう存在で、
その不気味さはさながら全能の監視者のようです。
彼の存在は、現代の監視社会や理不尽な権力のメタファーとも読めます。
Bによる執拗な追跡と心理的な責め苦は、
個人が巨大な悪意から逃れられない閉塞感を示し、読者にも息苦しい緊張を強いるものです。
最終的にBの正体は曖昧なままですが、
その得体の知れなさゆえに、権力そのものの象徴として機能していると言えます。
山峰はBから提示された「公正世界(ジャストワールド)」を信じるかという問い
すなわち「この世界に正義や救いはあるのか」という根源的な問題に、否応なく向き合わされます。
物語は決して誰もが安心できる勧善懲悪には流れず、
むしろそうした安易な物語へのアンチテーゼとして構築されています。
この厳しい現実認識こそが本作の社会的メッセージであり、
不都合な真実から目を背けずにいかに生きるかを読者に問いかけています。
重厚なテーマを内包しながらも、
本作は最後まで読者を引き込む強い物語の推進力を持っています。
その原動力となっているのが、著者の研ぎ澄まされた文体と構成の妙です。
中村作品はしばしば「硬質で重たい」と評される文体を持ちますが、
本作でも暴力や絶望を描く厳かな筆致が随所に光ります。
しかし決して難解なわけではなく、リズミカルで躍動感のある文の運びによって、
読者はむしろドライブ感すら感じながらページを繰ることができます。
特筆すべきは物語の構成で、
本作は非常に国際色豊かなマルチプロットが展開します。
ヨーロッパからアジアへ舞台が移り変わり、
英語・ドイツ語・フランス語・タガログ語など多言語が登場し、
さらには手紙や手記といった異なる文体・形式の挿話が挿入されます。
これらが一見バラバラな断章として積み重ねられながら、
最終的には一つの線に収斂していく構成力は見事という他ありません。
一つの長篇の中に宗教と戦争、移民と音楽、
そして愛という複数の物語が絡み合い、
読むほどにそれらの繋がりが見えてくる展開には思わず唸らされます。
新聞連載から生まれた作品ということで章ごとの独立性もありつつ、
長崎で全ての糸が結ばれるクライマックスでは大きなカタルシスが得られます。
中村文則は本作でドストエフスキー的な
ポリフォニー(多声音楽)の手法に挑戦したと述べています。
すなわち、作者自身の思想とは異なる複数の価値観や思想を
登場人物たちに語らせ、それらを物語の中でぶつけ合うことで、
読者に一面的ではない思考の場を提供しているのです。
例えば、狂信的な宗教家、極悪非道のB、
理想に燃えるジャーナリスト山峰といったキャラクターは、
互いに相容れない主張を抱え、その思想の対決が物語の軸の一つになっています。
こうした多層的な対話劇のおかげで、
読者は一方的な答えを与えられるのではなく、自ら思索することを促されます。
現実の社会問題から目を背けずに描いた本作は、
まさに読む者に「自分自身の在りよう」を問い直させる力を持った一冊だと感じました。
最後に
ここまで本書について紹介してきました。
現代社会の閉塞感に挑み、人間の闇と希望を描き切った本作は、
中村文則さんの表現技法が存分に発揮された意欲作だと感じました!
本書が気になる方は、是非手に取ってみてください!
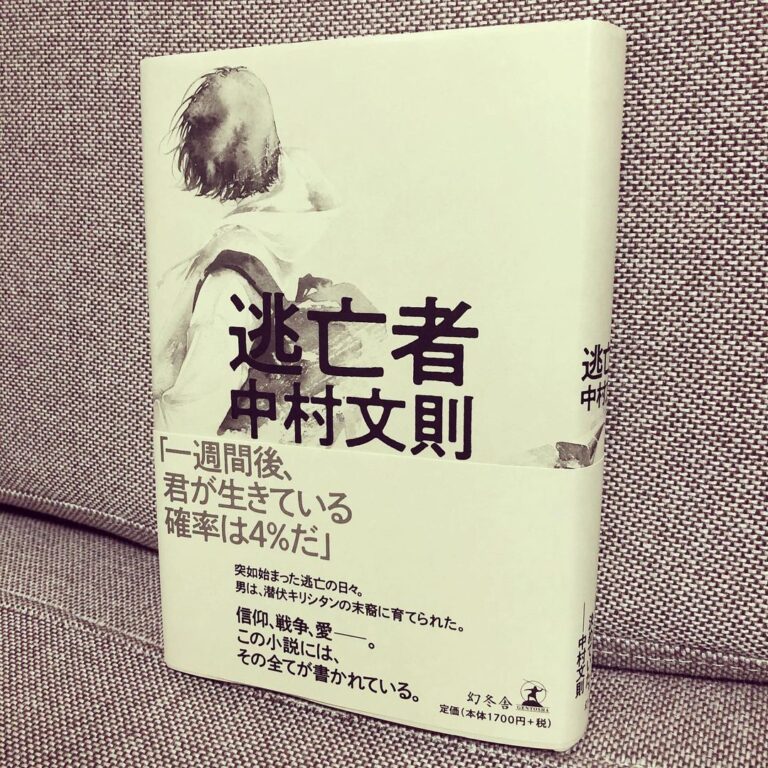
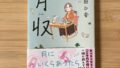
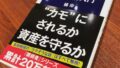
コメント