こんにちは!しょーてぃーです!
今回は、菅原道仁さんの
『すぐやる脳』について紹介をしていきます!
『すぐやる脳』について
本書の概要
本書はひとことで言うと
行動力を引き出すための脳科学アプローチが学べる1冊です。
本書をオススメしたい人
- 先延ばし癖がある人
- なかなか動けない人
- 新しいことを始めるのに不安がある人
本書は、脳神経外科医である菅原道仁氏による
行動力アップのための脳科学的アプローチを紹介する1冊です。
多くの人が「やりたい」と思っていてもつい先延ばしにしてしまうのは、
脳が本能的にエネルギーを節約しようとする特性に原因があると指摘し、
「怠け者」の脳に打ち勝ち、すぐやる人になるための具体策として、
ドーパミンの活用法を解説しています。
仕事や勉強、家事など「始めるまでに時間がかかる」のは人間として自然な反応ですが、
行動を起こしてしまえば脳内でドーパミンが分泌されてやる気が高まり、
どんどん物事が進むというメカニズムをわかりやすく説いているのが本書の特徴です。
現役の脳神経外科医による科学的エビデンスに基づく説明は信頼性が高く、
日常生活にすぐ役立つ実践的なアドバイスも満載で、最後まで読みやすい内容となっています。
『すぐやる脳』のまとめ
脳は本質的に怠け者である
本書は、「物事を先延ばしにしてしまう」「続けられない」「決められない」といった行動上の悩みを、
脳科学や心理学の知見からひも解き、解決策を提示してくれる内容です。
序章「脳がそれを拒否する理由」ではまず、人間の脳は本質的に怠け者であり、
エネルギー消費を抑えるようプログラミングされているという前提が示されています。
脳は体重の約2%しかない臓器なのに全身のエネルギーの20%も使うため、
できるだけ休もうとするのは当然とも言えます。
そのため「やらない・動かない・考えない」ことで体力を温存しようとする傾向が
誰にでも備わっており、「面倒だから動けない」「失敗が怖いから手を付けられない」という状態は、
決して意志が弱いせいではなく脳の生存本能に根ざした自然な反応です。
この視点は、つい自分を責めがちな人にとって
「やる気が出ないのは自分の性格のせいじゃなかった」と気づかせてくれます。
ドーパミンがやる気をつくる
ではどうすれば「すぐやる」人になれるのか。
菅原氏はその鍵こそがドーパミンという脳内物質にあると述べます。
例えば誰もが経験するように、始めるまでは腰が重かった作業も、
いったん取りかかるとエンジンがかかったように一気に進むことがありますが、
これこそがドーパミンの作用だといいます。
ポイントは、ドーパミンは「行動を始めてから」分泌され、
分泌されるほど更にやる気が湧いてくるという点です。
この現象を心理学的に「作業興奮」と呼び、
やる気は後からついてくるものだと本書は強調します。
したがって脳のやる気スイッチを押す唯一の方法は、
とにかく手を動かしてみることなのです。
著者いわく「脳のやる気スイッチ=側坐核」であり、
体を動かす刺激がそのスイッチを入れる最善策だと説明されています。
つまり頭で考えるより先に動くことが、
「やりたくない脳」を「やりたがる脳」に変える近道というわけです。
「まずやる」ための小さな工夫
本書第1章「ドーパミンこそが行動を決める!」では、
このドーパミン分泌によるモチベーション加速のメカニズムが詳しく解説されています。
続く第2章「すぐやる」では、とにかく考える前に一歩踏み出すための
具体的なステップが紹介されています。
たとえば「5分でいいから始めてみる」ことや、
完璧を求めず50点の出来でも構わないからまずやってみることなど、
すぐ行動に移すための現実的なコツが述べられています。
やる気がないからできない、と感じるときでも
「5分だけやってみよう」と自分に言い聞かせて手を付ければ意外と続けられるし、
最初から完璧を目指そうとすると永遠に始められないので
「見切り発車で構わない」というマインドが大切だと説くのです。
著者自身も「まずは50点でもいいからアウトプットして、
走り出してから改善すればいい」と述べ、
実際に本書の執筆スタイルも早めに書き始めることを実践したそうです。
これは心理的ハードルを下げて行動を開始する工夫であり、
先延ばしグセに対して非常に有効なアプローチです。
先送りを防ぐ「こまめ・早め」の習慣
第3章「こまめにやる、早めにやる」では、
日々の行動を先送りせず小まめに片付けていく習慣の大切さが語られます。
例えば仕事でもプライベートでも、面倒な用事ほど
後回しにせず早めに手を付けることで脳への負担を軽減できるといいます。
脳にとって「やらなければいけないタスクを覚えておくこと自体」が負荷となり、
ずっと気に抱えていると精神的エネルギーを消耗してしまうからです。
逆に言えば、思い立った時にすぐ片付けてしまえば
それ以上ストレスを感じずに済むので、結果的に省エネにも繋がります。
本章では時間を有効活用する工夫や、
すぐ取り掛かることで生産性を高める具体例が紹介されており、
「締切効果」を上手く利用して集中力を高めるテクニックなども触れられています。
要は、締切間近に急に集中力が増すのは脳の「接近勾配の法則」によるもので、
それを逆手に取り普段から自分で締切や目標を小刻みに設定して行動すると、
無駄なく物事を進められるということです。
小さなタスクでも先延ばしせず早めに処理する習慣がつけば、
常に頭がスッキリとしてパフォーマンスも向上します。
長続きの秘訣は「小さな成功体験」
第4章「続ける」では、始めたことを長続きさせるための工夫がテーマです。
三日坊主で終わらず習慣化するにはどうすればいいか、
脳科学と心理学の観点から具体策が示されています。
本章で紹介されるキーワードの一つが「馴化(じゅんか)」です。
これは心理学用語で「慣れ」の現象を指し、
人が最初は熱中していた物事に次第に慣れて刺激を感じなくなり、
飽きてしまうプロセスを意味します。
著者は、誰もが感じる「飽きっぽさ」「長続きしない」という現象に
きちんと名前がついている事実を知るだけでも、
客観的に自分の状態を把握できて対策の一歩になると述べています。
その上で、飽きて投げ出さないためには
小さな成功体験を積み重ねることが重要だと強調されます。
行動して何かを達成したり誰かに褒められたりすると、
「やればできる」という達成感や成長実感がドーパミンを生み出し、
さらに行動したくなる好循環が生まれます。
例えばSNSの「いいね!」やゲームのレベルアップといった身近な成功体験があると、
人はもっと頑張ろうという気持ちになります。
この原理を自分の習慣化にも応用し、
タスクをゲーム化して取り組むことで飽きずに続けられるよう自分をデザインできるといいます。
具体的には、達成状況を見える化してスコアを競ったり、自分にご褒美ルールを設けたり、
あるいは定期的に発表会を設定して緊張感を持つことなどが有効です。
実際、本書では「続けたければ発表会を設けよ」というアドバイスも紹介されており、
成果を誰かに見てもらう機会があると人は、途中で投げ出しにくくなると述べられています。
こうした工夫によって小さな達成→ドーパミン分泌→更なるやる気という
循環を回し続けることこそが、「すぐやる脳」を育てる秘訣だとまとめられています。
意思決定と感情コントロールへの応用
さらに本書では終盤、先延ばし克服のための脳科学的アプローチを
「決断」や「挑戦」「怒り」といったテーマにも応用しています。
優柔不断で物事を決められない人には、脳の働きを利用して
意思決定のストレスを減らすコツを提示します。
例えば、「あれもこれもやらなきゃ」と抱え込むのではなく
「何かをやらない」と決めて脳の容量に空きを作ることも大切だと説かれています。
また新しい挑戦への恐怖心については、
「脳は変化や未知の刺激を本能的に避けようとする」性質を理解しつつも、
それを乗り越えることで得られる成長や喜びを強調しています。
著者は「人間の脳には可塑性があり、適切に刺激すれば構造も変えられる」と述べ、
新たな挑戦に取り組んで深く考え行動することで前頭前野が鍛えられ、
恐れの感情を司る扁桃体の反応も弱まるという研究結果も紹介しています。
最後の第7章「怒らない」では、怒りの感情に振り回されないための
脳科学的アプローチが語られます。
怒りは一瞬で爆発する強力な感情ですが、
脳の衝動をコントロールする訓練によって誰でも穏やかに対処できるようになるといいます。
カッとなったとき6秒待つといったテクニックや、
深呼吸・リフレーミング(見方を変える)など古典的な対処法も、
実は脳内の扁桃体の暴走を抑える科学的根拠に裏打ちされていることが説明されており、
感情面でも「すぐカッとなって後悔しない脳」を作るヒントが得られます。
以上のように本書は、先延ばし癖の克服から習慣化、
意思決定、新しい挑戦、感情コントロールに至るまで、
脳のメカニズムを活用した幅広いテーマの実践的アドバイスを網羅しています。
最後に
ここまで本書について紹介してきました。
本書は、論理的かつ平易な語り口で
「やらない自分」を変える具体的な方法を示してくれる1冊でした。
本書が気になる方は、是非手に取ってみてください!
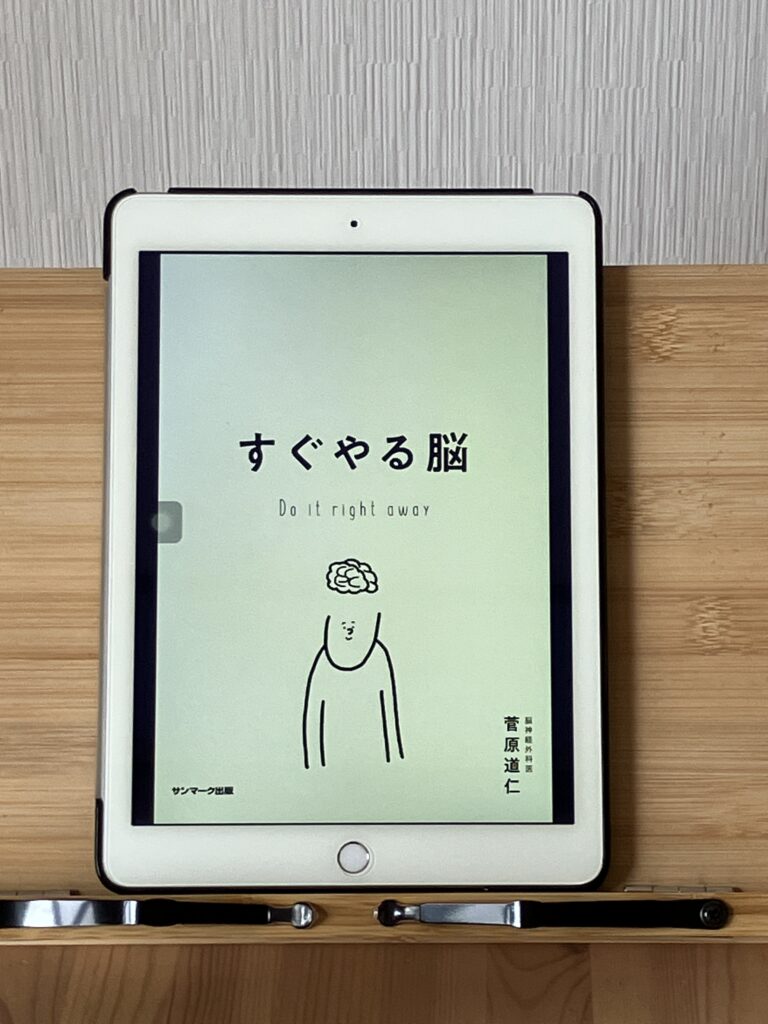
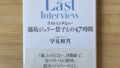

コメント