こんにちは!しょーてぃーです!
今回は、ちきりんさんの
『自分のアタマで考えよう』について紹介をしていきます!
『自分のアタマで考えよう』について
本書の概要
本書はひとことで言うと
他人の意見に流されずに、自分で決める力を育てる1冊です。
本書をオススメしたい人
・情報に振り回されがちな人
・仕事の意思決定に自信が持てないビジネスパーソン
・自分の価値観で行動したい人
本書は、社会派ブロガーであるちきりんさんが、
知識に惑わされず自らの頭で「考える力」を養うための方法を
わかりやすく説いた実用書です。
情報があふれる現代において、多くの人は「知識を得る」ことばかりに注力し、
「自分で考える」ことを忘れがちです。
本書では、他人の意見に流されず、自分なりの判断軸を持って考えることの大切さを、
身近な例とともに紹介しています。
また、思考と感情を切り離すコツ、疑う習慣を持つ重要性、
前提を外して発想する技術、意思決定のプロセスを設計することなど、
仕事や日常生活にすぐ役立つ具体的なアプローチが多数掲載されています。
「知識」よりも「思考」の大切さを説き、読者に行動を促す1冊です。
『自分のアタマで考えよう』のまとめ
はじめに
情報があふれる現代、他人の意見や既存の知識に流されずに
「自分の頭で考える」ことは、仕事でも人生でも重要なスキルです。
社会派ブロガー・ちきりんさんの著書『自分のアタマで考えよう』は、
知識に惑わされない思考の技術について具体的な方法を教えてくれる1冊です。
本記事では、日々の仕事や意思決定に
役立つ考え方のコツをテーマ別に整理しました。
自分の判断軸を持ち、感情に左右されず、
柔軟かつ論理的に物事を考えるヒントをつかんでいただければ幸いです。
自分軸で考える: 他人の意見に左右されない
周囲の意見や一般論に引っ張られず、
自分なりの視点・価値観に基づいて考えることが「自分軸で考える」ことです。
他人が出した「それっぽい結論」に飛びつくのではなく、
自分独自のフィルター(判断基準)を明確に持つことで、情報に振り回されにくくなります。
たとえば仕事の意思決定で「何を最優先するか」という
自分の価値観がはっきりしていれば、
「みんながこう言うから…」と流されることなく、自信を持って結論を出せます。
自分軸を持つためには日頃から
「自分は何を大切にしたいのか」「何を基準に判断すべきか」を意識しておくことが大切です。
将来のキャリア目標を思い描き、
そこから逆算して「自分にとって譲れない条件」をリストアップしてみることと
日々の小さな選択でも、自分の軸となる原則を、意識する習慣をつけていくことが重要です。
情報を鵜呑みにしない「疑う習慣」
インターネットや書籍から日々大量の知識が入ってきますが、
それらをそのまま鵜呑みにしていては「自分で考える」ことは始まりません。
他人の考えやデータに触れたとき、
一度「本当にそうだろうか?」と疑ってみる習慣を持つことが大切です。
たとえば「この業界は先細りだ」という情報を聞いたら、
「それはどんなデータに基づいているのか?他に別の見方はないか?」と
立ち止まってみるのが良いでしょう。
知識と思考を一旦切り離して考えることで、
固定観念に縛られない発想や新しいアイデアが生まれやすくなります。
また、与えられた数字や事実に対しても
「なぜそうなっているのか?」「だから何が言えるのか?」と問いかけることで、
表面的な情報の裏側にある原因や意味を深掘りすることができます。
一見矛盾しているデータや腑に落ちない統計に出会ったときには、
出典を調べたり関連情報を当たったりして、徹底的に検証する姿勢も大切です。
根拠を深く追究することで、安易な誤解を防ぎ、
より確かな結論に近づくことができます。
思考と感情を切り離す
冷静な思考には、自分の感情や思い込みをいったん脇に置くことも重要です。
仕事で議論がヒートアップしたときや、
重大な選択に迫られプレッシャーを感じるときこそ、
感情と論点を分けて考えるようにしましょう。
たとえば提案が否定されて悔しいと感じたら、
その感情自体は認めつつ、「提案の内容に論理的な改善点はあるか?」と考え直すことが役立ちます。
感情に流されず事実関係と論理に目を向けることで、
より客観的で妥当な判断がしやすくなります。
どうしても感情に押されそうなときは、一度時間をおいて頭を冷やしたり、
考えを書き出して自分の状況を客観視したりすると良いです。
自身の感覚や直感も大事ですが、
それによるバイアスが入りすぎていないか自問する姿勢が、
バランスの取れた思考には欠かせません。
前提にとらわれず発想する
問題解決や企画の場面では、暗黙の前提や既成概念を疑い、
あえて外して考えてみることで革新的なアイデアが生まれます。
最初から「これは無理」「普通はこうするものだ」と決めつけずに、
あらゆる可能性を探る発想法を意識することが大切です。
ちきりんさんも、議論の際に一つの方向に思考が走りがちなときは
「他の選択肢はないか?」と視点をずらして考えることを提案しています。
たとえば新商品のターゲット戦略を考えるなら、
「国内ではダメでも海外市場なら?オンラインではなくリアル店舗なら?」と
条件を変えてみることで、新しい視点が生まれます。
前提条件を疑うことで発想の幅が広がり、
今まで見えていなかった解決策やチャンスを見出すことができます。
意思決定のプロセスを設計する
情報収集や分析に入る前に、
「どうやって結論を出すか」という意思決定のプロセス自体を
先に考えておくことも効果的です。
闇雲にデータを集め始める前に、
「この案件では何をもって成功条件とするか」
「どの基準を満たしたら実行に移すか」をチームで合意しておくと良いです。
先に結論の条件を仮定してから検証するこのアプローチは、
ビジネスでよく言われる仮説思考にも通じます。
プロセス(判断基準と手順)を決めてから情報を集めれば、
「なんとなく関係がありそうだし、役立ちそうに思える情報」を
際限なく集め続けて結論が出ない、といった事態を防げます。
思考を見える化し、知識を整理する
頭の中だけで考えていると論点が散逸したり抜け漏れが生じたりしがちです。
そこで有効なのが思考の見える化です。
自分の考えを書き出したり図解したりすることで、
考えの甘さに気づき思考をより深めることができます。
選択肢を比較検討するときに表を作って縦軸・横軸に項目を並べれば、
どの案がどの基準で優れているか一目でわかります。
グラフやチャートを使ってデータを視覚化すれば、
数値の傾向や因果関係を直感的に把握できるようになります。
さらに、得た知識は単に覚えるだけでなく
「思考の棚」に整理して入れるイメージを持つことが効果的です。
関連する知識同士をカテゴリー分けして頭の中にストックしておけば、
必要なときに取り出して組み合わせ、新たな洞察を得やすくなります。
このように視覚化と整理を習慣づけることで、
思考の抜け漏れを防ぎ、生産性を高めることができます。
最後に
ここまで本書について紹介してきました。
自分の頭で考える力は、一朝一夕で身につくものではありません。
しかし、本書で紹介されたような技術を日々意識して訓練することで、
少しずつ思考の質は高まっていきます。
自分で考える力がつけば、情報に振り回されずに
自分の軸で意思決定できるようになり、
変化の激しい時代にも柔軟に対応できるようになります。
本書が気になる方は、是非手に取ってみてください!
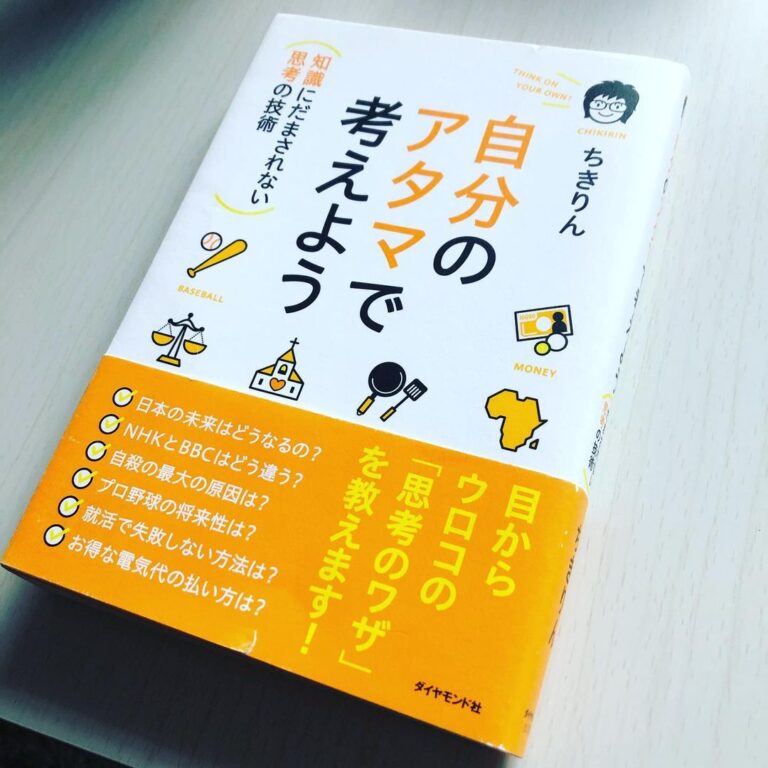

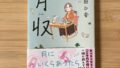
コメント