こんにちは!しょーてぃーです!
今回は、徳谷 智史さんの
『キャリアづくりの教科書』について紹介をしていきます!
『キャリアづくりの教科書』について
本書の概要
本書はひとことで言うと
キャリアに迷わないための指南書のような1冊です。
本書をオススメしたい人
- キャリアに漠然と不安を感じている人
- 転職や副業など、新たな挑戦を考えている人
- 部下や後輩のキャリア形成を支援する立場の人
本書は、転職・異動・起業から産休育休・就活まで、
あらゆるキャリアの転機で「何度も使える」決定版の1冊です。
著者の徳谷智史氏は2万人以上のキャリア支援と
1000社近い組織変革の実績を持つキャリア開発のプロです。
本書では、そんな著者が自身の経験と知見を凝縮し、
現代の「キャリア流動化時代」に必要な考え方と実践ノウハウを網羅的に解説しています。
内容はこれからのキャリアを旅にたとえ、
ゴールの設定、自分の強みやスキルという武器の準備、キャリア選択というルート決定、
そして転職後の活躍や他者支援までを段階的に指南する構成です。
全552ページにわたるまさに「キャリアの地図」とも言える1冊で、
一人ひとりのかけがえのない人生に寄り添ってくれます。
『キャリアづくりの教科書』のまとめ
キャリアは「旅」:キャリア3.0時代の到来
本書の第1章では、現代が「キャリア3.0」と呼ばれる
新しい時代であることが示されています。
もはや一つの会社に定年まで勤め上げる時代ではなく、
キャリアは「川下り」や「山登り」のような一本道ではなく
終わりなき旅のようなものだといいます。
著者はキャリアという旅路における4つの重要な構成要素を提示しています。
1.目的地(ゴール)
「どこに行きたいのか」「どんな状態で働きたいのか」といった自分自身のありたい姿です。
他人任せではなく、自分で決めるべきゴールであり、最初は漠然としていても構いません。
2.武器(スキル・強み)
旅を充実させるために必要な力や道具に当たります。
キャリアづくりの文脈では自分の価値を高めるための準備、
すなわちスキルや経験・強みの習得がこの「武器」に相当します。
3.ルート(選択肢)
ゴールに到達するための道筋です。
転職、独立・起業、社内で新たなチャンスをつかむなど、
目的地に向かう意思決定の数々がルートとして考えられます。
決して一つではなく、複数のルートがあり得ます。
4.終わりなきプロセス
旅には明確な終着点がなく、キャリアも一度の決断で終わらないということです。
旅の途中で新たな出会いや予想外の出来事にどう対処し、
それをどう楽しむかが大事であり、目的地に着いた後も次の旅が続いていくように、
キャリア形成も生涯にわたって続いていくプロセスです。
こうした「キャリアジャーニー」の時代には、会社も個人も変化への適応が不可欠です。
企業側は同じビジネスモデルで長く生き残ることは難しく、
人材に求められるスキルも変化します。
個人の側でも生涯一社・一職種の前提は崩れ、
複数の組織や職種を経験したり転職・副業することが一般化しています。
その中で将来の明暗を分けるのは、「看板(所属組織)」に安住せず
自らの意志で機会をつかみ続けてきたかどうかだと著者は強調します。
経験を通じた成長の差は次第に学歴や地頭の差よりも大きくなっていくため、
違和感に蓋をして現状に留まる人に明るい未来は望めないのです。
むしろ、短期的に収入が減るような選択や困難な経験にもあえて飛び込み、
中長期的な成長機会に投資して自分の価値を積み上げることが重要だと説かれています。
一時の損失をいとわず挑戦し、信頼や成長という「自己資本」を蓄積していくことで、
それをテコに将来的な経済的リターンも享受できるといった
長期視点のキャリア戦略が示されています。
自分を知る:固定観念の鎖を外し「自己言語化」する
第2章では、まず自分のキャリアを主体的に描くために
「自分自身を言語化する」プロセスが解説されています。
人は他者との比較の中で生きているため、自分の歩んできた道を無意識に正当化したり、
「これまでのキャリアには意味があったのだ」と思いたがる
自己正当化バイアスにとらわれがちです。
しかしそのバイアスが強すぎると、本当の気持ちを見失い、
心から望む未来を描けなくなると著者は指摘します。
まずは「自分には無理だ」「こうあるべきだ」といった
思い込みの固定観念の鎖を見つけ出し、
その外へ思考の範囲を広げることが重要だと説かれます。
過去の経験自体に善悪はなく、それにどんな意味付けをするかが人生を左右します。
経験を振り返ってそこから学ぶべきことは学び、
時には過去へのこだわりを手放すことも大切です。
また、自分のキャリアを考えるうえで
「利己」と「利他」のバランスにも触れられています。
まずは自分の「やりたいこと」「得たいもの」を満たさなければ
真の利他(他者貢献)は生まれない。
つまり自己実現を果たした先に、初めて誰かのために動ける人もいるというわけです。
「社会の役に立ちたい(利他)」と「自分の目標を達成したい(利己)」は
二項対立ではなく、両立しうるものだと本書では述べられています。
将来像を描くときは、まず「思考の壁」を取り払うことから始めます。
人は経験を積むほど現実を基点に未来を考えがちですが、
それでは理想を描けなくなることがあります。
そこで「もし何の制約もなかったら?」と自問し、一旦できない理由は脇に置いて、
自由に将来のやりたいことを考えてみることが勧められます。
最初から完璧な夢をひねり出す必要はなく、
著者はMust-Canアプローチという考え方も紹介しています。
与えられた目の前の仕事=Must(やるべきこと)に全力で取り組み成果を出すうちに、
自分にできること=Canが増えていき、
次に目指したいことが見えてくるという経験則です。
実際、どんな成功者でも最初から明確なビジョンがあったわけではなく、
仮の方向性を決めて走りながら経験を積み、
成長に伴ってビジョンを具体化・更新していくケースが多いと述べられています。
つまり行動しながら自分の「ありたい姿」を磨いていくことが大事だということです。
著者は自分を言語化するための3つのステップも提示しています。
- 自分の凝り固まった価値観を紐解く。 知らず知らず固定化している「〜すべき」「〜してはならない」といった前提や思い込みに気づく。
- 過去の経験を振り返り、思考や行動のクセ・軸を言語化する。 自分は何に喜びを感じ、何にストレスを感じるのか。経験の棚卸しから自分の傾向や強み・弱みを客観視する。
- 思考と行動の壁を取り払い、描きたい未来を仮置きして行動に移す。 制約を外して理想像を設定し、小さくてもいいので一歩踏み出してみる。行動からさらに学び、理想像をアップデートしていく。
市場価値を高める:希少性・市場性・再現性
第3章では、「市場価値」とは何かが定義され、自分の価値を高める視点が解説されています。
一般に市場価値は「希少性×市場性×再現性」の3要素で説明できるとされ、
本書でもこの3つの観点から自身の強みを見直すよう促しています。
希少性
他者にはない希少な価値かどうか。
具体的には持っているスキルや知識、そしてスタンス(姿勢・人柄)も含めて、
その人ならではの強みがどれだけレアかという指標です。
スキルは努力次第で後天的に身につけられる場合も多いですが、
スタンスは性格や信念にも関わるため習得に時間がかかります。
だからこそ将来大きな成長を生むスタンスの部分で高いレベルにある人は、
それ自体が希少価値になるといいます。
著者は「発注者の罠」という注意点も挙げています。
お金を出すクライアント側(発注側)の立場に長く身を置いていると、
自分では手を動かさず周囲が忖度してくれる環境に慣れてしまいがちで、
いざ自分が提供側(プレイヤー)に回ったときに
価値を発揮できなくなる恐れがあるというのです。
希少な人材であり続けるためには、
自ら手を動かし、フィードバックを受けて成長する立場を経験し続けることが大切だと読み取れます。
市場性
時代や市場のニーズに合った価値かどうか。
求められる分野であること、時流に乗っていることといった側面です。
本書では「課題解決力より課題設定力が重要になる」という示唆があり、
変化の大きいこれからの時代には、既存の延長線上の改善ではなく
ゼロから課題を見つけ出し解決策を創造する力が求められると述べています。
現状に満足せず健全な危機感を持って、
小さくてもいいから新しい挑戦を起こし続ける人こそが市場で評価される、という視点です。
つまり、自分の属する業界や職種で
これから重要となるスキル・経験は何かを見極め、
先んじて身につけることで市場性を高められるということです。
再現性
環境が変わっても同じ価値を発揮できるか。
言い換えれば「ポータブルスキル・ポータブルスタンス」を持っているかです。
つまり、どんな組織でも成果を出せる人は再現性が高い人材と言えます。
ここで著者が強調するのは、
「環境さえ変えれば誰かが自分を成長させてくれる」ということは
ありえないというシビアな真実です。
環境のせいにせず、どんな職場でも成果にこだわり抜く姿勢を持つ人こそが、
異なる環境でも成功できる人だといいます。
常に目標と現状との差を意識し、
埋めるために必要なスタンスやスキルを見極めて磨き続けることで、
どこでも通用する力が身につくのです。
また、自分一人で考え込まず、
他者との対話を通じて自分の特性を再発見することも勧められています。
自分では当たり前と思う強みが
他人から見れば突出している場合もあるので、
他者のフィードバックを活用して客観的に自己分析することが有効というわけです。
さらにテクニカルスキル(専門技能)に関しては、
「資格=スキル」ではないとも述べています。
資格は誰でも比較的短期間で取得できますが、
本当の専門スキルを高めるには地道な時間投資が必要であり、
だからこそ他人との差別化につながるといいます。
一つでいいので腰を据えて磨いた確固たる専門スキルを持つことが、
他との差を生む武器になるというアドバイスです。
著者はこの希少性・市場性・再現性の3要素を高めるために、
継続的な成長と環境の選択が重要だと説きます。
同じ環境に長く留まれば、誰しも成長は頭打ちになる時期が来るものです。
そこで大事なのが、自ら意図的に新しい環境に飛び込んで
非連続な経験をする「クリエイティブジャンプ」だといいます。
線形の延長ではなく、思い切って未知の分野に挑戦したり
今までと違う役割を担うことで、自分を一段成長させる飛躍の機会になります。
著者は「自ら非連続な機会を創り出し、非連続な機会によって自らを変えよ」と強く提言しており、
現状に安住せず自分で成長の舞台を作り出す姿勢を促しています。
キャリアの選択(前提編):T型からH型へ、可能性を制限しない
第4章「キャリアを選択する(前提編)」では、
キャリアチェンジに臨む前提となる考え方が語られます。
キーワードの一つは「T型からH型へ」です。
T字型人材(一本の専門スキルに深さを持ちつつ幅広い知見も備えた人)という言葉がありますが、
著者は自分の専門の成長が停滞したと感じたら、
思い切って別の軸を深めてH字型人材になることも検討せよと提案します。
一見遠回りに見えても、新たな分野に挑戦して別視点を身につけることで、
もともとの専門分野にもさらに深みが出るケースが多いというのです。
実際にH型に移行してから元の専門領域に戻ることで、
大きく飛躍した例も少なくないようです。
重要なのは、「自分の可能性を事前に狭めすぎないこと」。
人はやってみて初めて自分の本当の強みや適性に気づく場合が多いため、
最初から「自分にはこの道しかない」と決めつけてしまわないほうが良いとされています。
幅広くアンテナを張りながら、様々な分野に興味を持って経験してみて、
その中で相対的に自分の能力が発揮できるフィールドを見極めてから
もう一つの専門軸を深めていくというアプローチが勧められています。
また、キャリア後半の戦略にも触れられています。
40代以降になったら、残りの職業人生をどんな環境で過ごしたいかを改めて見定め、
それを具体的な言葉にすることが大事だといいます。
それまでに培った立場やスキルを「何のために活かすのか」を明確にし、
肩書きや年収といった内向きの視点だけでなく
社会や他者にどう貢献したいかという外向きの視点で
キャリアの軸を定め直すことを勧めています。
さらに人生は長いので、人それぞれペースが違って当然です。
全てをコントロールすることはできませんし、
焦って走り続ける必要もなければ、
シニアだからと新しい挑戦を諦める必要もないと述べられています。
休憩や遠回りだってあって良い、それも旅の一部だというのが
「キャリアジャーニー」という言葉に込められた思いなのです。
キャリアの選択(実践編):人生は選択の連続
第5章「キャリアを選択する(実践編)」では、
具体的にキャリアの意思決定をどう行うかについてのアドバイスが提示されています。
まず強調されるのは「人生は選択の積み重ね」という当たり前ですが重要な視点です。
どの会社で誰とどんな仕事をするか
実は「今の会社に居続ける」ということ自体も一つの選択であり、
我々は常に無数の選択肢の中から何かを選び続けているのだと指摘されています。
選択とは本来、文字通り他の選択肢を「断つ」ことです。
一つを選ぶということは、他の道を選ばないことでもある。
だからこそ、キャリアにおいては今この瞬間も
環境を選択し続けているという自覚を持つ必要があります。
この意識を持つと、惰性で現状に留まるのではなく
「自分で今ここを選んでいるのだ」と主体的に捉え直せるでしょう。
その上で、転職活動の本質についても語られます。
転職活動とは「内定をもらうことがゴールではない」と著者は断言します。
自分の目で会社を見て、話を聞き、考えた上で
「本当にその環境に身を置くべきか」を判断するプロセスこそが転職活動の意義だというのです。
面接で評価してもらう場というより、
自分に合った環境かを見極める場だという逆転の発想です。
そして実際に転職先を決める際には、
「選んだ道を正解にする」というマインドセットが提示されています。
転職はあくまで新しい環境への入口に過ぎず、
本当に大事なのは入社後にいかに成長・成果を出すかです。
どの会社が正解でどの会社が間違い、という絶対的な答えは存在しません。
人生にA/Bテストはできない以上、悩みに悩んで決めた道であれば、
後から「あの選択は正しかったか」と振り返るより、
選んだ環境で日々ベストを尽くして次のキャリアを切り拓くしか道はないと説いています。
さらに副業についても言及されています。
副業では多くの場合「時間よりも成果」が求められるので、
費やした時間ではなくアウトプットの価値にフォーカスすべきだといいます。
自分の提供したアウトプットがどれだけ価値を生み、
報酬に繋がるかを肌で感じることで、市場の感覚が養われます。
だからこそ、いかに短い時間で成果を出すか工夫し、
「時給思考」から抜け出そうというメッセージが記されています。
また、「今の会社に残る」という選択をプラスに転じるためには、
「他に行けないから残る」という消極的な理由ではなく、
「この会社で成し遂げたいことがある」という
主体的な意思で残ることが重要だとも述べられています。
同じ残留でも受け身と主体的では
その後のキャリアの明暗が大きく分かれるという指摘は示唆に富みます。
そして最後に、キャリアの選択においては
うまくいったかいかなかったか以上に
「なぜその結果になったのか」を分析し学ぶことの大切さも強調されています。
成功時も失敗時も要因を深掘りし次に活かすことで、経験が糧になるのです。
転職後の成功と失敗を分けるもの:最初の3日・30日・3ヶ月
第6章では、新しい環境でどう活躍できるかについて
具体的なアドバイスが語られています。
中途入社者の30%以上が2年以内に離職するという統計もあり、
特に「入社後半年~1年以内」で辞めてしまうケースがもっとも多いそうです。
そこで著者は、新天地で成果を出し長く活躍するために
「3日・30日・3ヶ月」が勝負だと言います。
最初の3日
第一印象づくりの期間です。
初日から3日間で「この人は良さそうだ」という印象を周囲に与えられれば、
その後の人間関係や情報収集が格段にスムーズになります。
逆に第一印象が悪いと様子見モードで警戒され、
支援も得られにくくなってしまうので要注意です。
挨拶や基本的な振る舞いはもちろん、
笑顔や謙虚さといった人となりで信頼感を与えることが肝心でしょう。
最初の30日
積極的に質問・対話する期間です。
年齢や立場に関係なく、入社直後の1ヶ月は
何を質問しても許される雰囲気があるものです。
社内の制度や文化が「なぜ・どのように生まれたか」といった
内部の事情は入ってみないと分からないので、
この30日間で徹底的に問いを立てて吸収する姿勢が推奨されています。
また、この間に部署や上下関係を越えて気軽に相談できる相手を
一人でも作っておくと良いと著者は述べます。
直属の上司でも同僚でもない「斜めの関係のメンター」、
いわゆる「ナナメンター」を意識的に見つけると、客観的に話を聞いてくれる存在ができるので
心理的な安心感につながるそうです。
最初から意識しておくことで良い相手を探しやすく、
「自分を客観視できる相談相手が身近にいる」というだけで
精神的負担が大きく軽減されるといいます。
最初の30日で小さな成功体験を積み信頼を得られれば、
その後は情報も集まりやすく、人脈も広げやすくなるため、
まず1ヶ月で信頼基盤を築くことが何より大事です。
最初の3ヶ月
結果を出すことに集中する期間です。
新しい職場に入ると、以前との違いから
様々な「改善ポイント」や課題が目につくものですが、入社後3ヶ月くらいまでは
まず自分の役割で成果を出すことにフォーカスすべきだとされています。
実績も出していないうちから「ここはこうした方がいい」などと提案しても、
周囲は聞く耳を持ってくれませんし、下手をすると「新参者のくせに生意気だ」
「前の組織を引き合いに現状批判している」と受け取られかねません。
焦って短期間で成果を出そうと空回りすると独りよがりのプレーに陥りがちですが、
著者は「むしろ周囲を巻き込んで知見を借りた方が断然うまくいく」と強調します。
周りの人の方がその組織での経験が長く知識も深いのは当たり前なので、
人間関係とカルチャー理解ができていれば協力を仰ぎやすいはずだというわけです。
つまり、3ヶ月までは組織に馴染み信頼を得つつ自分の責務を全うし、
結果を出すことに注力するのが得策ということになります。
以上の「3・30・3」ステップを経ることで、新しい環境でも土台を築けると本書は説きます。
もちろん、どんな組織にも課題は山ほどありますが、
新しく入った人に求められるのはそれらを指摘して嘆くことではなく、
まずは「なぜ解決できずにいるのか」という背景まで理解した上で、
解決策を模索する姿勢だとも述べられています。
表面的に問題点を挙げ連ねるだけでは何の意味もなく、
周囲も既にわかっていて苦労していることが多いのです。
過去の自分の成功体験すべてを否定する必要はありませんが、
一度立ち止まって「この新しい環境でも通用するやり方」と
「ここでは通じないやり方」を仕分けすることが重要だという指摘も心に留めたいポイントです。
そして何より、新しい組織の方針や考え方、
現在起きている事象に耳を傾ける謙虚さと敬意を持つことが、
信頼を築き成果を出す上で不可欠だと強調されています。
他者のキャリアづくりを支援する:対話で「Will」を引き出す
第7章では、部下や後輩など他者のキャリア形成を支援する方法について述べられています。
まず大前提として、人それぞれキャリアや人生に求めるものは違うという
当たり前の事実を肝に銘じる必要があります。
頭では理解しているつもりでも、
無意識のうちに「自分の当たり前」を相手にも当てはめてしまい、知らず知らず
自分の経験談に基づくアドバイスを押し付けてしまうことがあると著者は指摘します。
それは支援のつもりでも、相手の価値観からずれた押し付けになっていないか、
自分の中の自己正当化バイアスに注意しようという呼びかけです。
マネージャーへの問いかけとして、本書では次のような点が挙げられています。
- 会社の目指す姿や事業の意義を、メンバーが納得できるレベルで説明できているか?
- 各メンバーのキャリア志向を理解し、その上で組織の方向性とメンバーのキャリアを結びつけ、機会を提供できているか?
すべての業務が個人のやりたいことや成長目標に直結するとは限りません。
しかし、個人の「ありたい姿」や成長につながる部分と
組織の目標とを少しでも結びつけて機会を与えようとする姿勢が、
メンバーからの信頼に繋がると述べられています。
要は、「あなたの成長やキャリアをちゃんと考えているよ」というメッセージを
行動で示すことが、支援する側の役割だということです。
次に、メンバーの「Will(ありたい姿)」を引き出す対話について詳細に語られています。
実は若手に限らず転職活動中のプロですら、
最初から自分がどうありたいか明確に言語化できている人はほとんどいないのだといいます。
多かれ少なかれ、ほぼ全ての人が対話を通じて徐々に考えを整理し、
言語化していくものだというのです。
だから大切なのは「そもそもWill(やりたいこと)があるかないか」ではなく、
「Willをいかに具体化していくか」というプロセスに寄り添うことだと著者は強調します。
具体的な対話のステップとして、本書ではまず「過去の仕事で楽しかったことは何?」と質問し、
続けて「なぜそれが楽しかったと思う?」と尋ねる方法が紹介されています。
いきなり「将来何がしたい?」と問うのはハードルが高いので、
「出来事」と「それに感じた理由」を2段階に分けて質問する方が答えやすいというわけです。
同様に、可能であれば「挫折経験」や「コンプレックスに感じていること」についても、
「どんな出来事だったか」「なぜそれをそう感じたのか」に分けて聞いてみると良いとされています。
これら過去の体験の棚卸しを対話で行うことで、その人が大事にしている価値観や軸が見えてきて、
今後伸ばしたい方向性が浮かび上がりやすくなるのです。
とはいえ、プライベートな悩みや制約を抱えている場合、
いくらWillを具体化しようとしても考えが及ばないこともあります。
その場合は無理に将来ビジョンを詰めようとせず、
まずは状況を理解して「待つ姿勢」も大事だと著者は言います。
上司が自分の状況をわかってくれている、というだけでも大きな支えになることがあり、
「わからないことがあるのだと理解しておく」ことで
意図せず部下を追い詰めることを避けられるかもしれません。
次に能力開発の支援についてですが、上司がキャリア面談などで
「あなたの強み・課題は?今後伸ばしたい能力は?」と問いかけても、
すぐに的確に答えられる人は稀ですし、自己評価と他者評価がズレている場合も多々あります。
そこで、まずは「理想的な能力の姿」を仮置きし、
続いて現在地を確認する作業が有効だと説かれています。
ポイントは抽象的な表現ではなく具体的に、
「△△の業務で○○がどの程度できているか」と仕事の実例に紐づけて言語化することです。
そうすることで上司と部下の目線合わせがしやすくなります。
能力のうちできること)については特に主観を排し、本人が客観視できるよう事実ベースで
フィードバックすることが望ましいとも述べられています。
一方で、組織として人員を配置する以上
「ずっと同じ人に同じ仕事をしてもらいたい」という本音もあり、
手放したくない人材をマンネリなポジションに留め続けてしまうケースもあります。
しかしそれは本人のやりがいを奪い、成長機会を塞ぐ可能性があるため望ましくありません。
著者は「キャリア3.0の時代には、部下のキャリア形成を支援できるマネジャーこそ
市場価値が高まる」ことを思い出してほしいと述べています。
部下を囲い込んで目先の業務に縛りつけるのではなく、
長期的に人を育て送り出すくらいの器量が、
これからのマネージャーには求められるということでしょう。
もっとも、組織運営上、本人の希望だけを優先するわけにもいきません。
そこで組織の求める役割と本人の意向の両方を踏まえて、
複数の選択肢から現実的に伸ばせる能力を一緒に考える対話が必要だとしています。
また、どんな仕事でも細分化すれば単調な作業になりえますが、
だからこそ「この仕事は君のWill(ありたい姿)にどう関係するか」
「部署や会社のPurposeにどう繋がるか」を
上司が伝えて共有することが大切だとも述べられています。
自分のやっていることの意義が腹落ちすれば、モチベーションも保ちやすくなるからです。
全ての業務を本人の希望と完全に一致させるのは難しいですが、
それでも「何か1つでいいから、短期的に本人のWillに近く、
Canの開発につながる仕事」をアサインしてみることを最低ラインの意識として推奨しています。
例えば9割はルーティンワークでも、1割は新しいチャレンジを任せてみるといった
メリハリの利いた配分を心がけるわけです。
最後に、キャリア面談等の振り返りの場での姿勢についても触れられています。
基本的には面談ではまず本人にセルフフィードバックを話してもらい、
それを受けて上司がフィードバックを返す、という順序が鉄則だといいます。
上司が一方的に評価を伝えるより、本人に語ってもらう方が内省が深まり、
納得感やモチベーション向上、行動改善につながりやすいからです。
また、部下の悩みが深かったりモヤモヤが晴れない時は、
一回の面談ですべて解決しようと気負わないことも大事だと述べられています。
その場で次のアクションプランまで無理に決めず、
ひとまず話を聞くだけに留めることも場合によっては十分効果があります。
当人が「解決したい」と思える段階になるまで待って、
改めて一緒に考える機会を設ければ良いのです。
上司やメンターも完璧主義になりすぎず、
型にハマらない柔軟な対応が望ましいというアドバイスです。
最後に
ここまで本書について紹介してきました。
組織ぐるみでキャリア自律を促進しようとする企業も増える中、
個人と会社の理想をどうすり合わせるかというテーマまで網羅しているのは
本書の特徴であり、まさにキャリアづくりを
あらゆる角度から捉えた1冊と言えるでしょう。
本書が気になる方は、是非手に取ってみてください!
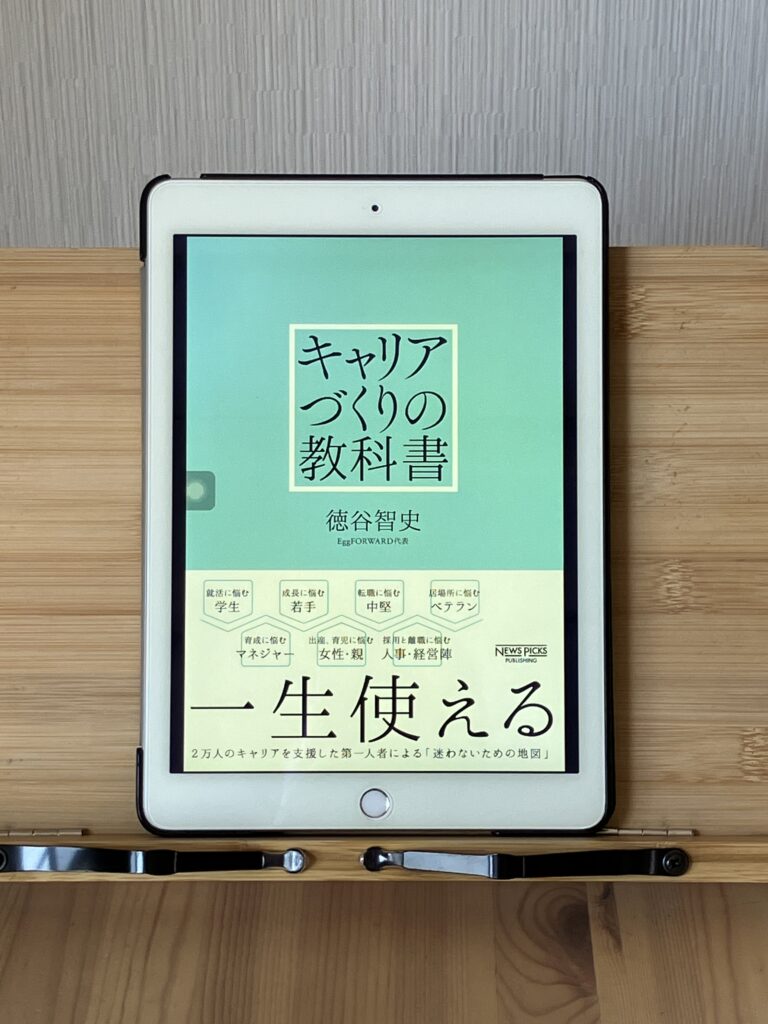
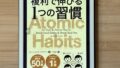

コメント