こんにちは!しょーてぃーです!
今回は、安宅 和人さんの
『イシューからはじめよ』について紹介をしていきます!
『イシューからはじめよ』について
本書の概要
本書はひとことで言うと
「本当に解くべき課題」を見極め、成果を最大化する方法が詰まった1冊です。
本書をオススメしたい人
- いつも仕事に追われ、「やるべきことが多すぎる」と感じている人
- 仕事の生産性向上=作業スピードを上げることだと考えてしまっている人
- 日々の業務で本質的な課題に取り組みたい人
本書は、問題解決に取り組む前に
「そもそも解くべき問題(イシュー)は何か」を見極めることの重要性を説いた1冊です。
著者の安宅和人氏が、自身の経験を通じて編み出した
生産性を飛躍的に高める思考法を本書で紹介しています。
最大のメッセージは、「優れた解決策を導く力」以上に
「解くべき問いを見極める力」が重要だという点です。
世の中に「問題候補」は数あれど、
本当に今答えを出すべき重要課題はごくわずかしかありません。
実際、著者は100ある問題候補の中で、
本当に解決すべきものはせいぜい2〜3に過ぎないと述べています。
したがって、真に価値ある仕事をするには、
まずその2〜3のイシューを見極め、
それ以外の無駄な努力を削ぎ落とす必要があるのです。
本書ではまず「イシュー(本当に取り組むべき課題)とは何か」を定義し、
次に生産性を上げるためになぜイシューから考えるべきかを示した上で、
良いイシューの条件やイシューの見極め方、
さらに選んだ課題に対して、質の高い解を導くための
具体的なアプローチまで、体系立てて解説しています。
単なる理論にとどまらず、コンサルタント流のフレームワークも豊富に紹介されており、
問題設定と解決の双方について学べる内容です。
『イシューからはじめよ』のまとめ
イシューとは何か – 解くべき課題を見極める
本書でいう「イシュー」とは、一言で「本当に取り組むべき課題」のことです。
具体的には、「複数の人々にとって未解決であり、
根本に関わるが白黒はっきりしていない問題」を指します。
ビジネスでは日々様々な「問題らしきもの」が挙がりますが、
そのすべてが解決に値するわけではありません。
安宅氏はまず、「問題はまず『解く』ものではなく、
『解くべき問題を見極める』ことから始めよ」と強調しています。
つまり、闇雲に目先の課題に飛びつくのではなく、
「本当に答えを出すべき問いかどうか」を吟味することが最初のステップなのです。
生産性とバリュー:「犬の道」を避ける
では、なぜイシューを見極めることがそれほど重要なのでしょうか?
理由の一つは、それが仕事の生産性に直結するからです。
本書では生産性を
「成果(アウトプット)÷投入した労力・時間(インプット)」と定義しています。
生産性を上げるには、同じアウトプットを生み出すための時間・労力を削るか、
同じ時間・労力でより大きなアウトプットを生み出すしかありません。
もちろん成果とは、ビジネスにおいて顧客から対価を得られる
「バリューのある仕事」でなくてはなりません。
著者はこのバリューを測る軸として
「イシュー度」と「解の質」を提示しています。
イシュー度とは「自分の置かれた局面でその問題に答えを出す必要性の高さ」、
解の質とは「そのイシューに対してどれだけ明確で質の高い答えを出せているか」という度合いです。
価値の高い仕事とは、このイシュー度が高く、
かつ解の質も高い領域に位置するものだと説明されています。
多くの人はつい「より良い答えを出すこと(解の質の向上)」が
価値に直結すると考えがちです。
しかし本書はその考え方を否定し、
「課題の質」すなわちイシュー度こそが決定的に重要だと説きます。
なぜなら、いくら解の質を高めても、
イシュー度の低い(解決する必要性が低い)問題であれば、
その仕事の価値はゼロに等しいからです。
極端な例をいえば、誰も困っていない問題を必死に解決しても、
得られる成果は無意味に終わります。
したがって生産性を上げるには、
まず解決すべきイシューを正しく見極めて不要な作業を大胆に削り落とし、
限られたリソースを本当に価値の高い解答に集中させる必要があります。
ここで著者が戒めるのが、誤った努力の仕方である「犬の道」です。
犬の道とは、「一心不乱に大量の仕事をこなせばいつか価値ある成果に届く」と信じて
闇雲に努力するアプローチを指します。
しかしその方法では真に価値ある成果が生まれる可能性は限りなくゼロなのです。
著者は「世の中で『問題かもしれない』と言われることが100あれば、
今この局面で本当に答えを出すべき問題はせいぜい2〜3つしかない」と述べています。
そのわずかな当たりの課題に集中せず無数のタスクに手を広げていては、
生産性が上がらないのも当然です。
逆に言えば、重要な2〜3のイシューさえ見極めれば、やるべき仕事は劇的に絞り込まれるのです。
良いイシューの3条件
「解決すべきイシュー」の条件として次の3つが挙げられています。
本質的な選択肢であること
その問いに対する答え次第で、
後の方針や戦略が大きく変わるような、本質的分岐点となる課題か。
例えば製品Aの売上不振の原因を考える際、
「製品A自体に問題があるのか」
それとも「製品Aには問題はないが売り方に問題があるのか」という問いの立て方によって、
後の戦略の方向性は大きく異なります。
このように結論の違いで意味合いが変わる問いこそ、本質的なイシューと言えます。
深い仮説があること
一般に信じられている前提を覆すような洞察に富む仮説が存在しているか。
つまり、常識を疑う視点や鋭い仮説をもって問題に臨める課題かどうかです。
表面的な仮説しか立てられないテーマより、
意外性のある仮説によって新たな発見をもたらせるテーマの方が、追求する価値が高いでしょう。
答えを出せること
その問題に対して明確な答えを導き出すことが現実的に可能かということです。
ビジネスには構造的に正解を出せない問いも多く存在します。
どんなに本質的で深い仮説を含んでいても、
検証不能で答えを出せない課題ではイシューたりえないのです。
誰もが重要と感じつつ「難しくて手が出ない」と思っている問題に対し、
「自分なら答えを出せる」と思える盲点的なイシューを発見できれば
理想的だと著者は述べています。
以上のポイントを念頭に置けば、
日々の業務でも「そもそも何を解決すべきか」を考える指針になります。
重要度・仮説の深さ・答えの出しやすさという観点から、
自分の状況で真に取り組むべき課題を選び抜くことが、
生産性の高い仕事の第一歩と言えるでしょう。
イシューを見極める方法:仮説と思考のフォーカス
では実際にイシューを見極めるにはどうすればよいでしょうか。
本書は、具体的な仮説を立てて言語化することが鍵になると説きます。
闇雲に「〇〇について調べよう」と動き出すのではなく、
「もしかすると〇〇ではないか?」という仮説を、自分なりに設定してから検証を始めるのです。
仮説なしに情報収集を始めてしまうと、どこまで調べても答えにたどり着けず、
永久に答えが出ない問いを追いかける危険があります。
逆に具体的な仮説があれば、
「何を・どこまで調べれば十分か」がはっきりし、無駄な作業が減ります。
例えば「△△市場の規模はどれくらいか?」という
漠然とした設問にすぐ取り掛かるのではなく、
「△△市場の規模は縮小しつつあるのでは?」と仮説を立ててから
情報収集を始めるべきだと本書は述べています。
仮説形にすることで、「本当に確かめるべきこと」が明確になり、
答えを出し得るイシューへと具体化できるわけです。
また著者は、イシュー見極めの際には情報収集に入る前に
専門家の意見を聞いて視野を広げることや、
仮説に基づき一次情報を集めることも有効だと述べています。
まず業界やテーマの専門知見に当たって有望な論点のヒントを得て、
次に現場の生の情報で裏付けることで、
机上の空論に陥らない実践的な課題設定が可能になります。
こうして仮説を適宜更新しつつ、
本当に答えを出すべきイシューかどうかを見極めていくのです。
解の質を高めるためのアプローチ
イシューを特定したら、次はその課題に対して
質の高い答えを導き出すフェーズです。
安宅氏はマッキンゼー仕込みの問題解決術として、
仮説ドリブン → アウトプットドリブン → メッセージドリブンという思考ステップを提唱しています。
仮説ドリブン
まず初めに仮説ありきで分析に臨む姿勢です。
仮説を立てることで検証すべきポイントが定まり、分析の無駄を省けます。
常に「自分の仮説は何か?」を意識して情報収集・分析を進めれば、
効率的に答えに近づくことができます。
アウトプットドリブン
分析の途中でもアウトプット(成果物)から逆算して考える視点を持つことです。
最終的にどんな形で結論を提示したいか、
ゴールイメージを描きながらデータ分析を進めます。
例えば「どんなグラフや比較結果が出れば仮説を裏付けられるか?」と考え、
その結果を得るために必要な作業に集中します。
分析が自己目的化してデータの海に溺れないよう、
常にアウトプット重視で効率的に検証を進めることが重要です。
メッセージドリブン
最後は伝えたいメッセージを軸に考える段階です。
得られた結論を効果的に伝えるため、
結論から逆算してストーリーラインを構築します。
最終的に伝えたいポイントを定め、それを裏付ける論拠やデータを配置していくことで、
筋の通った明快なプレゼンテーションが可能になります。
著者はこれを「ストーリーを絵コンテにする」と表現しており、
分析段階からプレゼンの骨子を意識することで、ブレない結論を導けるとしています。
さらに本書では、「分析の本質とは比較である」という重要な指摘もなされています。
高度な統計手法を思い浮かべがちですが、根底にあるのは適切な軸で対象を比較し、
その差異から意味を読み解くことだといいます。
例えば単に「A社の業績は良い」と述べるだけでは分析になりませんが、
業界平均や競合他社と比較することで
初めてその好調さの意味が見えてきます。
なお本書では具体的な問題解決手法も多数紹介されていますが、
すべてを使いこなすことより「なぜイシューから始めるのか」を理解し、
自分の仕事に活かせる部分を取捨選択することが大切だと著者は述べています。
最後に
ここまで本書について紹介してきました。
忙殺されがちなビジネスパーソンに
立ち止まって考える大切さを思い出させてくれる1冊です。
本書が気になる方は、是非手に取ってみてください!
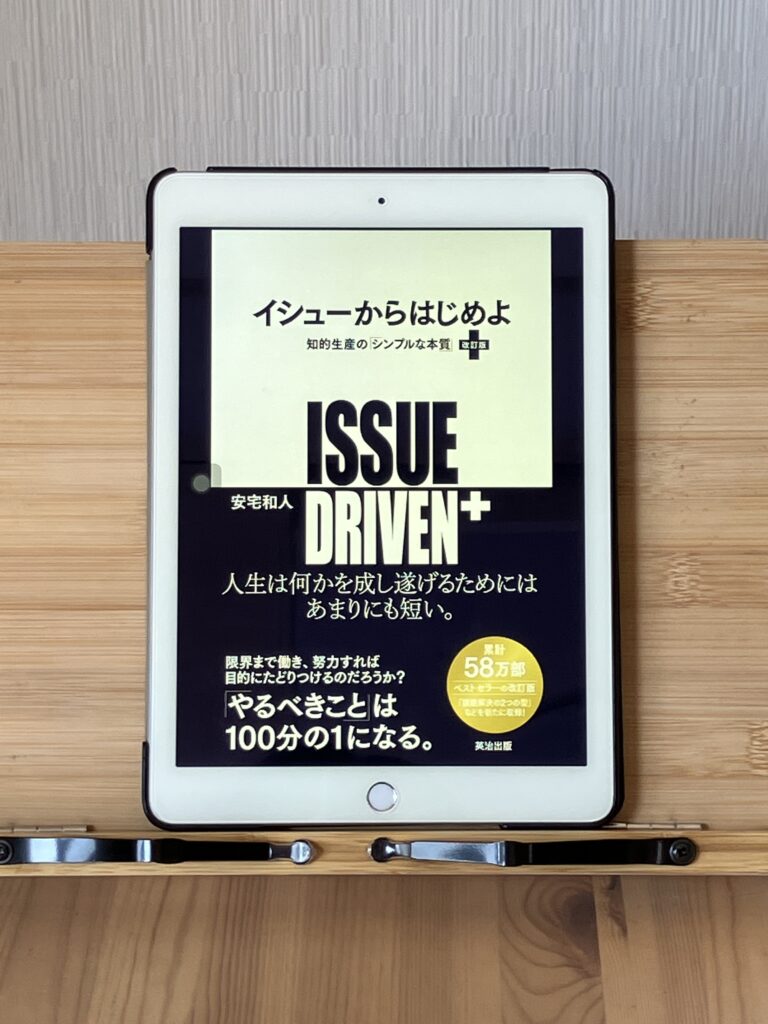


コメント