こんにちは!しょーてぃーです!
今回は、朝井リョウさんの
『イン・ザ・メガチャーチ』について紹介をしていきます!
『イン・ザ・メガチャーチ』について
本書の概要
本書はひとことで言うと
現代の狂熱をリアルに描いた1冊です。
本書をオススメしたい人
- アイドルや俳優の推し活文化やファン心理に興味がある人
- SNS時代の熱狂や集団心理をテーマにした社会派小説を読みたい人
- 朝井リョウの作品が好きで、現代社会を鋭く描く物語に惹かれる人
本作は、「推し活」や「ファンダム経済」といった現代的なテーマを軸に、
異なる立場や背景をもつ3人の登場人物の視点から描かれる重層的な群像劇です。
物語に登場するのは、仕事にも家庭にも行き詰まりを感じている中年男性・久保田、
居場所のなさを感じながら日々を過ごす女子大学生・澄香、
そして推しの舞台俳優を支えに生きる派遣社員の絢子。
それぞれが「推し」によって心を動かされ、
生きる意味を見出す一方で、その熱狂が徐々に日常や人間関係を変化させていきます。
物語の背景には、「物語の力」がどのように人を突き動かし、
時に現実を侵食するかという問いがあります。
アイドル運営側が意図的に作り出す“感動のストーリー”や、
SNSで拡散される陰謀論のような“もう一つの現実”が、
人々の心を強く揺さぶり、時には理性をも超えて行動を促してしまう
そんな現代社会の光と闇が丁寧に、しかし容赦なく描かれています。
タイトルの「メガチャーチ」とは、
信仰や物語に人々を引き込む構造を象徴するもので、
信仰の対象が神から推しに変わった現代の一面を風刺的に表しています。
本作は、その構造を通して、
「私たちはなぜ、誰かを信じ、熱狂し、時に暴走するのか?」という
普遍的なテーマにも迫っています。
そして、朝井リョウさんデビュー15周年を記念する本作は、
エンタメ性と社会批評を高い次元で融合させた力作であり、
書店員から「今年一番の衝撃作」として高い評価を集めています。
読者の心に鋭く突き刺さるメッセージ性と、
精緻な構成によって構築されたストーリー展開は、読後に深い余韻と衝撃を残します。
『イン・ザ・メガチャーチ』のあらすじ
あらすじの概要
沈みゆく列島で、“界隈”は沸騰する。
あるアイドルグループの運営に参画することになった、家族と離れて暮らす男。内向的で繊細な気質ゆえ積み重なる心労を癒やしたい大学生。仲間と楽しく舞台俳優を応援していたが、とある報道で状況が一変する女。ファンダム経済を仕掛ける側、のめり込む側、かつてのめり込んでいた側――世代も立場も異なる3つの視点から、人の心を動かす“物語”の功罪を炙り出す。
「神がいないこの国で人を操るには、“物語”を使うのが一番いいんですよ」
イン・ザ・メガチャーチ より
この物語は三人の登場人物の人生が交錯しながら進んでいきます。
それぞれが抱える孤独や葛藤、そして“推し”への思いが、
やがて一つの大きな物語へと収束していきます。
久保田慶彦:停滞した日々と再燃する情熱
久保田慶彦(くぼた よしひこ)は47歳のサラリーマン。
かつて情熱を注いだ外資系音楽レーベルでの仕事から現在は経理部門に異動となり、
仕事にも人生にも煮詰まりを感じる毎日です。
家庭では離婚を経験し、娘とも離れて暮らしており、
自分が時代に取り残されていくような虚しさを抱えています。
そんなある日、久保田は同僚だった橋本から声をかけられます。
橋本は今や人気アイドルグループのプロデューサーとして名を馳せており、
「もう一度一緒に働かないか」と久保田を誘ってきたのです。
久保田は久しく忘れていた胸の高鳴りを感じ、
停滞した自分を変えるチャンスだと考えてこの誘いを受けます。
こうして彼はアイドルグループの運営スタッフとして再出発を切ることになります。
しかし彼が任されたのは、
自身が思い描いていた華やかな音楽制作とは少し異なる役割でした。
久保田は裏方としてグループを支える中で、
ファンの熱狂を意図的に生み出す“物語”作りに関わっていくことになります。
「神がいないこの国で人を操るには、“物語”を使うのが一番いいんですよ」
久保田は戸惑いつつも、その言葉に示唆される現実、
熱狂的なファン心理をビジネスに転換する手法を目の当たりにしていきます。
武藤澄香:孤独な大学生と推しとの出会い
武藤澄香(むとう すみか)は内気で繊細な女子大学生です。
高校時代から「海外志向」で洋楽や洋画に傾倒し、
自分は日本のミーハーな流行とは一線を画しているつもりでいました。
しかし実際には周囲に馴染めず、留学の夢もうまくいかず、
自分に自信が持てない日々を過ごしています。
空虚な日常を埋めるようにSNSに目を向けては、
他人への劣等感と自己嫌悪に苛まれていました。
そんな澄香がある日ふと目にしたのが、とある新人アイドルの動画でした。
そのアイドルが放つひたむきさや輝きに、
自分でも驚くほど強く心を動かされます。
気付けば彼女はそのアイドルを“推し”と呼び、
ライブ配信を追いかけ、グッズを買い集め、初めて熱中できるものを見出します。
皮肉にも、かつて内心で馬鹿にしていたはずの「推し活」の世界に、
自らのめり込んでいったのです。
澄香にとって推し活は単なる娯楽以上の意味を持ち始めます。
それは自分の孤独を埋め、同じ趣味を持つ人と繋がることで
居場所を得る手段でもありました。
しかし、夢中になるほど彼女の視野は狭まり、
日常生活とのバランスが崩れていきます。
SNSで見かけた狂信的なファン集団「りんファミ」のことを
嘲笑していた彼女でしたが、いつしか自分自身も
「推しのためなら多少無理をしても構わない」と考えるようになっていくのでした。
隅川絢子:“推し”に支えられた日常の崩壊
隅川絢子(すみかわ あやこ)は30代半ばの独身女性。
正社員ではなく派遣社員として働き、
将来への不安を抱えながら日々を過ごしています。
そんな絢子にとっての生きる支えは、
職場の先輩である友人と一緒に通っている
若手舞台俳優・藤見倫太郎(ふじみ りんたろう)の公演を応援することでした。
二人で“推し活”に励む時間だけが、
絢子にとって心から楽しく充足感を得られるひとときだったのです。
ところがある日、テレビやネットニュースで
藤見倫太郎が若くして急逝したことが報じられます。
突然の推しの死。
絢子は現実を受け入れられず、大きな喪失感に襲われます。
同時に、藤見の熱狂的ファンコミュニティ「りんファミ」の動向が
世間の注目を集め、SNSでは「#りんファミ」がトレンド入りする騒ぎとなりました。
悲しみに暮れるファンたちの中には取り乱す者もおり、
社会現象の様相を呈していきます。
絢子も心の拠り所を失い、精神的に不安定になっていき
彼女の周囲も一変し、共に推し活をしていた先輩友人との関係にも微妙な変化が生じます。
唯一の楽しみを奪われた喪失感から逃れるように、
絢子はネット上で同じ痛みを抱えたファンたちと繋がろうとします。
しかし、その過程で過激な陰謀論に触れることになりました。
ある陰謀論者が「藤見倫太郎の死の真相」について煽動的な情報を流し始め、
悲しみに暮れるファンたちの心に付け入ったのです。
藤見の死にまつわるデマや噂が飛び交う中、
絢子は次第に正常な判断力を失っていきます。
悲しみと怒り、そして何かにすがりたいという衝動に突き動かされ、
彼女はある行動に出ようとします。
その行動は常軌を逸したもので、
取り返しのつかない事態を招く引き金となっていきました。
交錯する物語、そして衝撃の結末
藤見倫太郎の死をきっかけに、三人の物語は思わぬ形で交差し始めます。
久保田が携わるアイドル運営側でも、この出来事によるファン心理の変化に対して
何らかの対応を迫られることになりました。
橋本ら運営陣は「物語」を利用して
ファンの関心を引き留めようと策を巡らしますが、
その手法は危うい綱渡りでもあります。
一方、澄香は「推しがいる幸せ」を噛みしめる中で、
藤見の件に関するネットの狂騒ぶりに複雑な思いを抱きます。
やがて澄香と絢子、そして久保田の運命が接点を持つとき、
物語は急速に緊張感を高めていきます。
物語の後半では、ネット上の陰謀論や熱狂するファン心理が
現実世界で暴走を始め、三人それぞれがその渦に巻き込まれていきます。
久保田は運営サイドの人間としてファンの暴走を食い止めようと奔走しますが、
自身もまたその熱狂の一端に取り込まれていくことに気付くのです。
澄香は推しへの想いと理性との間で揺れ動き、
絢子を含む「りんファミ」の暴走を目の当たりにして恐怖を覚えます。
絢子はもはや現実検討ができない状態で、遂に重大な決断を下してしまいます。
そして迎えるクライマックス。物語は絶望的な結末へとなだれ込み、
救いのない結末が読者の心に重く突き刺さります。
狂信に取り憑かれた人々の行動は取り返しのつかない結果を生み、
残された者たちは深い喪失感と虚無に覆われます。
絶望的な状況の中で、久保田はふとある大切な事実に思い至ります。
それは、「自分が今も昔も本当に大切にすべきものは誰だったのか」という問いです。
久保田は最後にようやく気付くのです。
「どうしてわからなかったのだろう。今も昔も、一番に大切にすべきは我が娘だった…」
狂おしいほどの熱狂の日々を経て、彼が辿り着いた答えはあまりにもシンプルで、
しかしあまりにも遅すぎる悟りでした。
自らの娘という現実の存在に背を向け
、“物語”に夢を託してしまっていたことへの後悔が、静かに胸を締め付けます。
『イン・ザ・メガチャーチ』の感想
メガチャーチ タイトルに秘められた意味
本書のタイトルは
「若者の教会離れを食い止める方法を経済に応用する」という
学問用語に由来しています。
つまり、「信仰という物語」を「商売という現実」に変換することが
テーマの一つになっているのです。
読んでいくと、このタイトルがまさに物語全体を象徴していることに気付かされます。
アイドルや俳優への熱狂
それは宗教的な「信仰」にも似たものであり、
運営側はそれを巧みに利用してビジネスとして成り立たせている。
いわば本作の舞台となるファンダムは、巨大な“教会”のようなものなのです。
作中では、熱心なファンたちがまるで信徒のように振る舞う場面が印象的でした。
推しの成功を自分のことのように喜び、
推しのためとあらば多少の無理や規範逸脱も正当化してしまう。
極端な例では「推しのためにやっているのだから犯罪を犯しても許される」といった暴走すら描かれます。
現実の社会ルールよりも、自分たちが信じる物語の方が優先されてしまう。
その危うさと恐ろしさを、朝井リョウは容赦なく描き出しています。
熱狂がピークに達したファンの心理はまさに“宗教”さながらであり、
本作を読みながらタイトルの示唆する意味に何度も頷かされました。
全方位に切り込む社会批評
本作は単にオタク文化やファン心理を批判する物語ではありません。
むしろ、本作が凄いのはあらゆる立場の人間のエゴや
弱さを浮き彫りにしている点です。
アイドル運営側の打算や、ファン側の盲信だけでなく、
登場人物それぞれが抱える孤独・焦燥・承認欲求といった
現代人の抱える問題が生々しく描かれます。
本作は特定の誰かに肩入れすることなく、
登場人物全員を時に冷徹なまでに描写しています。
若者も中年も、男性も女性も、リア充も陰キャも、善人も悪人も
あらゆる属性の人間が物語の中で等しく
自己中心的で滑稽な部分を暴かれていくのです。
読んでいて感じたのは、「誰のことも安易に肯定しない姿勢」の徹底ぶりでした。
多くの物語では、どこか一人のキャラクターに感情移入させたり、
悪役を作ってカタルシスを得たりしがちです。
しかし本作では、登場人物たちの言動に
「それは違うだろう」と思う場面が多々ある反面、
全員に心当たりのある欠点や身勝手さが描かれていて、
読者は自分自身を省みるような不思議な感覚に陥ります。
加えて、本作が優れているのは、
こうした社会批評をエンターテインメントとして高い次元で融合させているところです。
物語は終盤に向かうにつれスリリングさを増し、
先が気になってページを捲る手が止まらなくなりました。
陰謀論という要素まで飛び出し、物語が交錯していく展開は純粋にスリルがあります。
それでいて、「誰かが改心してハッピーエンド」的な
お決まりの展開には決して逃げず
最後の最後まで現実は容赦なく突きつけられ、
読後にはなんとも言えないやるせなさが残りました。
この徹底ぶりこそ、本作が単なる娯楽小説の域を超えて
強烈なメッセージ性を帯びている所以でしょう。
巧みな構成と圧巻の読後感
朝井リョウの文章力・構成力も見事でした。
三者三様の視点が時間軸を前後しながら展開する物語ですが、
全体の整合性は最後まで崩れません。
場面がテンポ良く切り替わっていくにも関わらず
読みづらさを感じないのは、文章が非常に練られていて洗練されているからでしょう。
複雑に入り組んだプロットが破綻なく一つの作品に収斂していく様は圧巻で、
読了後に振り返って「よくこれだけの内容を綺麗にまとめ上げたな」と
思わず唸ってしまいました。
また、随所に光る比喩表現や会話のテンポの良さも特筆すべき点です。
登場人物のやりとりの中で、
「子どもから玩具でも取り上げるように、国見は言った。」や
「濁音が、まるで小さな爆発音のように響く」といった描写が差し込まれ、
情景や緊張感が鮮やかに伝わってきました。
セリフ回しも独特でセンスが良く、
それでいて過剰にならず物語のリズムを損なわない絶妙な塩梅です。
著者の卓越した文章センスによって、
読者は終始物語に引き込まれ、ラストまで一気に読まされてしまいます。
そして何と言っても読後のインパクトが凄まじいです。
救いのない結末ではありますが、
不思議と「読まなければよかった」とは思いません。
それどころか、胸の奥にじわじわと痛みが広がるような、
心を抉られる読後感が「読んで良かった」という確かな手応えに変わっていきました。
自分が何を信じ、何に時間や情熱を捧げるのか
その問いを読者一人ひとりにも突き付けてきます。
最後に
ここまで本書について紹介してきました。
現代日本の抱える“熱狂”や“物語”の力を
真正面から描き切った意欲作です。
読み進めるほどに引き込まれ、最後には言葉を失うほどの衝撃を受けました。
本書が気になる方は、是非手に取ってみてください!
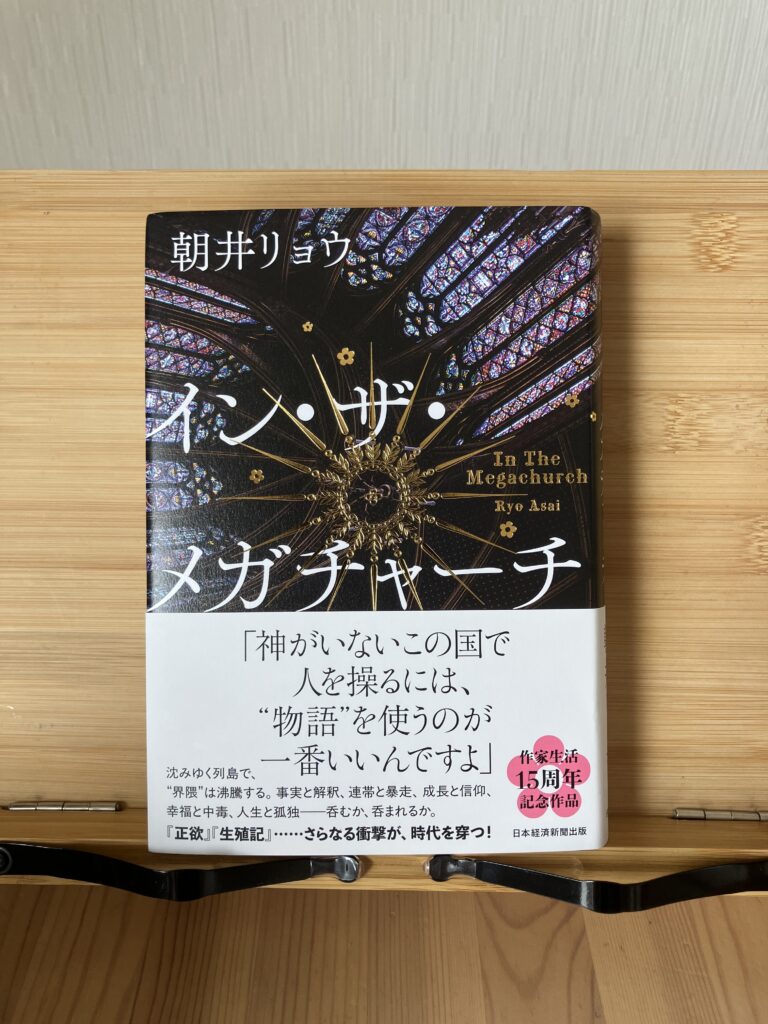
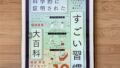

コメント