こんにちは!しょーてぃーです!
今回は、ユヴァル・ノア・ハラリさんの
『NEXUS 情報の人類史 上 人間のネットワーク』について紹介をしていきます!
『NEXUS 情報の人類史 上 人間のネットワーク』について
本書の概要
本書はひとことで言うと
神話からマスメディアまで、情報が人類を動かしてきた軌跡を解明する1冊です。
本書をオススメしたい人
- 歴史や人類学が好きな人
- テクノロジーや社会問題に興味がある人
- 『サピエンス全史』『ホモ・デウス』『21 Lessons』を読んだ人
本書は、歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリによる6年ぶりの新作です。
石器時代から現代AI時代に至るまでの人類の歴史を
「情報ネットワーク」の観点から読み解きなおし、
なぜ私たちホモ・サピエンスが自らを破滅させかねない愚行を繰り返すのか、
その原因に迫る壮大な試みとなっています。
上巻である本書では、人類文明の礎となった「人間のネットワーク」の歴史を辿り、
古代の神話・文字の発明から印刷術・マスメディアの登場まで
情報伝達が人類社会にもたらした結束と対立の歴史を明らかにします。
下巻「AI革命」と合わせ全600ページ超に及ぶ大著であり、
情報史の通観を通じて21世紀の民主主義の危機や
AIの影響を考えるための洞察を提供する内容です。
『NEXUS 情報の人類史 上 人間のネットワーク』のまとめ
情報とは何か:人類史における情報の力とは
まずハラリは、「情報とは何か?」「真実とは何か?」という根源的な問いを立て、
人類の歴史において情報が果たしてきた役割を概観します。
ホモ・サピエンスが他の生物を凌駕する途方もない力を獲得できた背景には、
大規模な情報共有ネットワークの存在がありました。
私たちは言語やシンボルを駆使して情報を伝達・蓄積し、
知識を世代間で共有することで文明を築いてきたのです。
その反面、賢いはずの人類が生態系破壊や戦争など自滅的な危機を招いているのも事実であり、
その原因を解く鍵が「情報ネットワークの歴史」にあるとハラリは指摘します。
第1章では情報と真実の関係、そして原始時代から現代に至る情報伝達の進化が、
人類社会に与えた影響を俯瞰して導入しています。
物語 虚構が生む大規模協力
ハラリは『サピエンス全史』で提示した「認知革命」のテーマを本書でも発展させ
人類は、物語を語る動物であると強調します。
神話や宗教、国家の理念などの共同主観的な「虚構」=物語が登場したことで、
見ず知らずの大勢の人々同士でも協力できるようになり、
巨大な国家・企業・宗教組織が成立しました。
物語という情報ネットワークが人類文明の裏にあった立役者であり、
人類は虚構を介して初めて大規模なネットワークを構築できたのです。
本書でもこの視点から歴史が語られ、
例えばユダヤ人社会では「あなたの魂もモーセが十戒を受けた場に居合わせたのだ」という語り方で神話を
自分事として共有する伝統が紹介されます。
こうした語りによって世界各地に離散しても
数千年にわたりユダヤ人としてのアイデンティティが維持されてきたことは、
物語が生む結束の力を示す象徴的な例です。
人類に無限のつながりをもたらす物語の力と、
それが時に「高貴な嘘」となって葛藤を生む永続的なジレンマについて論じられています。
文書 文字が生んだ制度と権力
次にハラリは、文字の発明と文書記録の発達によって
情報ネットワークが飛躍的に拡大した歴史を追います。
粘土板に刻まれたメソポタミアの貸付契約から始まり、
古代ローマ帝国の行政文書、中国・秦始皇帝の統治における文字の統一、
カトリック教会の聖典管理など、
書かれた情報が権力や統治に果たした役割が具体例とともに紹介されます。
文書によって情報は空間と時間を超えて保存・伝達されるようになり、
複雑な官僚制度や法律体系、学術知の蓄積が可能になりました。
ハラリはこれを「紙というトラの一嚙み(かみ)」という比喩で表現し、
紙の文書が時に現実の虎の一撃にも匹敵する威力を持ったことを示唆しています。
例えば、古代において契約書という文書一枚が人の生死や財産を左右し、
書かれた法律が王や将軍の権威をも凌駕する場面もあったでしょう。
文書検索技術の発展と官僚制の確立、
そして官僚制が「真実の探求」に与えた影響についても考察されます。
著者は自身のユダヤ人の家族の例も挙げています。
祖父母が迫害を受け故郷を追われた経験から、
「いつ何が起きてもよいようあらゆる公的書類を絶対に捨てず保管している」というエピソードは、
記録された情報の重要性を物語っています。
誤り 「完璧な情報」を求める罠と自己修正
情報ネットワークには誤情報や錯誤の問題もつきまといます。
人類が「誤りなく完全な情報」を求めてきた歴史と、その幻想の危うさが描かれます。
古くは聖書など宗教文書の編纂において矛盾を無くそうとする試みや、
中世から近代にかけて権威ある制度が
自らの誤りを認めず硬直化した例が取り上げられます。
しかし近代になると、人類は「自らの無知の発見」という転換を迎えます。
すなわち、自分たちは完全な真理を持っていないと認めることで科学革命が興り、
試行錯誤しつつ知識を更新していく自己修正メカニズムが社会に組み込まれるようになりました。
一方で、新たな情報技術である印刷術は知の発展に寄与する一方、
情報の氾濫が招く負の側面も生み出しました。
ハラリが興味深い例として挙げるのは17世紀ヨーロッパの魔女狩りです。
印刷技術の発達によって、魔女に関する虚偽だらけの本がベストセラーになり
魔女狩りの指南書として流布した結果、大衆が狂気に駆られて魔女狩りという大量虐殺に突き進んでしまったのです。
これは情報メディアの発展が引き起こした集団ヒステリーの典型例であり、
現代の陰謀論拡散にも通じる警告と言えます。
さらに著者は、現代の情報環境におけるエコーチェンバー現象にも言及し、
人々が自分に都合の良い情報ばかりを聞く循環が、いかに「誤りの自己増幅」を招くかを指摘します。
学術の世界では「出版か死か(Publish or Perish)」という言葉に象徴される
競争原理が研究の質を歪める可能性も論じ、
いかにして社会が情報の誤りを検知・訂正し続けるかという課題について考察を深めています。
決定 情報ネットワークから見る民主主義と全体主義
政治体制と情報ネットワークの関係にも焦点が当てられます。
ハラリは人類史における民主主義と全体主義の揺れ動きを、
「情報の流れ」という軸で論じています。
まず原始時代の小規模社会では合議的(民主的)な意思決定が行われていた可能性に触れ、
直接民主制は村落や都市国家といった小さな単位でこそ機能することを指摘します。
しかし近代以降の国民国家レベルでの民主主義は、
新聞・ラジオなど情報を広範囲に届ける仕組みの発展なしには、成立し得なかったとも述べています。
実際、19〜20世紀における印刷メディアやラジオ・テレビの普及は、
大衆(マス)民主主義の成立を可能にしました。
一方で同じ大量伝播メディアは大衆全体主義も生み出しうる刃でもありました。
例えば20世紀前半、ラジオや新聞を利用したプロパガンダにより
ナチスやソ連などの全体主義体制が民衆の熱狂的支持を得て成立した歴史があります。
ハラリは古代のスパルタや秦の始皇帝の統治から、
20世紀のファシズム・共産主義体制まで情報統制による支配の系譜を辿りつつ、
ポピュリズム(大衆迎合主義)が「多数派による独裁制」となって真実を脅かす危険性も論じます。
民主国家と独裁国家では情報の流れ方が根本的に異なり、
前者では言論の自由と多様な意見の衝突から合意が生まれるのに対し、
後者では検閲と宣伝によって一方通行の「真実もどき」が作り出されます。
著者はまた、テクノロジーの発達によって
権力の在り方が振り子のように揺れ動くことにも言及しています。
ときに新しいメディア技術が民主主義を強化する一方、
別の時代には新技術が独裁者に完全なる監視と統制を許す繰り返しが歴史には見られるのです。
最後に
ここまで本書について紹介してきました。
類史の長大なスパンを通じて情報と権力のダイナミクスを描き出すことで、
現代世界を読み解く視座を提供してくれます。
ハラリの語り口は学術的知見に裏打ちされつつ平易で親しみやすく、
歴史に詳しくない一般読者でもストーリーを追うように学べるの一冊となっています。
本書が気になる方は、是非手に取ってみてください!
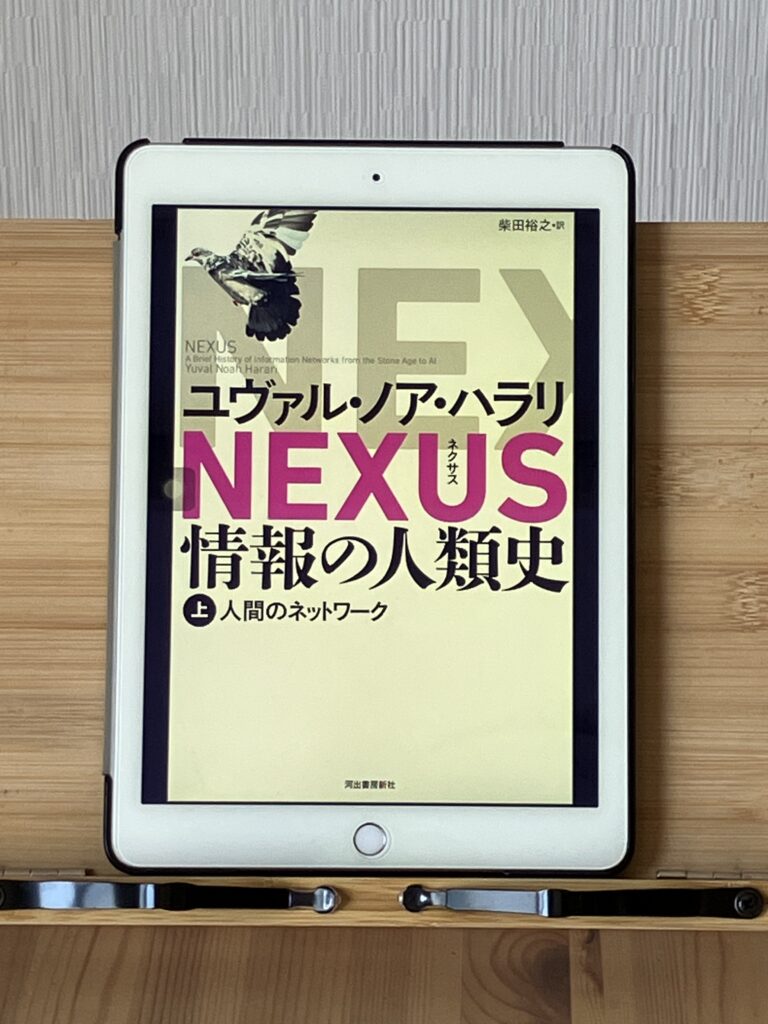

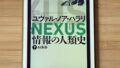
コメント