こんにちは!しょーてぃーです!
今回は、舟津昌平さんの
『Z世代化する社会 お客様になっていく若者たち』について紹介をしていきます!
『Z世代化する社会 お客様になっていく若者たち』について
本書の概要
本書はひとことで言うと
「最近の若者」像への先入観が覆る1冊です。
本書をオススメしたい人
- 同僚がZ世代で「最近の若手は扱いにくい…」と悩む人
- Z世代の消費傾向や価値観を知りたい人
- 現代の若者文化や社会変化に関心のある人
本書は、Z世代と呼ばれる若者の実態を通じて
現代社会の在り方を明らかにしようとする社会論的な1冊です。
著者の舟津昌平さんは1989年生まれの東京大学講師で、
自身が日々接する大学生たちへの取材や調査をもとに、
SNSでの立ち振る舞いから就職活動、職場での価値観まで、
若者文化をユーモラスかつ深く描写しています。
タイトルにある「お客様になっていく若者たち」が示す通り、
現在の若者が学校や職場で“自分はお客様”のように振る舞う傾向に注目しつつ、
「なぜ彼らはそうなったのか?それは若者固有の問題ではなく
我々社会全体の問題ではないか?」という視点で論じているのが特徴です。
単に若者像を批判するのではなく、若者に内在する“不安”をキーワードに据えて、
そこから見える社会構造や企業の動向分析しており
最終的には世代間の溝を埋め、
より良い未来を築くための示唆を与えてくれる内容となっています。
『Z世代化する社会 お客様になっていく若者たち』のまとめ
Z世代のリアリティ:SNS・学校での姿
第1章では、Z世代の「住処」として
SNSや学校・友人関係における若者のリアルが描かれます。
例えば、SNSでは過度に目立つ投稿は「イタい」とされ敬遠されます。
Instagramでキラキラした写真を投稿しつつも、
「自己満です(自己満足のアカウントです)」と
プロフィールに断り書きを入れて批判を避けるなど、
「イケてるけどイタくない」微妙な均衡を保とうとするのが最近の若者の処世術です。
人一倍他人の目を気にし、「痛々しいほど空気を読んでいる」姿が見えてきます。
また、リアルの学校生活でも「お客様化」が進んでいます。
舟津氏自身の授業で、学生から「知らないことばかり扱われて不安だった」
「発音を直されて不愉快。先生の方が間違っているのでは?」といった
コメントが出た例が紹介されます。
まるで大学の授業をサービスとして消費しているかのように
学生が振る舞うこの現象に、著者は驚きを持って報告しています。
「大学は学びを共に創る場のはずが、
テーマパークのように『大学に満足を提供してもらう場』と
捉えられているのではないか」という指摘は鋭く、
本書の副題「お客様になっていく若者たち」を象徴するエピソードと言えます。
こうした環境では教師側も下手に叱責や注意ができず、
「踏み込まず淡々と接する」ようになるため、
学生は「黙って座っている=いい子」という学習をしてしまう。
しかし社会に出れば受け身でいるだけでは評価されません。
このズレが後に述べる若者の不安にも繋がっていきます。
消費の主役となる若者たち:コスパ志向と経営者化
第2章では、消費社会におけるZ世代に焦点が当たります。
ここでキーとなるのが若者の「コスパ」「タイパ」志向です。
無駄なお金や時間を嫌い効率を重視するのは誰しも同じですが、
Z世代はそれを日常生活の細部まで徹底しているように見えます。
本書では大学生の会話として、学期初めに
「あの授業、コスパ悪いから切ったわ」
(=出席厳しく課題が多いので単位取得に労力がかかる授業は履修をやめた)という例が紹介されています。
週23時間ほど節約できる計算になりますが、
その分空いた時間で別の勉強や有意義な活動をするわけでもない。
このようにコストを惜しむあまり
パフォーマンスを何も得ていないケースが多々あり、
著者は「コスパ志向の罠」として警鐘を鳴らします。
つまり「コストばかり気にして本当に大事なパフォーマンスを得ていない」という
本末転倒に陥っていないか、という指摘です。
さらに著者は、このような考え方が蔓延する背景に
社会全体の「経営者化」傾向を読み取ります。
若者だけでなく我々大人もまた効率至上主義に染まりすぎていないか
これは「自分自身を経営するように人生を最適化せよ」というプレッシャーが
社会に広がっているのではないかという問いかけです。
実際、本章では企業側の視点も交え、若者が消費の主役として注目される一方で、
彼ら自身がビジネスの論理に絡め取られている実態が描かれます。
例えば、「安くて速い」ばかりを求める消費者マインドは便利さを生む一方で、
本当に価値あるものを見失わせる可能性があります。
本書はユーモアを交えつつも、効率重視社会の光と影を
若者の行動から浮かび上がらせているのです。
言葉が現実を作る?:唯言論と非倫理的ビジネス
第3章のタイトルは難解ですが、「唯言が駆動する非倫理的ビジネス」とあります。
ここでキーワードになるのが「唯言論(ゆいげんろん)」という考え方です。
簡単に言えば、「言葉が独り歩きして実体(内容)を持たないまま
現実を形作ってしまう」現象を指します。
著者はこれを若者の世界に当てはめ、いくつか興味深い実例を挙げています。
例えば、クラス内で人気者の女子に嫉妬した上位カーストの生徒が
「よく見るとあの子ってブサイクだよね」と言いふらしたら、
いつの間にかクラスの共通認識が「彼女はブサイク」になってしまった…という話。
事実かどうかではなく、言葉が広まることで“事実”が後付けで構築されてしまう典型です。
大学生の例では、年長者の講演を聞いた学生が感想で
「途中で宗教みたいだと思った」と言った途端に、その講演の価値が矮小化され
嘲笑の対象になってしまったというエピソードも紹介されています。
熱心なアドバイスですら「説教かと思いましたよ」と一言ラベリングされれば
「空気の読めない説教おじさん」で片付けられてしまう。
このように、Z世代の間では不用意な熱血・精神論は
すぐ嘲笑のネタにされる傾向があるといいます。
言葉ひとつで相手を貶めて優位に立つ「唯言の暴力」が跋扈する背景には、
インターネット上の煽り文化や匿名コミュニティの影響もあるとのことです。
本章ではさらに、この唯言的な風潮が結びついた
非倫理的ビジネスについても語られます。
具体例として、後述する「モバイルプランナー」と呼ばれる
怪しげな学生ビジネスが取り上げられ、
言葉巧みに学生を誘う手口や、それを批判する大人たちの声が紹介されています。
劇的な成長神話:モバイルプランナーの光と影
第4章では、前章から引き続き「モバイルプランナー」という
具体的なビジネスケースが深掘りされます。
モバイルプランナーとは、一言で言えば
「携帯電話の料金プラン契約を代理で取って手数料を稼ぐ仕事」です。
大学生の間で「インターン」や「起業体験」のように喧伝され、
一時期メディアでも取り上げられました。
友人・家族など自分の人脈を使って契約を取るケースも多く、
手法的にはマルチ商法に近い側面があるため、
大人からは批判的に見られがちな仕事です。
しかし一方で、営業スキルや人脈作りなど
「成長できる」「稼げる」という触れ込みに惹かれて取り組む学生も少なくありません。
著者はこの現象を通じて、「成長神話」への疑問を投げかけます。
現代の就活市場では「学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)」として
インターンや起業経験、ボランティアなど
何かしら目に見える成果を求められる風潮があります。
本章では、「成長」という言葉ばかりがもてはやされて実態が伴わないケースや、
企業側が安易に「成長できます」「自己研鑽できます」と謳って
学生を囲い込む構図が批判されています。
レビュアーによれば、著者は「成長」を安易にありがたがる
企業やセミナー講師、就活生に対し
「それは具体的に何を指すのか?『成長した』という自己満足に過ぎないのでは?」と
冷静な視点を向けているとのことです。
要は、「成長」という言葉もまた唯言的に独り歩きしていないか、
本質的な学びや能力向上と切り離されて流行語化していないかを問うています。
モバイルプランナーの例では、違法ではないものの
リスクや友人関係の悪用と紙一重のビジネスに学生を引き込む企業と、
それに飛びつく学生側双方の問題を提示し、
「一概に善悪を決められないグレーな領域」に踏み込んだ議論がなされています。
著者は明確な答えを断定はしませんが、
「学生の不安や焦りにつけ込む大人社会の構図」が見て取れると述べています。
ブラック企業は消えたが…:「不安世代」の登場
第5章「消えるブラック、消えない不安」では、
舞台を就職後の職場に移し、Z世代の若手社員たちについて論じます。
ここでクローズアップされるのは、近年の職場環境の変化と若者の離職理由です。
かつて「ブラック企業」が社会問題になりましたが、
コンプライアンス強化やハラスメント対策の流れで、
過剰な長時間労働やパワハラは徐々に是正されつつあります。
結果、最近では「上司が優しすぎて厳しく怒られたことがない」環境で
育った若者も多いようです。
一見良いことのようですが、著者は皮肉な現象を指摘します。
それは「不満型ではなく不安型の離職」が増えているのではないかという点です。
例えば本章に登場するケースとして、ある新入社員が朝寝坊して出社が遅れた際、
上司は「午後から来ればいいよ」と優しく許してくれた。
すると本人はかえって「こんなゆるい職場で自分は成長できるのだろうか?」と不安になり、
「他社や他部署で通用しない人間になるのでは」と悩み始め、
結局「居心地は悪くないが不安だから辞める」という決断に至ってしまうというのです。
これは職場が厳しすぎて嫌になる昔の離職パターンとは真逆で、
「優しすぎて不安になる」という一種の贅沢病にも映ります。
しかし著者はこの背景にこそ重要なポイントがあると説きます。
それは、学校でも職場でも「怒らない方がマシ」という風潮が
20年かけて社会に浸透し、若者たちはそれを当たり前とする中で育ったという事実です。
コンプライアンスや炎上リスクを恐れるあまり
大人たちが叱責を封印した結果、若者は怒られ耐性がつかないまま社会に出る。
実際、「最近の若手はすぐ辞めるし打たれ弱い」と嘆く上司世代も多いですが、
それは若者のせいではなく大人側が“怒らなくなった”ことの副産物だと著者は分析します。
そしてもう一つ、本章で議論されるのが「○○ガチャ」という他責的な物の見方です。
親ガチャ、上司ガチャ、配属ガチャなど
世の中には自分ではコントロールできない運不運があります。
Z世代の間ではそれを「ガチャになぜ当たらないのか」と嘆く言い回しが流行りました。
これは自己責任論への反動として生まれた考え方とも言われます。
しかし著者は冷静に、「いくら嘆いても親ガチャも配属ガチャも引き直しはできない」こと、
さらに「嘆いている人には当たりが来ても気づけない」と手厳しく指摘します。
運任せと割り切って努力を放棄してしまえば、
せっかく巡ってきたチャンスすら認識できないという厳しい現実です。
つまり、不安や不満をただ環境のせいにするのではなく、
自分がどうそれに向き合うかが重要だと本章は示唆しています。
Z世代は社会の鏡:我々に何ができるのか
最終章(第6章)では、以上の議論を踏まえ
「われわれに何ができるのか」が語られます。
著者はまず、「Z世代を観察することで我々の社会の在り方と変化を展望しよう」という
本書の狙いを再確認します。
そして結論として、Z世代とは社会の構造を写し取った存在であると述べています。
彼ら若者が見せる極端にも思える言動
例えば前述の「怒らない社会」や「コスパ至上主義」「不安ビジネスへの過剰反応」は、
実は若者だけが特別に異質なのではなく、
社会全体が既にそうなっている姿をいち早く体現したものに過ぎないというのです。
Z世代はまさに炭鉱のカナリアのように
社会の変化に敏感で影響を受けやすい存在であり、
その行動を見れば今の世の中の問題点が浮き彫りになる。
だからこそ、彼らを単に「理解できない他人」と突き放すのではなく、
自分たちと地続きの存在として捉え直すことが大切だと著者は説きます。
では具体的に世代間の溝をどう埋め、協調していけばよいのか。
本書は「Z世代とうまくやっていく方法」として興味深い提言も述べています。
それは、「同じ推しを持つことでも、一緒にYouTubeを見ることでも、
テーマパークに行くことでもない」と一旦否定した上で、
「社会の中で自分たちの間に共通する構造があると認識し、
どう生きていくかを共に考えること」だと言うのです。
つまり表面的に若者文化に迎合するのではなく、
お互いの立場の違いを越えて内在する課題を共有し、
解決策を模索する対話が必要だというメッセージです。
著者はさらに、上司世代へのアドバイスとして
「若者の内面に強引に踏み込んで距離を縮めようとするのではなく、
大人自身が自己開示し、キャリアを通じて得た余裕や自信を示すこと」の重要性を述べています。
大人が希望ある未来像を見せられれば、
若者の不安も自然と和らぐはずだという指摘は示唆に富みます。
こうした提言は押し付けがましくなく、
具体的なアドバイスや考え方がいくつも紹介されています。
中でも「もっと肩の力を抜いていい」
「◯◯が無くてもガチで危機感を持たなくていい」といったメッセージは、
不安に駆られがちなZ世代本人にも届くエールとなっています。
著者自身大学教員として、知識や教育によって
そうした“揺るぎない自信”や“余裕”を身につけることが大切だと説いており、
その言葉は非常に力強く感じられます。
総じて本書は、若者世代と大人世代の双方にとって
今の社会を考える鏡のような役割を果たし、
単なる世代論に留まらない深みを持った内容と言えます。
最後に
ここまで本書について紹介してきました。
Z世代という一見ミステリアスな存在を解説しつつ、
実はそこに我々自身の姿をも映し出す良書です。
コミカルな語り口で読ませながらも本質を突く指摘が随所にあり、
若い世代とのコミュニケーションに悩む人や
現代社会の行方に不安を感じる人にとって、
多くの発見と安心感を与えてくれます。
本書が気になる方は、是非手に取ってみてください!
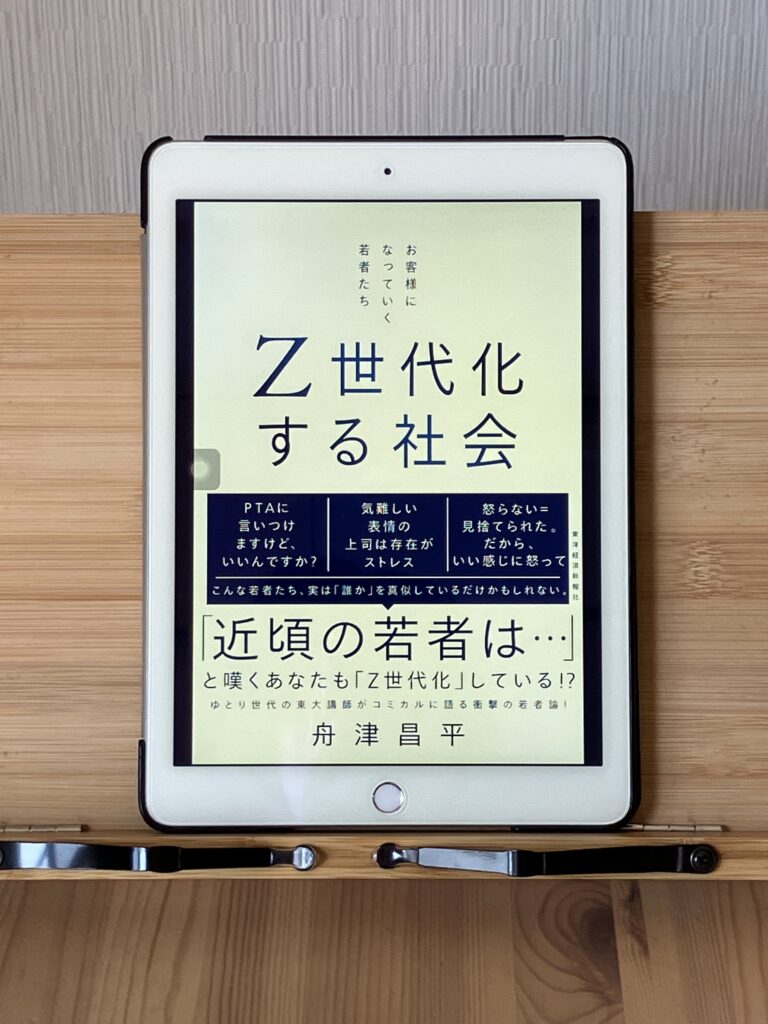
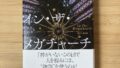

コメント