こんにちは!しょーてぃーです!
今回は、夏川草介さんの『エピクロスの処方箋』について紹介をしていきます!
『エピクロスの処方箋』について
この記事でわかること
- 『エピクロスの処方箋』の概要と、作品が見つめるテーマ
- 前半までのあらすじ(結末は触れません)
- 感想(テーマ/人物(語り)/読後感)と、刺さりそうな人の目安
本書の概要
『エピクロスの処方箋』は、京都の地域病院で働く内科医・雄町哲郎(通称マチ先生)が、治らない病や避けられない死を前に、「医療にできること」「人が人を救うとは何か」を問い直す物語です。
前作『スピノザの診察室』で描かれた穏やかな日常に、大学病院の症例と権力構造という“外の世界”が流れ込み、医師としての腕と、人としての覚悟が同時に試されていきます。秋から冬へ季節が移り、患者や家族、同僚医師、甥の龍之介との会話を通して、幸福と快楽、孤独、そして「第三の道」という視点が少しずつ立ち上がっていきます。
出版社は水鈴社、発売日は2025年9月29日。章立ては第一話「錦秋」/第二話「冬至考」/第三話「百鬼夜行」/第四話「初弘法」の四つです。2026年本屋大賞ノミネート作で、大賞発表は2026年4月9日予定とされています。
本書をオススメしたい人
- 家族の介護や看取りが、どこか他人事ではなくなってきた人(「治す」以外の医療の姿を知りたい人)
- 仕事やキャリアの“正解”が見えなくなった人(名声・評価と、目の前の生活のあいだで揺れている人)
- 哲学を「難しい理論」ではなく「日常で人を傷つけずに生きるための道具」として味わってみたい人
正直、あまり向いていない人
- 奇跡や逆転で一気に盛り上がる医療ドラマの読後感を求めている人
- 哲学の解説が前面に出る読み味を期待している人(物語の中でじわっと効いてくるタイプです)
- 重い題材を読むとき、息継ぎの描写があっても気持ちが追いつきにくい人
『エピクロスの処方箋』のあらすじ
あらすじ(ネタバレ控えめ・前半)
本作は四つの章で、京都の秋から冬へと時間が流れていきます。軸にいるのは、地域病院(原田病院)で働く内科医・雄町哲郎――通称「マチ先生」です。
マチ先生は、かつて大学病院で内視鏡治療のスペシャリストとして将来を嘱望されながら、妹を病で失い、ひとり残された甥の龍之介と暮らすために“町の病院”へ移っています。栄光の舞台でもあった大学病院は、価値観が衝突し、去ることになった場所でもあります。
第一話「錦秋」は、紅葉のなか訪問診療に向かうところから始まります。洋食屋の主人・田畑元之助の家で、寝たきりで難病の妻・光恵は回復が望めない状況です。元之助は「呼んでどうする、治してくれるわけでもない」と突き放しますが、マチ先生は“効く・効かない”だけで関係を閉じず、返事が返らない患者にも声をかけ続けます。
その頃、大学准教授の花垣がマチ先生の腕前を頼り、難しい症例の相談を持ち込みます。ただ、その患者は82歳の老人で、しかも大学病院の“絶対権力者”飛良泉寅彦教授の父親でした。訪問診療の静けさと、医局の政治のざわめきが交互に迫り、マチ先生は「あの世界に再び足を踏み入れるのか」という選択に揺れていきます。
この作品はどんな読書体験か
医療と幸福のあいだを、静かに行ったり来たりする読書体験だと思います。「治す」だけでは届かない場所に光を当てながら、派手さよりも心の平静に寄り添ってくる感じがありました。読みながら、こちらの呼吸も少し整っていくような場面があるのが、正直ありがたかったです。
『エピクロスの処方箋』の感想
感想①:テーマ
この作品が何度も触れてくるのは、「孤独にしない」ことの意味だと感じました。病気が治るかどうかの前に、人が孤独からどれだけ距離を取れるか。そこに医療がどう関われるのかを、押しつけずに問い直していく印象があります。
また、幸福と快楽を混同しないこと、快楽の本質を「精神の安定」と捉え直す視点が、物語の奥でじわっと効いてきます。派手な勝利や興奮より、心が揺れすぎない状態を大事にする考え方って、今の自分にも必要かも…と思わされました。
感想②:人物(語り)
マチ先生は、万能のヒーローというより、限界を前提にしながら人に向き合おうとする医師として描かれていると思います。冒頭の訪問診療で、返事が返らない患者にも自然に声をかけ続ける姿は、医学的な効果というより“場の空気”を守っているように見えました。
そして、大学病院の症例や権力構造という“外の世界”が流れ込むことで、腕だけじゃなく覚悟も試される。ここが読んでいてピリッとします。名声や肩書きより、目の前の人を孤独にしないことこそ仕事だ、という返しも印象に残りました。
感想③:読後感
題材は厳しいのに、読後に残るのは悲壮感だけではなく、静かな肯定感に近い温度でした。京都の景色や和菓子の描写が“息継ぎ”として挟まって、命の話の重さを日常の手触りに戻してくれる感じがあるんですよね。
読了後、次の季節へ視線を残すような余韻が残るのも特徴だと思います。ああ、終わった…というより、「じゃあ自分はどうする?」と、そっと背中を押される感覚に近いかもしれません。
この作品が投げかける問い
もし「治す」ことだけでは救いきれない場面があるなら、私たちは何を手渡せるんだろう。心に悩みがないこと、肉体に苦痛がないことに加えて、「孤独ではないこと」を重ねたい――その視点は、医療だけじゃなく、日々の働き方や人付き合いにも静かに刺さってきます。あなたは今、誰か(あるいは自分)を孤独にしないために、何か小さくできているでしょうか。
最後に
『エピクロスの処方箋』は、医療の現実を見つめながら、「人生の終わり方から、今日の生き方を考え直す」きっかけをくれる1冊だと思います。在宅診療の静けさと、大学病院の政治のざわめきが交互に訪れ、そこでマチ先生の「第三の道」が少しずつ立ち上がっていく流れが印象的でした。
医療小説が好きな方は、他の医療小説の記事もぜひ読んでみてください。
気になった方は、京都の季節と会話の温度を確かめるつもりで、ぜひ『エピクロスの処方箋』を手に取って読んでみてください。
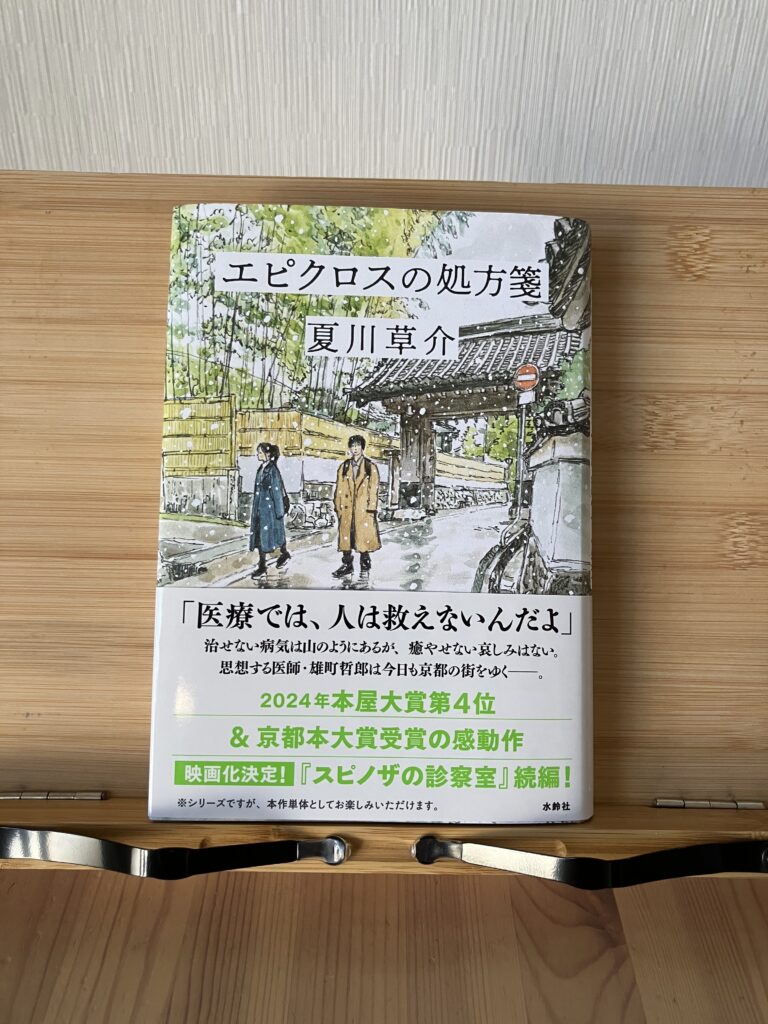

コメント