こんにちは!しょーてぃーです!
今回は、佐藤優さんの
『メンタルの強化書』について紹介をしていきます!
『メンタルの強化書』について
本書の概要
本書はひとことで言うと
「負けない・折れない・疲れない」心の鍛え方を教えてくれる1冊です。
本書をオススメしたい人
•職場のプレッシャーで「もう心が折れそう」と感じている人
•激しい競争環境でメンタルの強化策を求めている人
•他人を蹴落とすのではなく、品格を保って仕事で成果を出したいと考える人
本書は、元外務省主任分析官で作家の佐藤優氏によるビジネス書で、
ストレスフルな現代社会でメンタルを強化する方法を説いたものです。
著者は、急速に進む新自由主義的な競争社会によって
多くのビジネスパーソンが常に競争圧力にさらされ、
心の不調を訴える人が激増していると指摘します。
弱肉強食の時代では、他人を押しのけてでも生き残ろうとする
図々しい「下品な人」だけが勝ち残り、
繊細で優しい人ほど心が折れてしまうと著者は述べています。
こうした状況では従来の心構えでは自分のメンタルや品格を守りきれないため、
本書では品格を失わずに心を守り抜く方法を提案しています。
過酷な競争に負けず、心が折れず、
そして疲弊もしないで働き続けるための具体的な知恵が、本書には詰め込まれています。
『メンタルの強化書』のまとめ
現代社会は激しい競争と急激な変化にさらされ、心の健康が脅かされています。
著者の佐藤氏は、日本社会が新自由主義化した結果、
ビジネスパーソンが常に競争に追われるようになり、
そのプレッシャーからメンタル不調に陥る人が増えていると分析します。
競争に勝ち残るのは「自分勝手で図々しい下品な人」ばかりで、
心優しい人ほど心が折れてしまう現状に、強い危機感を示しています。
また、著者はこの異常な世界と距離を置いて生きる姿勢も必要だと説きます。
周囲の理不尽な状況に飲み込まれないようにすることも、
自分の心を守る上で重要だという指摘です。
硬いものはいつか折れる。柔らかさこそ本当の強さ という言葉の通り、
本当に強いメンタルとはしなやかで柔軟なものだと説いています。
著者自身、外務省や特捜検察といった巨大組織にも屈せず心を守り抜いた経験を持ち、
その知見を本書で余すところなく伝授しています。
メンタル強化の基本方針として、
本書は「自分の内面」と「自分を取り巻く環境」の双方からアプローチする大切さを強調します。
心が折れそうなとき、その原因が内面的なものか環境によるものかを見極め、
それぞれに対処する必要があると説きます。
また、強くしなやかな心を作るには自分自身の考え方・心構えを変えると同時に、
心が折れにくい環境を整えることが肝要だと指摘します。
この「内面」と「環境」という二本柱でメンタルを鍛える視点が、
本書全体を通じた軸になっています。
前のめり社会への警鐘:情報との向き合い方
第2章では、何事にも“前のめり”に突き進む生き方を見直すよう促しています。
現代人は不安から情報に飛びつきがちですが、
著者はむやみに新しい情報に飛びつくとミスリードされる危険を指摘します。
一度立ち止まり、「なぜこの情報が出てきたのか?」「誰が発信しているのか?」
「その目的は何か?」といった視点で冷静に見極めることが大事です。
そして、「人より半歩遅れて進む」くらいがちょうど良いとも述べています。
少し引いた位置から物事を見ることで
全体像が見え、判断のための時間を稼げるからです。
焦って先頭を走るのではなく、半歩引いてタイミングを計ることで、
情報過多な時代に振り回されずに済むというアドバイスです。
さらに著者は、自己責任論や過度な競争意識にも疑問を投げかけています。
競争社会では「努力しない者が悪い」という風潮がありますが、
本来「自己責任」という考え方は欧米にはなく、
何でも個人の責任に帰すのは行き過ぎだと指摘します。
人は共同体の一員であり、お互いに支え合う存在なのに、
現代は個を強調しすぎて孤独に陥っているというのです。
この章を通じて、情報や競争に踊らされず、
自分のペースと価値観を見失わない大切さが語られています。
折れない・疲れない働き方改革
第3章では、無理をしない働き方を追求する具体的な知恵が紹介されています。
例えば、著者は「明日できることは今日やらない」という逆転の発想を提案します。
これは怠惰を推奨するのではなく、限られたエネルギーを無駄遣いしないためです。
やる気が出ないときは、無理に仕事を進めるよりもまず机や部屋の片付けをする など、
環境を整えて気持ちを切り替えるようアドバイスしています。
また、「仕事ができない人は単純な仕事を複雑に、できる人は複雑な仕事を単純にする」という指摘も印象的です。
仕事の目的とやるべきことを明確にし、
タスクをシンプル化することで余計な負荷を減らせるということです 。
著者は自分を守るために環境をできるだけシンプルにする重要性も強調します。
身の周りの環境を整え、人間関係も整理することでストレス要因を減らし、
「心が折れにくい」状況を作ることができます 。
さらに、常に最悪の事態を想定しておけば、
いざというときに慌てずに済むとも述べられています。
心の備えをしておくことで、不測の事態にも冷静に対応できるというわけです。
心が折れそうなときの対処法
第4章では、心が折れてしまいそうなとき、あるいは折れてしまった後の対処法が語られます。
まず大切なのは「とにかく休むこと」です。
心が限界に近いと感じたら、勇気を持って一旦休職したり休暇を取ったりして、
自分を守ることを最優先にすべきだと強調されています 。
そして、もし復帰する際も、いきなり全力で以前と同じように頑張るのではなく、
以前の6割程度の力からで十分だと述べられています。
心の回復には時間がかかるので、無理せず徐々にペースを上げればいいのです。
また、現代ではスマートフォンやSNSの普及により、
心が休まる暇がないことも問題視しています。
常時オン状態の情報社会から意識的に距離を置き、
オフの時間を作ることがメンタルヘルスには不可欠です。
さらに睡眠の質の重要性にも触れられ、
睡眠不足や質の低下がメンタルに悪影響を及ぼすため、
しっかり休む習慣を持つよう勧めています。
心を立て直す具体的な方法としては、小さな目標を仕事以外に作ることも提案されています。
趣味や運動など、仕事と関係ない分野で達成感を得られる目標を持つことで、
成功体験や充実感を積み重ねて心の支えにする狙いがあります。
そして意外に見落としがちなのが怒りのコントロールです。
イライラしている時こそ静かに落ち着いた行動を取り、
瞑想や祈りを活用して心を鎮めるといったテクニックが紹介されています。
ゆったりとした音楽を聴いたり、美しい風景や芸術を鑑賞したり、
意識的に笑顔を作ることで感情を落ち着かせる方法も有効だといいます。
怒りや不安といった感情に振り回されず、
自分で心の状態を整える術を身につけることがメンタル強化には欠かせません。
つながりと日本的な「美意識」の力
最後の第5章では、人とのつながりや日本的な価値観が
メンタルの支えになることが語られます。
著者は「どれだけ多くのつながりを持てるかが、厳しい時代を生き抜く上で不可欠」だと述べ、
人とのネットワークこそ最大のセーフティネットであると強調します。
人生のセーフティネットを築く上で必要なものとして、
(1)お金(自助)、(2)公的制度(公助)、(3)仲間や共同体(共助)の三つを挙げていますが、
中でもこれからは共助の比重が高くなると説きます。
かつて日本では会社が家族的なコミュニティの代役を担ってきましたが、
現代ではそうした会社コミュニティの機能も薄れつつあります。
だからこそ、自分たちで新たなコミュニティを作り、
仲間同士で支え合うことがこれまで以上に重要になってきます。
著者は具体例として、独身者同士・子育て中の夫婦同士が集まって協力し合うような
アソシエーションの形を提案しています。
こうした共助のネットワークこそが、いざというときの心の支えになると述べています。
さらに佐藤氏は、日本人の伝統的な美意識にも言及します。
哲学者・九鬼周造の著書『「いき」の構造』に登場する
「媚態(びたい)」「意気地(いきじ)」「諦め」という概念を引き合いに出し、
これらがこれからの時代をしなやかかつ強かに生き抜く鍵になると述べています。
ここでいう「媚態」は他者にこびること、
「意気地」は自分の誇りや意地、「諦め」は物事を受け流す達観といったニュアンスです。
著者自身、過酷な逆境を生き延びて再び社会で活躍できたのは、
この「意気地(いきじ)」を持ち続けていたおかげだと振り返ります。
逆に、自分の限界を知らない人間は傲慢になるとも警鐘を鳴らし、
困難な時代だからこそ一度日本人の美意識の核に立ち戻り、
自分たちなりの物語を作って人と結びついていくことが必要だと説いています。
最後に
ここまで本書について紹介してきました。
厳しい時代を折れず・負けず・疲れずに生き抜くための知恵が凝縮された一冊です。
周囲の環境に流されず、自分らしい品格を保ちながら、
したたかに生きていくヒントが詰まっていました!
本書が気になる方は、是非手に取ってみてください!
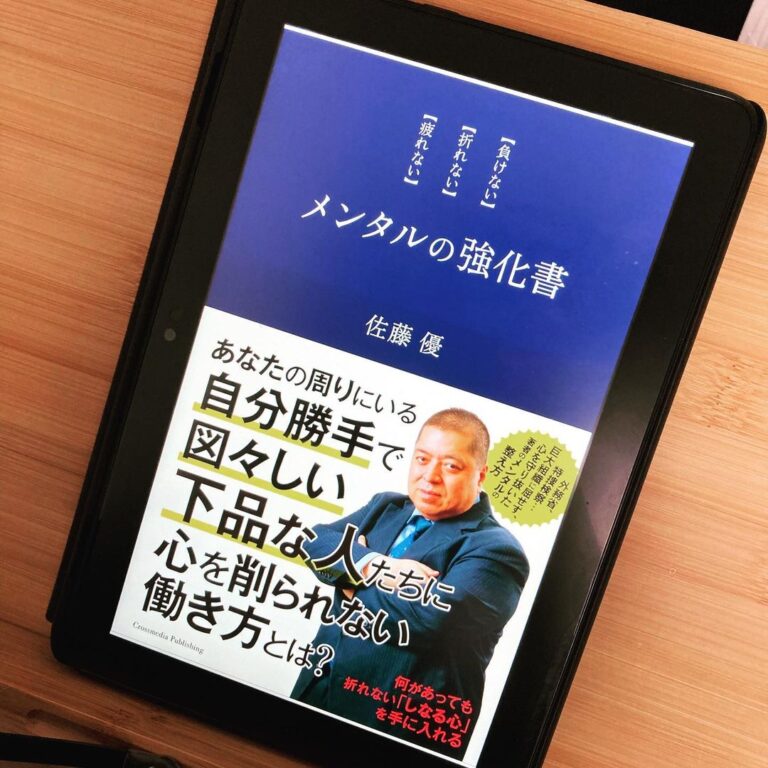

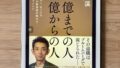
コメント