こんにちは!しょーてぃーです!
今回は、恩田 陸さんの
『spring』について紹介をしていきます!
『spring』について
本書の概要
本書はひとことで言うと
一人の天才をめぐって交差する、芸術と人生の物語です。
本書をオススメしたい人
・芸術や舞台表現に興味がある人
・語ること・記憶することに関心がある人
・多層的な語りや群像劇が好きな人
本作は、天才バレエダンサー・萬春(よろず・はる)の人生と芸術を、
多角的な語りで描いた重厚な群像劇です。
物語は萬春の周囲にいたライバル、叔父、作曲家、
そして萬春本人の視点から語られ、
彼の「存在」がさまざまな角度から浮き彫りにされていきます。
バレエという身体芸術を通じて、人はなぜ表現するのか、
そして誰かを「語る」とはどういうことなのかが繊細に描かれます。
芸術とは、才能とは、そして変わり続けることの意味を問いかける静かで熱い物語です。
『spring』のあらすじ
あらすじの概要
自らの名に無数の季節を抱く無二の舞踊家にして
振付家・萬(よろず)春(はる)。
少年は八歳でバレエに出会い、十五歳で海を渡った。
同時代に巡り合う、踊る者 作る者 見る者 奏でる者――
それぞれの情熱がぶつかりあい、
交錯する中で彼の肖像が浮かび上がっていく。
彼は求める。舞台の神を。憎しみと錯覚するほどに。
一人の天才をめぐる傑作長編小説。
spring より
踊り続けた男の四重奏
物語の中心人物は、世界的に著名な天才バレエダンサー兼振付家・萬春(よろず・はる)。
彼の名前が示す通り、「春」のように生命力に満ち、
どこか人間離れした存在感を持つこの青年は、
若くして世界にその名を知られる伝説的なアーティストとなります。
小説は彼の人生を一本の直線で描くのではなく、
「萬春という人間を巡る複数の語り手たちの証言」によって構成されています。
全4章からなるそれぞれのパートは、
萬春に関わった異なる人物の視点で語られ、時間軸も交錯しながら進んでいきます。
第1章:ライバル・美潮の視点
第1章の語り手は、萬春の幼なじみであり、
唯一といっていいライバル・美潮(みしお)。
彼は萬春と同じ時期にバレエ界に入り、
その才能に嫉妬しながらも、深い敬意を抱いています。
二人の関係は友情というには距離があり、
美潮にとって萬春は、到達できない高みにいる者でありながらも、
自分の踊りの原点でもあります。
バレエ公演の裏側や、若き日のレッスン風景などが美潮の記憶を通して描かれ、
彼の視点から見える萬春の才能と孤独が浮かび上がります。
第2章:叔父・稔(みのる)の視点
第2章は萬春の母方の叔父である稔の視点で描かれます。
彼はかつてジャーナリズムの世界に身を置いていたが、
萬春の家族に近い距離で関わってきた人物です。
萬春の幼少期、家族との関係、
そして彼がなぜあれほどバレエにのめり込んでいったのか。
その原風景を見つめてきた語り手として、
萬春の根源的な「存在の謎」に迫るパートとなっています。
萬春の父は政治家で、母は元バレエダンサーという背景も明かされ、
彼が持つ血の中の矛盾や、芸術と支配の間で揺れ動く精神性が浮かび上がります。
彼の身体と精神、芸術への執着には、
決して「環境」だけでは説明できないものがあることが示されます。
第3章:音楽家・七瀬の視点
第3章では萬春と最も深く作品を共にした作曲家・七瀬が語り手です。
彼女は萬春とともに数々の舞台作品を作ってきたパートナーであり、
芸術家としての萬春の「表現欲」と「制御不能な創造衝動」に最も近い位置にいた存在です。
この章では、舞台制作の裏側、音楽と踊りがどう共鳴し合っていくか、
またときには衝突し、葛藤を生み出すかが細かく描かれます。
七瀬は萬春の天才性に圧倒されながらも、
自らの音楽でそれに応えようと苦悩し続けると同時に、
「一緒に作品を作っていくうちに、自分が萬春に“創られていた”のではないか」と
感じるようにもなっていきます。
第4章:萬春自身の視点
最終章は、ついに萬春本人の視点によって語られます。
これまで他者の証言の中で語られてきた彼が、
自身の言葉で、自らの芸術と人生、そして存在のあり方を語ることで、
物語は静かに核心へと向かっていきます。
彼の内面は意外なほど静謐で、理性的でありながら、どこか冷たくさえあります。
踊るとは何か、自分という身体はなぜ存在するのか、
観客は自分のどこに惹かれているのか、
彼はそれらの問いに対し、踊りという行為を通じて
答えを出し続けていたことを明かします。
萬春は最終的に、すべてを踊りに昇華させようとします。
「踊る」という身体表現が、言葉や理性、
思想すら超える領域にあると、彼は直感的に信じていました。
その視点から語られる舞台のラストシーンは、
読む者にも「芸術とは何か」という問いを突きつけます。
『spring』の感想
語られることで生き続ける、天才の肖像
本作は、「一人の天才が生きた軌跡」ではなく、
「一人の天才を通して照らし出された、他者の生き様と芸術の輪郭」です。
萬春という天才ダンサーを主人公に据えながらも、
彼を自らの言葉で語らせず、他者の視点から少しずつ立ち上がらせるという
「神話の生成過程」を描いた小説であり、
「人が他者をどう語り、どう憧れ、どう突き放すか」を静かに問い続ける作品でもあります。
「神話」は語る人によって形を変える
本作では、4人の語り手がそれぞれ異なる立場から萬春を語ります。
幼なじみ、家族、創作パートナー、そして本人。
読み進めるうちに気づかされるのは、
「同じ人物を語っているはずなのに、萬春の像が章ごとに全く違う顔を見せる」ということです。
たとえば第1章の美潮にとって、萬春は届かない頂点にいる存在であり、
どこか人間離れした畏敬の対象です。
第2章の叔父・稔から見れば、
彼はまだ輪郭のあやふやな少年でありながらも、すでに「何者か」でした。
その輪郭が明確に見えるのは、
芸術を共に創り上げた作曲家・七瀬の視点を経て、ようやく萬春の「内側」へ近づいていきます。
そして第4章で、初めて萬春自身の言葉によって語られるとき、
私たちは初めて「彼自身が、自分をどう見ていたか」を知ります。
これは、まさに芸術家の神格化がどう起こるかの過程そのものであり
天才はいつだって、他者の言葉によって神話化されます。
けれど、その実像は曖昧で、語る人の数だけ像があり
著者は、その「像の揺らぎ」を徹底的に描き出すことで、
単なる人物伝を超えた「芸術と語り」の小説を作り上げたと思います。
芸術は言葉にできるのか?という挑戦
バレエという身体芸術を題材にしながらも、
著者はそれを言葉で描ききるという難題に挑戦しています。
踊りの動き、音楽との絡み、舞台上の空気感。
どれも視覚と聴覚を通じて体感するものであり、本来、文字で完全に伝えるのは困難です。
しかし彼女は、「踊りの余韻」「観客の息を呑む気配」「踊る側の肉体のうねり」など、
見る者・作る者・踊る者それぞれの感覚を通じて、
読者の想像力を最大限に引き出します。
とりわけ、七瀬の章における「音楽と踊りの関係」の描写は圧巻で、
共創の難しさと美しさがこれほどまでに繊細に描かれた場面は稀だと感じました!
「変わらないために、変わり続ける」
作中、印象的なセリフの一つに、
七瀬の「変わらないために、変わり続けるしかない」という言葉があります。
これはまさに、本作の主題でもあります。
萬春は決して同じ踊りを繰り返さないです。
彼は毎回、自らの肉体を更新し、解体し、再構築し続けることで、自分の芸術を守っています。
そこには、「型を持たない型」があり、
「変わり続けること」によってしか保てない「不変」があります。
これは芸術だけでなく、人間関係や人生にも通じる真理だと感じました。
安定を求めれば、やがてそれは劣化に繋がります。
最後に
ここまで本書について紹介してきました。
ただの芸術小説でも、バレエに詳しい人のためだけの小説でもなく
才能と情熱の正体、人間の内に潜む衝動と、
それを他者がどう受け止めるかという普遍的なテーマが、重層的に描かれた作品でした!
本書が気になる方は
是非本書を手に取ってみてください!

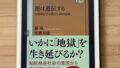
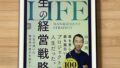
コメント