こんにちは!しょーてぃーです!
今回は、ハル・ハーシュフィールドさんの
『THINK FUTURE「未来」から逆算する生き方』について紹介をしていきます!
『THINK FUTURE「未来」から逆算する生き方』について
本書の概要
本書はひとことで言うと
先延ばしや挫折の原因を科学的に解明し、解決策を示す1冊です。
本書をオススメしたい人
- 目先の誘惑に負けてしまい、先延ばしにして後悔しがちな人
- 将来のために何かしなければと悩んでいる人
- 自分の習慣や考え方を改善したい人
本書は、未来の自分を私たちがどう捉え、なぜ時にないがしろにしてしまうのかを解明し、
そのギャップを埋める実践的方法を紹介する1冊です。
著者のハル・ハーシュフィールド氏は、UCLA経営大学院の心理学教授で、
将来の自己に関する研究で世界的に注目されています。
本書は「なぜ貯金やダイエットが続かないのか?」という身近な疑問から始まり、
人間が未来をどう認識し行動に移すかを科学的に分析しています。
「未来の自分を他人のように見てしまう心理」が
先延ばし癖や目先の欲求に負けてしまう原因だと指摘し、
未来の自分と現在の自分をつなげることで目標達成がしやすくなると、
多くの研究と実例を交えて解説しています。
さらに「未来の自分を視覚化する」
「未来志向の行動をとりやすくする環境づくり」など、
誰にでも実践できる具体策も豊富に紹介されています。
未来から逆算して行動する力を養うことで
人生の質を向上させることを目指した内容です。
『THINK FUTURE「未来」から逆算する生き方』のまとめ
未来の自分は「他人」?
人は将来の目標を立てても、いざ行動となると現在の快楽を優先しがちです。
それは心理的に「未来の自分」を
まるで他人のように捉えてしまう傾向があるからです。
ハーシュフィールド氏の研究では、
被験者が「将来の自分」を思い浮かべた時の脳の反応パターンが、
「他者のことを考えた時」に近いことがMRI実験で示されています。
言い換えれば、私たちにとって未来の自分は
現時点の自分とは別人に感じられており、
その“見知らぬ他人”のために努力するのは難しくなってしまいます。
加えて人間は本質的に自己中心的で
「今の自分の幸福」を優先する生き物ですから、
遠い未来のための行動は目の前の快楽との競争に負けやすいのです。
このため、「いつかやろう」と決めた
貯金や勉強、ダイエットが続かないという現象が起こります。
未来を無視してしまう3つの錯覚
本書では、私たちが未来の自分をなおざりにしてしまう原因を
「3つの脳内タイムトラベルのミス(思考の錯覚)」として整理しています。
現在に注目しすぎる
現在の状況や欲求は具体的で強く実感できますが、
将来のことは不確実で曖昧なため、どうしても目先の欲求を優先してしまいます。
たとえば「1年待てば10万円もらえるが、
今すぐなら9万9000円もらえる」という選択では、
多くの人が手数料で減額されても「今すぐ」のお金を選ぶ傾向があります。
時間的に近づくほど「すぐ手に入れたい」という気持ちが、強まる心理が働くからです。
うわべだけ未来を考える
将来について漠然と想像するだけで満足してしまい、具体策を取らないことです。
例えば「後になればやる気が出るだろう」と楽観して
面倒な作業を先延ばしにしても、いざその時になれば
結局同じように億劫に感じて実行に移せなくなります。
このように表面的な未来イメージに頼ると、
いつまで経っても意図した未来には辿り着けません。
未来が現在と同じだと勘違いする
将来の自分の状況や心境が、現在と大きく変わる可能性を無視してしまうことです。
ここには2つのバイアス(認知の偏り)が関係しています。
一つは「プロジェクションバイアス」で、
現在の自分の感情や欲求がそのまま未来も続くと考えてしまう癖です。
例えば空腹のまま買い物に行くと、先の食事の分まで必要以上に買い込んでしまうのは、
今の飢えた感覚を未来にも当てはめているからです。
もう一つは「歴史の終わりの幻想」で、
現在の自分の性格や好みはこの先も大きく変わらないだろうと信じてしまうことです。
しかし振り返れば誰しも過去から徐々に変化してきたはずなのに、
未来については「今のままだ」と錯覚しがちなのです。
未来の自分とつながるために
上記のような心理的ハードルを乗り越え、
未来の自分との関係を深めるにはどうすればよいでしょうか。
本書はそのポイントとして、以下3点の重要性を説いています。
- 望む将来の具体的な姿を鮮明に思い描くこと
- 未来の自分を遠い他人ではなく大切な存在として身近に感じること
- 現在の延長線上にとらわれず「未来は今とは違う自分になり得る」と認識すること
こうした視点を持つことで、未来を現実の延長として捉えられるようになり、
将来のために今何をすべきかが見えてきます。
では具体的な方法として、どんなアプローチが有効なのでしょうか。
まず「未来の自分を視覚化する」ことが効果的だといいます。
将来の自分の姿(例えば10年後、20年後の自分)をイメージできれば、
未来が現在の続きだと実感しやすくなります。
著者が紹介する研究では、自分の老けた姿をシミュレーション画像で見せられた人々は、
そうでない人に比べて将来に向けた貯蓄意欲が高まり、
健康への関心も増したという結果が得られています。
また、ケニアの農村で行われた調査では、
将来の自分を思い描くトレーニングを受けた女性たちが貯蓄額を伸ばし、
健康的な生活習慣を取り入れるようになった例もあります。
このように未来の自分の姿を具体化するだけでも、
現在の行動に良い変化が生まれるのです。
次に「時間を超えた手紙を書く」という方法も紹介されています。
未来の自分宛てに手紙を書く、あるいは逆に未来の自分になったつもりで
今の自分に手紙を書くことで、時間を超えた対話が生まれます。
実際、本書で紹介されているある教師の取り組みでは、
小学6年生に高校3年生の自分へ宛てた手紙を書かせ、
それを卒業間近に郵送で届けるというプロジェクトが行われました。
生徒たちは過去の自分が書いた手紙を読み、
自分の現在を振り返る機会を得ています。
その結果、多くの生徒が自身の今の姿勢を見直し、
当時描いていた夢に立ち返るようになったといいます。
未来の自分に手紙を書くことも、同様に自分の将来像を明確にし
現在の行動を方向づける助けとなります。
さらに「未来志向の行動を起こしやすくする環境づくり」も重要です。
人間は「面倒だな」と感じるとすぐ行動を後回しにしてしまうものです。
だからこそ、行動へのハードルをできるだけ下げる工夫が効果的だと本書は説きます。
例えばダイエットのために運動したいなら、
トレーニングウェアやシューズをいつでも手に取れる場所に出しておく。
勉強を習慣化したいなら、机の上に参考書を開いて置いておく。
こうするだけで「わざわざ準備する」手間が省け、すぐ行動に移しやすくなります。
このように仕掛けを用意しておけば、
未来の自分のための行動を自然と継続しやすくなるのです。
加えて、目標に向けた現在の行動を確実に継続するためには、
コミットメント装置と呼ばれる仕組みを活用するのも有効です。
誘惑に打ち克ち計画通りに進むために、次のような戦略が紹介されています。
- 目標達成に向けて自ら具体的な計画を立て、第三者に実行状況をチェックしてもらうこと。
- 計画の邪魔になるような選択肢(誘惑)をあらかじめ排除しておくこと。
- もし怠けてしまった場合に自分にペナルティ(罰則)が科されるルールを設定すること。
例えばダイエット中なら家の中のお菓子を処分しておき、
運動をサボったら友人に決められた額のお金を支払う、といった取り決めをするイメージです。
こうした前もっての「縛り」を入れることで、目先の快楽に流されにくくなり、
未来の利益のために現在の自分を律することが容易になります。
現在と未来のバランス
もっと先の未来を考えるほど、「どうして今我慢しなければならないのか」と感じてしまう
これは多くの人が抱く疑問です。
しかし本書では、将来のための犠牲と現在の幸福を両立させる視点として
「混合感情(複雑な感情)の受容」を提案しています。
ポジティブな感情とネガティブな感情を同時に味わうことで、
人はより深い充足感を得ることができるといいいます。
単純に楽しいことだけを追求するのではなく、苦労や不安の中にも小さな喜びや意味を見出す
そうした前向きさが、長期的には大きな幸福感につながります。
実際、辛さと楽しさが入り交じった複雑な感情がもたらす恩恵はすぐには実感できませんが、
時間をかけてじわじわと現れてくると指摘されています。
つまり、「未来のために今を我慢する」のではなく、
「未来のために投資している自分」に誇りや喜びを感じることが大切です。
現在の満足度と将来の利益はトレードオフではなく、
両立しうるものだと本書は教えてくれます。
最後に
ここまで本書について紹介してきました。
未来の自分との関係を見直すことで
人生をより良く変えていく方法を具体的に示してくれる1冊です。
日々の選択に迷ったとき、5年後や10年後の自分を思い浮かべて
「その自分が誇れる決断はどれだろう?」と考えてみるだけでも、
きっと行動の指針が見えてくると思いました!
本書が気になる方は、是非手に取ってみてください!
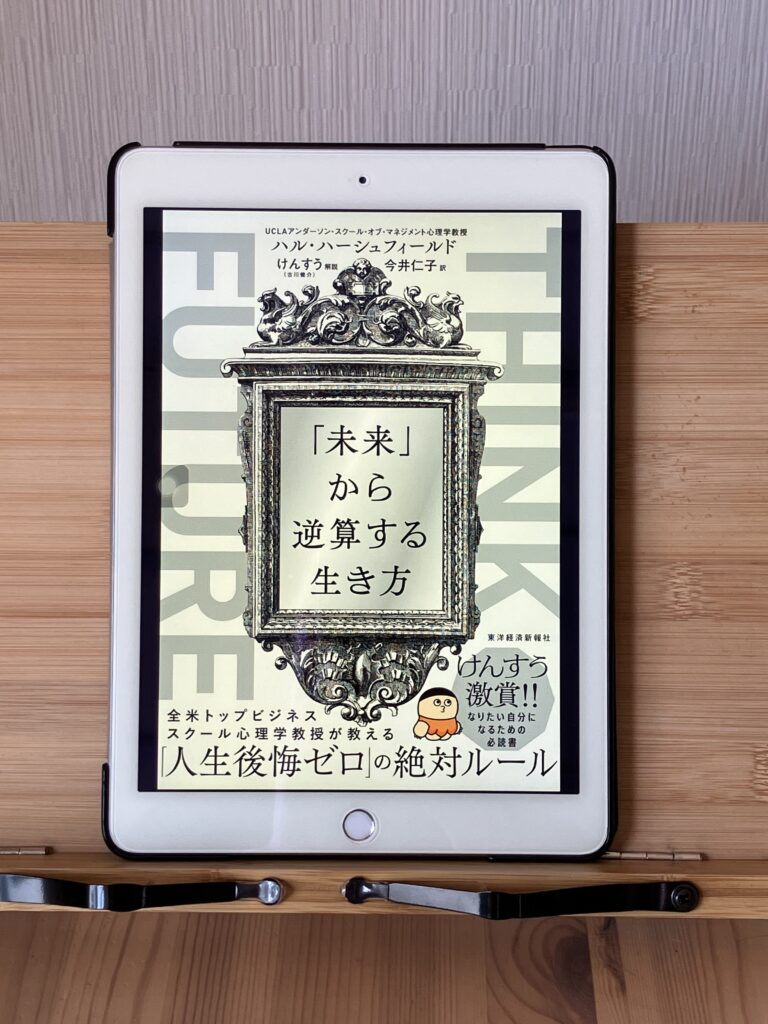

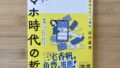
コメント