こんにちは!しょーてぃーです!
今回は、長倉 顕太さんの
『本を読む人はうまくいく』について紹介をしていきます!
『本を読む人はうまくいく』について
本書の概要
本書はひとことで言うと
忙しくても続けられる読書習慣の作り方が満載の1冊です。
本書をオススメしたい人
- 読書の効果を実感したい人
- 戦略的な読書術を身につけたい人
- 最近読書から遠ざかっている人
本書は、単なる読書テクニック本ではなく、読書という行為を通じて
人生のあらゆる悩みの根源となる「思考のOS」を更新するための指南書です。
伝説的編集者であり著者でもある長倉顕太氏が、自身の経験を交えながら、
読書の効能や習慣化の工夫、良書の選び方までを徹底解説しています。
長倉氏自身、1冊の本との出会いをきっかけに渡米し、
人生が大きく変わったと語るほど読書の力を実感した人物です。
本書の中で彼は「自分の能力の100倍の年収を稼いでいると思っている」とまで述べ、
その理由は「本のおかげ」だと断言しています。
本書を読めば、読書が仕事・人間関係・お金といったあらゆる分野にプラスの影響を与え、
読む人と読まない人の間に「圧倒的な差」が生まれる理由が記されています。
さらに、読書から得た知識を現実の成果に結びつける具体策として、
「7つの目的別・本の選び方」や「忙しい人でも無理なく続けられる22の読書習慣プラン」といった
実践的アドバイスが豊富に盛り込まれています。
『本を読む人はうまくいく』のまとめ
第1章 なぜ、本を読む人はうまくいくのか?
長倉氏はまず、「読書」は人生を有利に進めるための最強の戦略であり、
読書こそが人生を変える力になると主張します。
多くの人の人生が行き詰まるのは、
自分の現在地や進むべき道を示す「地図」を持っていないからだと言います。
そして読書はその人生の「地図」を手に入れる最も確実で安価な方法だと説くのです。
1冊の本には、著者が何年もかけて得た知見や経験が凝縮されており、
著者によれば「1冊を書くのに100冊分のインプットが必要」だとも言われます。
それだけの知識を数千円で手に入れられる読書は、
非常にコストパフォーマンスが高い自己投資です。
実際、本書では「読書をすればするほど、リターンが蓄積されていく」と述べられており、
読書は「100%以上のリターンが保証された投資」だと強調されています。
長倉氏自身、読書によって得た知識のおかげで
「自分の能力以上の成果を出せている」と語り、
読書が人生にもたらす恩恵の大きさを身をもって示しています。
さらに著者は、現代を生き抜く上で鍵となる能力として「環境適応能力」を挙げます。
時代の変化や未知の状況に適応する力は、
様々な人生や思考プロセスを疑似体験できる読書によって鍛えられるからです。
言い換えれば、本を読むことは他人の人生を擬似体験し、
自分の引き出しを増やす行為だといえます。
その結果、予測不能な世の中でも柔軟に対応し、チャンスを掴み取る力が養われるのです。
また、本書の冒頭では「学生時代に勉強しなかった知識不足を
今から挽回するにはどうすれば…」と悩む人にこそ
本書が大きな気づきを与えると述べられています。
読むか読まないかで人生に大きな差が生まれるというメッセージは、
本書全体を貫くテーマになっています。
第2章 なぜ、読書をすると頭が良くなるのか?
読書が「頭が良くなる」と言われるのは、単に知識量が増えるからだけではありません。
本書では、読書によって物事の本質を見抜く思考力、
特に「抽象化思考」が鍛えられると解説されています。
例えば、複数のビジネス書に書かれた成功事例から
共通する原則を読み取るような読書を重ねることで、
表面的な情報に惑わされない本質的なパターン認識力が養われます。
これがどんな問題にも応用できる汎用的な思考力につながり、
結果的に「頭が良い」と言われるような判断力・解決力を発揮できるようになるのです。
また、本書は「知れば知るほど、さらに新しいことを知りたくなる」という
好循環にも触れています。
読書によって知識が増えるほど、逆に自分の無知に気づき
もっと学びたくなるという現象です。
この知的好奇心のスパイラルによって、
読書を重ねるほどさらに頭脳が活性化し、学習意欲が高まっていきます。
著者は、読書で得た知識は必ずしもすぐ結果に直結しなくても、
「読めば読むほど内側に資産が積み上がっていく」ものだと表現しています。
蓄積された知的資産が土台となり、いざというときに創造的なアイデアや
的確な意思決定を引き出せるようになるのです。
加えて、本書では「読んでもすぐ内容を忘れてしまう」という悩みに
応える工夫も紹介されています。
単に読むだけでなくアウトプットや記憶に定着させる読み方についても触れられており、
読書の効果を最大化する具体的なテクニックが示されています。
つまり、本を読んで終わりにせず、得た知識を
自分のものにして活かす方法まで網羅されているのです。
第3章 なぜ、本を読むと頭が柔らかくなるのか?
本を読むことで「頭が柔らかくなる」とは、
言い換えれば発想力や視野が広がるということです。
本書によれば、読書は自分一人では得られない
多様な視点を与えてくれる最も手軽な方法だといいます。
私たちは往々にして自分の経験や業界の常識に囚われてしまいがちですが、
例えば歴史小説を読めば現代とは異なる価値観や社会構造に触れることができます。
その体験によって「自分の当たり前」が絶対ではないと気づき、
凝り固まった思い込みが打ち砕かれるのです。
著者は、普段自分が手に取らないジャンルの本にこそ
新しい発想のヒントが隠れていると強調します。
マンネリ化した仕事に行き詰まっているとき、
意外な分野の書物からブレイクスルーの種が見つかることもあります。
読書によって得た未知の視点が固定観念を崩し、柔軟な思考へと導いてくれるのです。
その結果、「今までこうだと思っていたこと」が覆され、
新たなアイデアやアプローチが次々と生まれるようになります。
さらに、多くの本に触れることで、
自分の価値観の軸が明確になるとも本書は述べています。
様々な人の人生や考え方を知るうちに、自分は何を大事にしたいのか、
どんな生き方に共感するのかが見えてくるからです。
例えば、複数の起業家の自伝を読むと成功の形が一つではないと分かり、
自分なりのキャリア観を見直すきっかけになります。
そうして「他人と比べて迷う」ことが減り、
自分の意思決定の軸が定まるため、優柔不断さから脱却できるのです。
頭が柔らかくなるというのは、単に発想が豊かになるだけでなく、
自分の考え方の土台がしなやかに強くなることでもあります。
第4章 なぜ、本を読む人は人間関係も豊かなのか?
読書は対人関係にも大きな効果をもたらします。
本書では特に文学作品、小説を読むことの効用に触れ、
物語を読むことで他者の感情を読み取る力(感情認識能力)が高まると指摘しています。
小説の中で登場人物の心の機微や複雑な感情の動きを追体験することで、
現実でも他人の気持ちを想像し共感する力が養われるのです。
実際、ある研究ではフィクション小説を読んだ人は
ノンフィクションだけを読んだ人に比べて、
他者の感情を読み取るテストの成績が向上したとの結果も紹介されています。
これは物語への感情移入が人の脳の共感に関わる領域を
活性化させるからだとされています。
要するに、小説を読むことで得た「人の気持ちを察する力」が
現実のコミュニケーションにも活きてくるということです。
職場での対人関係が苦手な人でも、物語世界で培った想像力によって
相手の立場に立ったコミュニケーションがとりやすくなり、
人間関係が円滑になる効果が期待できます。
さらに、読書によって得た幅広い知識は人との繋がりを豊かにします。
著者は多くの成功者と接してきた中で気付いた共通点として
「例外なく彼らは読書家だった」と述べています。
知識が豊富な人は周囲から「有益な情報をくれる存在」として頼りにされやすく、
結果として良質な人間関係や信頼を築くことができるのです。
本書でも、現代の「人生100年時代」を充実させる社会関係資本(人脈や信頼)は
読書によってこそ培われると強調されています。
知的な会話ができる人、面白い話題を提供できる人には自然と人が集まります。
加えて、読書習慣は言語化能力(自分の考えを的確に言葉にする力)を高めてくれます。
多くの良質な文章に触れることで語彙が増え、
論理的で分かりやすい表現方法が身についていきます。
その結果、自分の思考やアイデアを他人に伝えるコミュニケーション能力が向上します。.
ビジネスの場面でも、報告・提案を明快な言葉で伝えられれば説得力が増し、
チームとの意思疎通もスムーズになります。
このように、読書によって培われる共感力や知識、言葉の力は
人間関係全般を豊かにする土台となるのです。
第5章 うまくいく人はどうやって本を選んでいるのか?
「本を読むこと」が重要なのは言うまでもありませんが、
本書はさらに一歩踏み込んで、「どの本を読むか」を戦略的に選ぶことの大切さを説いています。
著者によれば、成功する人たちは単にベストセラーを手あたり次第読むのではなく、
自分の目的や課題に応じて読む本を厳選しているというのです。
読書を真の自己投資にするには、今の自分にとって
必要な知識・刺激を与えてくれる本を選ぶことがポイントになります。
本書の第5章では、そのための具体的な指針として
「7つの目的別・本の選び方」が紹介されています。
たとえば「仕事で成果を上げたい」「人間関係を円滑にしたい」「お金の知識を身につけたい」など、
テーマごとにどんな本を選べばよいかが示されているのです。
なんとなく話題の本に飛びつくのではなく、
自分の課題にフィットした一冊を選ぶことで、読書体験がより実践的な学びに変わります。
また、巻末には「人生が好転し、視野が広がるオススメ本101冊リスト」が
特別付録として収録されています。
長倉氏自身が厳選した101冊のリストで、
自己啓発から小説まで多彩なジャンルが網羅されています。
読書初心者でもこのリストから興味を惹かれる一冊を選んで読み進めていけば、
自然と自分の視野が広がり、人生を変える一冊に出会える可能性が高まります。
「どの本を読むか迷ったら、まずこの中から選んでみる」
そんな心強いガイドが用意されている点も、本書の魅力の一つです。
第6章 読書体質になる22のアクションプラン
最後の第6章では、読書を習慣化して「読書体質」を手に入れるための
具体的な22のアクションプランが提示されています。
読書体質とは、意志の力に頼らなくても
日常的に自然と本を手に取ってしまうような状態のことです。
多くの人が「忙しくて時間がない」「三日坊主で続かない」といった悩みを抱えますが、
本書のプランは誰でも無理なく実践できるよう工夫されています。
その中には例えば、「朝一番に15分だけ読む」、「1日10ページだけ読む」、
「通勤など移動時間を読書に充てる」、「読書仲間を作って感想を共有する」といった
シンプルながら効果的なアイデアが含まれています。
重要なのは完璧を目指さず、ハードルの低い目標から取り組んで
小さな成功体験を積み重ねることです。
例えば「1日15分の読書」でも、それを1年続ければ約91時間にもなり、
塵も積もれば山となる効果があります。
朝の静かな時間に読書を習慣づければ、
脳が活性化してその日一日の生産性が上がるというメリットもあります。
たとえ15分でも毎朝読書をすることで、「今日もやり遂げた」という自己効力感が得られ、
自信と集中力をもって一日をスタートできるのです。
22のアクションプランは非常にバリエーション豊かで、
自分の生活スタイルに合った方法を選んで組み合わせることができます。
「夜寝る前の10ページ読書」から「週に一度は図書館や書店に行く」まで、
人それぞれの環境に適したプランが用意されているため、
「続けられない」という言い訳を封じ込めてくれます。
こうした工夫を取り入れることで、読書は特別な行為ではなく
歯磨きのように当たり前の習慣へと変わっていきます。
一度読書体質が身につけば、本を読むこと自体が楽しくなり、
更なる知識欲が生まれる好循環に入れるでしょう。
そして何より、読書という習慣を継続できたという事実そのものが
「継続する力」を養い、他の目標達成にも波及する貴重な財産になります。
読書習慣は自己成長の土台であり、
人生を好転させる第一歩だと本書は語りかけています。
最後に
ここまで本書について紹介してきました。
読書がもたらす恩恵を論理的かつ具体的に教えてくれる1冊です。
知識が増えるほどさらに学びたくなり、小さな習慣の積み重ねが大きな差を生む
読書の力を再確認させてくれる本書を通じて、
「今日から一日15分読んでみよう」という前向きな一歩を踏み出せるでしょう。
本書が気になる方は、是非手に取ってみてください!
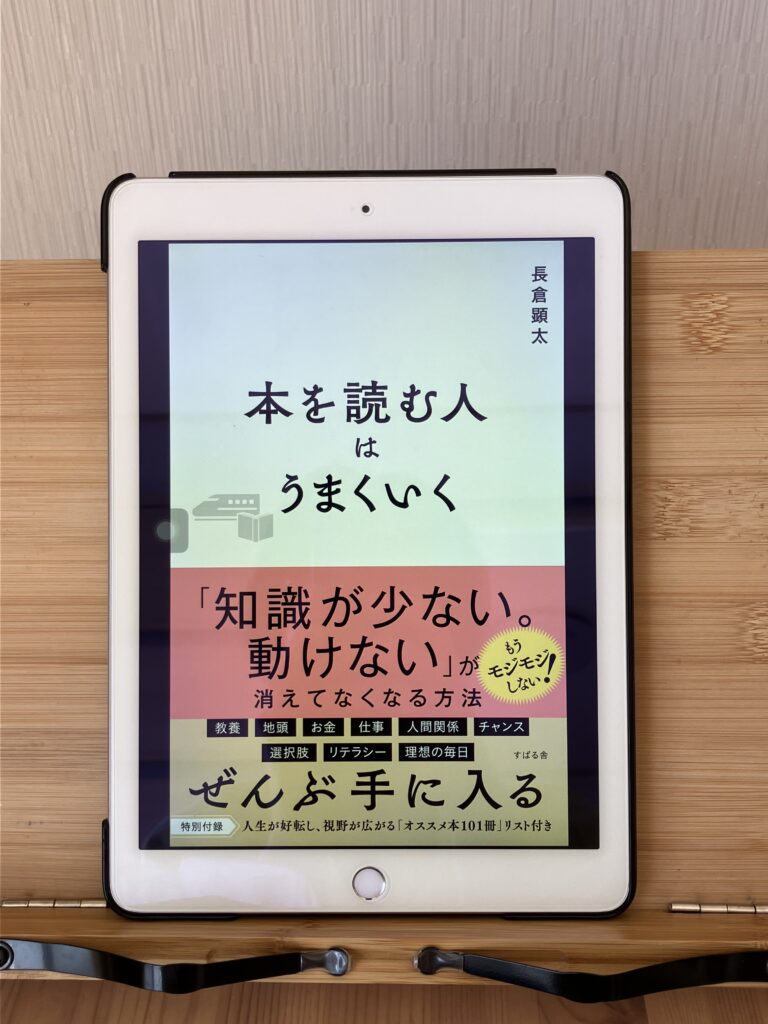
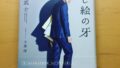

コメント