こんにちは!しょーてぃーです!
今回は、鈴木大介さんの
『貧困と脳 「働かない」のではなく「働けない」』について紹介をしていきます!
『貧困と脳 「働かない」のではなく「働けない」』について
本書の概要
本書はひとことで言うと
誰にでも起こりうる「働けない脳」のリスクに気付かせてくれる1冊です。
本書をオススメしたい人
- 貧困問題や社会福祉に関心がある人
- ミスを「意識の甘さ」と感じてしまう人
- ストレス過多の働き方に不安を感じ、自身の働き方を見直したい人
著者の鈴木大介氏は、貧困問題を取材してきたルポライターです。
ベストセラー『最貧困女子』では、貧困女性の実態を記されていますが
本書では、貧困の背景に「働けない脳」という見えない問題があることを指定しています。
著者自身の脳梗塞による高次脳機能障害の体験や、
貧困当事者の取材を通じて、本人の怠惰ではなく
脳の認知機能低下が原因で「働きたくても働けない」人々の実態を明らかにし、
従来の自己責任論に疑問を投げかけています。
また、脳機能への支援や社会制度の改善の必要性も提言しています。
脳卒中や発達障害、うつ病などによる脳の機能低下が、
当人の努力ではどうにもならない生活の困難を招き、
結果として貧困につながるケースが多い現実を浮き彫りにしています。
さらに、この問題は高齢化やストレス社会に生きる誰にとっても他人事ではなく、
従来の価値観や支援の在り方を見直す必要性を訴えています。
貧困の本質を脳の問題として捉え直し、当事者への理解と支援を社会に促す意欲作です。
『貧困と脳 「働かない」のではなく「働けない」』のまとめ
「できない人」ではなく「できなくなった人」
鈴木大介さんは長年、社会の底辺で暮らす人々を取材し続けてきました。
その中で、約束に遅刻したり何度も予定変更を繰り返す、
目の前の優先事項を決められず全く別のことをしてしまう
いわば「困ったパーソナリティ」を持つ貧困当事者によく出会ったといいます。
そうした姿を見て著者は当初「これでは貧困に陥るのも無理はない」と感じていました。
しかし2015年、鈴木さん自身が脳梗塞を患い、
高次脳機能障害という認知障害を抱えると状況が一変します。
発症直後の著者はあらゆる場面で自分をコントロールできなくなり、
時間も守れず思うように働けないなど
「当たり前の日常的タスクがまるっきりできない」状態に陥りました。
簡単な文章を読み解くことも、人と他愛ない会話を交わすこともできず、
人混みを歩くことすら困難となり、自分でも「どうしてできないのか?」と
戸惑う日々だったといいます。
そしてその「圧倒的な不自由さ」の感覚が、
かつて取材した貧困当事者たちが語っていた苦しみと見事に一致したのです。
著者はこの経験から、貧困当事者が「やろうとしない」「ちゃんとしていない」のではなく、
「やりたくてもできない」のだと痛感します。
脳の認知機能や情報処理能力が健常者の基準から逸脱し、
「不自由な脳」すなわち「働けない脳」になってしまうと、
当人がどれほど自助努力をしても当たり前の生活を営むことすら困難になるのです。
実際、脳の機能低下は事故や病気、発達障害、うつ病など様々な要因で起こりうるもので、
とりわけ短期記憶の低下が顕著になって日常生活に大きな支障が出るといいます。
脳の司令塔である前頭前野の働きが落ちると意思決定や衝動抑制が難しくなり、
頭では「ちゃんとしなきゃ」と思っていても目の前の行動をコントロールできなくなります。
かつて鈴木さんが疑問に感じていた
「なぜこんな当たり前のことができないのか」という問いに対する答えは、
努力不足ではなく脳機能の問題だったと言えます。
日常の崩壊 脳機能の低下がもたらすリアル
では、脳の機能が低下すると具体的にどのような問題が起きるのでしょうか。
鈴木さんはまず「遅刻が増える」ことを挙げています。
短期記憶が損なわれると物の場所や予定を忘れやすくなり、
結果として時間に遅れがちになるのです。
取材対象となった貧困者の多くも約束を守れず遅刻やドタキャンを繰り返し、
著者自身も脳梗塞後に同じように時間が守れなくなったと述べています。
次に指摘されるのが「仕事の極端な遅さ」です。
短期記憶が低下すると情報を保持しづらくなり、仕事の効率が著しく落ちます。
実際、著者が会ったある女性は会議の内容を理解できず、
メモを取っても後で見返して意味がわからなくなる状態でした。
鈴木さん自身も発症後、パソコンのフォルダ内から目的のファイルを探すのに時間がかかり、
作業スピードが大幅に低下したといいます。
こうした人々は周囲から「仕事が遅い人」と見なされがちですが、
その原因は本人の怠慢ではなく脳の問題にあるのです。
さらに深刻なのは、重要な書類や請求書が届いても開封できなくなるケースです。
頭が情報を処理しきれず現実を直視できなくなってしまうためで、
決して「サボって支払いを滞納している」のではありません。
著者によると、貧困者の多くが請求書をそのまま放置して
借金を雪だるま式に膨らませてしまう事例が数多く見られるといいます。
脳の処理能力の低下は、当事者に強い疲労感ももたらします。
軽い作業でも極度の疲労を感じる「脳性疲労」に陥り、
十分に休息してもなかなか回復しないために、
また作業が滞ってしまう悪循環を招きます。
周囲からは「根気がない」「すぐサボる」と誤解されてしまいがちですが、
実際には本人の脳が常に疲れ切ってしまっているのです。
また、些細なことにも過剰な不安を感じて行動が止まってしまう
「不安スイッチ」という心理状態も報告されています。
例えば「叱られるのではないか」と心配するあまり上司に報告ができなかったり、
一度のミスで「もう何もかもうまくいかない」と極度に落ち込んでしまったりといった具合です。
自立と依存の間で
さらに、自力で生活を回せないため周囲に頼らざるを得ず、
支援者との間に依存関係が生まれてしまう悪循環もあります。
生活が困難な人が他人にすがるうちに、その相手に支配されてしまい、
抜け出せなくなるケースも少なくありません。
このように「働けない脳」を抱えた人々は、
自助努力だけで困難を乗り越えることが極めて難しい状況にあります。
にもかかわらず、社会の支援にも高いハードルが存在します。
たとえば生活保護など公的扶助を受けようにも、その申請手続きは複雑で煩雑です。
「情報収集・書類記入・提出」という一連のプロセス自体が大きな負担となり、
単に用紙の書き方がわからないというレベルを超えて、
記憶力や情報処理能力の低下ゆえに申請を完遂できないケースも多いのです。
加えて、「怠けているだけ」という偏見の目も根強く、
支援を求めにくい空気があります。
生活保護は困窮者にとって重要なセーフティネットですが、
その申請の煩雑さや周囲の偏見が大きな障壁となっており、
必要な人に行き届かない現状があります。
行政や支援団体による申請サポートの取り組みも進みつつありますが、
より利用しやすい制度への改革が求められているのが実情です。
「包摂する社会」への処方箋
では、どのようにすれば「働けない脳」を抱える人々を支援できるのでしょうか。
本書では当事者・支援者・社会の3つの視点から具体策が提示されています。
まず当事者自身には、できない自分を過度に責めないことが大切です。
そして生活には工夫を凝らすことが勧められています。
例えばスマホのリマインダー機能やアラームを活用して予定や用事を忘れないようにする、
チェックリストでタスクを「見える化」するといった対策です。
支援する側に対しては、相手への指示をできるだけシンプルにし、
一度に多くのことを求め過ぎない姿勢が求められます。
役所の書類記入を代わりに手伝うなど、実務面でのサポートも有効です。
社会全体としては、支援制度の簡素化や、
働けない脳の人々も能力を発揮できる就労支援プログラムの充実などが必要とされています。
著者は具体例として、フィンランドの柔軟な教育システムのように
多様性に配慮した仕組みを紹介し、
ベーシックインカムやフレックスジョブ制度の検討など思い切った施策にも言及しています。
また、「生産性」だけにとらわれず
「多様性・創造性」を重視する新しい価値観への転換も提案されています。
誰もが生きやすい社会を実現するためには、
働けない脳の当事者を包摂する柔軟な仕組みづくりが重要だと本書は訴えています。
最後に
ここまで本書について紹介してきました。
本書を読み終えると、貧困問題への見方が大きく変わるように感じました。
私たちはつい困っている人に「もっと努力すればいい」と言いがちですが、
その影には当人の努力ではどうにもならない脳の不自由が潜んでいるかもしれません。
本書は今こそ自己責任論に終止符を打ち、
見えづらい困難を抱えた人を社会全体で支える必要性を教えてくれます。
本書が気になる方は、是非手に取ってみてください!
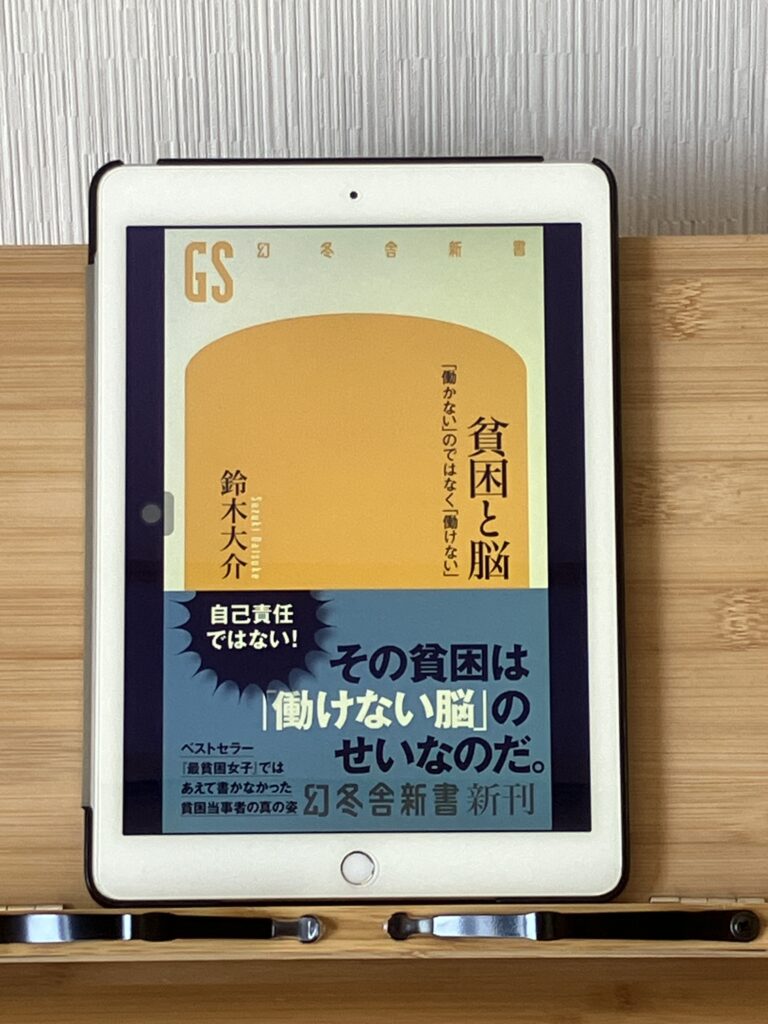
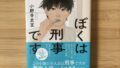

コメント