こんにちは!しょーてぃーです!
今回は、堀田秀吾さんの
『科学的に証明された すごい習慣大百科』について紹介をしていきます!
『科学的に証明された すごい習慣大百科』について
本書の概要
本書はひとことで言うと
意志に頼らず習慣を変えるコツが凝縮された1冊です。
本書をオススメしたい人
- 習慣づくりに挑戦しても挫折しがちな人
- 科学的根拠に基づいた方法で自己成長したい人
- 日々の行動を少しずつ改善したい人
本書は、ハーバード大学やスタンフォード大学など
世界の一流研究機関で実証された習慣化テクニックを112個紹介する実用書です。
人生が変わる具体的なヒントが満載で、
仕事や勉強、健康、人間関係、メンタルケアなど
幅広い分野の悩みを科学的アプローチで解決に導きます。
本書の前提となるのは「習慣化に意志力はいらない」という斬新な考え方で、
小さな仕組み作りと環境設計によって
無理なく行動を自動化できると説かれています。
著者の堀田秀吾氏は明治大学法学部の教授で、
心理言語学や脳科学の知見を横断的に探究する言語学者です。
『図解ストレス解消大全』など数々のベストセラーも手掛けており、
科学的知見に裏付けられた習慣術を
わかりやすく伝えてくれる頼もしい専門家です。
『科学的に証明された すごい習慣大百科』のまとめ
本書は「仕事、健康管理、勉強、目標達成など、
あらゆる成功のカギは習慣化にある」と説いています。
その反面、もし誤った習慣を身につけてしまえば
大きな代償を払うことにもなりかねません。
だからこそ「何をどう習慣化すればいいか」を知るためには
科学的なエビデンスが重要であり、本書では信頼できる研究によって
効果が証明された手法のみが厳選されています。
本書のプロローグでは、習慣形成において大切なのは
「意志」よりも「環境設計」と「条件設定」であると強調されます。
意志の力に頼らずとも、小さな仕組みを整えることで
習慣は自然と身につくという視点が示されており、
これが本書全体を通じた土台となっています。
第1章 科学的に証明された『仕事の効率化』習慣
仕事の生産性を劇的に高める習慣術が紹介されています。
例えば、時計の針の動きを通常より速くすることで
作業効率が向上するというユニークなテクニックや、
あえて仕事を中途半端なところで中断しておくことで
次回の再開を容易にする方法などが取り上げられています。
さらに、「もしAをしたらBをする」と事前に決めておく
If-Thenプランニングによって行動を自動化し、
意思決定の負荷を減らすアイデアや、
目標設定の際に憧れの人のやり方を真似してみるといった工夫も紹介されています。
また、「52分間作業して17分休憩する」という
効率的なワークリズムも提唱されており、
メリハリのある休憩が集中力維持の鍵になるとされています。
第2章 科学的に証明された『勉強』習慣
学習効率を最大化するための科学的メソッドが数多く示されています。
章タイトルには「勉強をするのに遅すぎるということはない」とあり、
何歳からでも学習を始められるという
前向きなメッセージが込められています。
勉強に取りかかる前に軽く散歩をして
脳に酸素を送りパフォーマンスを高める方法がまず紹介されます。
また、勉強は興味のあることから始めると脳がやる気を出すという指摘や、
異なる種類の問題をランダムに織り交ぜて学習する「差し込み学習」によって
従来の集中学習より大幅に効率が向上することなど、
効果的な学習法が示されています。
さらに、デジタル全盛の時代にあえて紙の本で読んだり
紙に書いたりする方が記憶定着に効果的であることや、
右手でボールを握って暗記し、左手で握って思い出すというユニークな記憶術など、
すぐに試したくなる学習ハックが満載です。
第3章 科学的に証明された『ダイエット・健康』習慣
まず「脳と体の健康の土台は『運動』と『睡眠』にあり」と
基本的な生活リズムの重要性が強調されています。
その上で、身体と脳の健康を維持するための
シンプルな習慣が多数紹介されています。
例えば、食事前に指でおでこを
30秒ほどトントンと軽く叩くと食欲を抑えられることや、
小さいお皿を使うだけで摂取カロリーを減らせるといった、
手軽に実践できるダイエットの工夫が示されています。
また、実際に食べる前に頭の中で食べ物を思い浮かべる
「脳内食事」をすることで食べ過ぎを防げるというユニークな方法や、
運動はハードにやるよりも無理のない範囲でゆるく継続する方が効果的であること、
さらに意識を向けるだけでも筋肉は鍛えられるといった
興味深い知見も紹介されています。
こうした小さな工夫を積み重ねることで、
体と心の健康の土台をしっかり築けると説かれています。
第4章 科学的に証明された『コミュニケーション』習慣
「コミュニケーション能力とは話す力だけではない」という視点から、
対人関係の質を高めるための様々なテクニックが取り上げられています。
例えば、会議中にスマホをテーブルの上に置かないだけで
相手に与える親近感が高まるという指摘は、思わずハッとさせられます。
また、温かい飲み物を手に持って会話するだけで
自分の印象が温かく感じられることや、会議では最初に発言することで
自分の提案が採用されやすくなるといった、
ちょっとした行動の工夫で、コミュニケーションが円滑になることが示されています。
さらに、アイコンタクトは相手をじっと見つめれば良いというものではなく、
視線を合わせる割合は7割程度が適切であること。
そして、自分のことを何でも包み隠さず話せばいいわけではなく、
「自己開示」はありのままの自分を50~60%開示するくらいが
相手に最も好印象を与えるという知見も紹介されています。
第5章 科学的に証明された『メンタル』習慣
心の健康を保つための習慣がまとめられています。
朝起きたときにまず楽しかった記憶を思い出すことで
朝のストレスを軽減し、一日を良い気分でスタートさせる方法や、
不安な気持ちを紙に書き出すことで
ネガティブな感情を緩和するテクニックや、
嫌な出来事を別の視点で捉え直すことで
心の負担を軽くする方法など、メンタルケアに役立つ習慣が紹介されています。
また、日常的に使う言葉をポジティブにするだけで
辛い状況への耐性が高まるという報告もあり、
前向きな言葉遣いを習慣づける効果が強調されています。
さらに、落ち込んだときには
意識的に体を動かすと心も連動して動き出しストレスが解消されること。
そして、「自分は運がいい」と思い込むことで
実際に運が向いてくるという、一見不思議ですが
科学的に裏付けられたメンタル術も取り上げられています。
第6章 科学的に証明された『生活』習慣
日々の暮らし全般に応用できる多彩な習慣が集められています。
例えば、毎日数秒でも貯金残高を記録するだけで
お金を貯める意識が高まると紹介されています。
また、自分の性格に合った貯蓄法を選ぶと
より貯蓄がうまくいくという研究もあり、
性格特性に応じて方法を工夫する重要性が指摘されています。
さらに、何かを決める際には必ず選択肢を3つ用意しておくことで、
行動を起こすハードルを下げられるとも述べられています。
そして、人生のあらゆる選択で完璧を求めすぎず
「ほどほどで良し」とする満足主義の考え方を取り入れることで、
余計なストレスを減らせるともアドバイスされています。
さらに、いつもとは少し違う小さな新しいことに挑戦してみることで
脳に適度な刺激を与え、マンネリを防ぐことも推奨されています。
小さな習慣の積み重ねによって生活の質が大きく向上することを、
本書は具体的なエビデンスとともに示してくれます。
最後に
ここまで本書について紹介してきました。
継続できないのは自分の意思が弱いせいではなく、
仕組みや環境に工夫が足りないだけなのだと考え直せることで、
自己否定感が和らぎ前向きな気持ちになれました。
忙しい毎日の中で無理せず自分を変えたいと思っている方にとって、
本書はきっと心強い味方になってくれるはずです。
本書が気になる方は、是非手に取ってみてください!

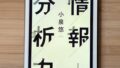
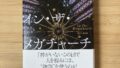
コメント