こんにちは!しょーてぃーです!
今回は、佐々木俊尚さんの
『現代病「集中できない」を知力に変える 読む力 最新スキル大全』について紹介をしていきます!
『現代病「集中できない」を知力に変える 読む力 最新スキル大全』について
本書の概要
本書はひとことで言うと
多彩な視点を身につけて、知識を血肉化する術が書かれた1冊です。
本書をオススメしたい人
・スマホでの情報収集には熱心だが、集めるだけで満足してしまっている人
・集めた情報をうまく整理・消化できずに自分の血肉にできていない人
・脳を効果的に活用する方法や最新の知的生産術を取り入れたい人
現代人にとって「集中すること」がいかに難しいか
本書はまさに、その 5分しか集中できない時代 に対応した読書術の指南書です。
著者の佐々木俊尚氏は、毎日約1000本もの記事見出しに目を通し、
有用な記事を選んで発信し続けている情報収集の達人です。
そんな著者が、スマホ全盛の今だからこそ
必要なインプット術とアウトプット術をまとめ上げています。
ニュースや本から効率良く情報を得て理解を深め、
多彩な視点を取り入れて自分の知力へと変換する方法論が網羅されています。
「読む力」を鍛えることを通じて知的生産性を上げ、
最終的には得た知識を自分の血肉(知肉)にして
クリエイティブな成果に結びつけるための1冊です。
『現代病「集中できない」を知力に変える 読む力 最新スキル大全』のまとめ
本書は、スマホによって常に情報があふれる現代社会を前提に、
「集中できない」ことを逆手に取った新しい知的生産の方法を提案しています。
著者によれば、スマホは我々の「第二の脳」とも言える便利なツールですが、
その一方で人間に飽きっぽさや集中力の低下という副作用をもたらしました。
本書は「それならば無理に集中するのを諦め、細切れの注意力(散漫力)を活用しよう」という発想で書かれており、
5分しか集中が続かない現代でも成果を出すための
具体的なインプット・アウトプット術が解説されています。
現代の知的生産に必要な5つの前提
まず序章では、本書全体を貫く5つの大前提が提示されます。
それは現代の情報社会で効率良く知力を養うための基本原則です。
- メディアを「4つのタイプ」に分類すること
あらゆる情報源を鵜呑みにせず、まずメディアの特性を見極めて取捨選択する姿勢です。
横軸に「広く浅い vs 深く掘り下げた」媒体、縦軸に「中立的 vs 主観が強い」媒体という基準で分類し、偏りや落とし穴の大きいメディアから距離を置くことが重要だと説かれます。 - 「ニュースを読み解く流れ」を作ること
一つの記事を読んだだけで「全部わかった」と思い込まない姿勢です。5W1Hで概要を押さえ(アウトライン)、専門家の解説や複数の論点に触れて(視点)、ようやく立体的な全体像が見えてくるという、アウトライン→視点→全体像の流れを意識することが提唱されています。 - 「読む目的は多様な視点の獲得」と心得ること
一つの論調だけで分かった気になるのは危ういと警鐘を鳴らし、複数の視点を取り入れ全方位から物事を見ることの重要性を説きます。
ニュースを「大きなゾウ」に例え、一部しか見ない人間には全体像が掴めないと説明しています。 - 得た知識や視点を「知肉」化すること
「知肉(ちにく)」とは、知識を自分の血肉=身についた教養に高めること。視点を増やし、そこから共通する概念を掴み出し、自分なりの世界観を構築することで、それが「自分だけの知力(知肉)」になります。 - 無理に集中せず「あえて散漫力を活用」すること
スマホが手放せない現代で「集中しろ」というのは非現実的。
著者は散漫になりがちな注意力を逆に活かす術を提案し、複数のことに目配りしながらマルチタスク的に取り組むアプローチを紹介しています。
情報収集・整理の新しいアプローチ(ネット・記事編)
第1章~第4章では、主にネット記事やニュース情報の収集・整理術が扱われています。
現代は誰もがSNSやニュースサイトから膨大な情報に触れられる一方で、
情報に振り回されて「気が散る」人がほとんどです。
著者はまず「落とし穴」を見極め、読むべき情報源を選別することの大切さを説きます。
先述のようにメディアの特性を把握し、避けるべき情報源を知ることが出発点となります。
本書では「偏りが強いメディアを見抜くポイント」や
「SNS・新聞それぞれの落とし穴」についても具体的に解説されており、
信頼できる情報とそうでないものをふるいにかける方法が紹介されています。
次に、効率的に情報収集するコツとして著者が強調するのが
「プッシュ情報」と「プル情報」の使い分けです。
プッシュ情報はSNSのタイムラインやニュースアプリの通知など、
放っておいても流れてくる受動的な情報です。
一方、プル情報は検索やRSSなど、自分で能動的に取りに行く情報です。
本当に価値のある情報は「自分のためになるか」という視点で取捨選択し、
良質なプル情報を意識的に集めにいく姿勢が重要だと説かれます。
特に「Feedly」などのRSSリーダーを活用して、
お気に入りサイトをカテゴリ別に登録・整理する方法や、
あとで読むために「Pocket」へ保存する習慣、タグで管理するテクニックも紹介されています。
いまは不要でも半年後に役立つ情報」をアーカイブしておけば、
知識のストックとして再活用できるという視点は目からウロコです。
さらに、読んだ記事の中で「永久保存版」と思えるものは、
メモアプリにもコピーしておくと良いとされています。
これは元のWebページが削除された時の備えになるだけでなく、
書き写すことで内容の定着度が高まるからです。
またOneNote、Evernote、Notionなどのメモツールの使い分けも丁寧に解説されており
こうして情報を取集・整理・保存していくことで、知識の基盤ができていきます。
しかし情報は集めるだけでは意味がありません。
そこから「多様な視点」や「共通概念」を引き出し、
自分なりの世界観にまで高めることが大切なのです。
本から多彩な視点と教養を得るコツ(読書編)
第5章では、書籍を活用した深いインプット方法が解説されています。
ネット記事は速報性や断片的な情報に長けていますが、
体系的に知識を得るには書籍が最適です。
著者は「名著・良書には、その分野の多様な視点が1冊に凝縮されている」と語り、
紙の本と電子書籍、書店と図書館の使い分けなど、現代的な読書術を具体的に紹介します。
特に印象的なのは、読書中の「気づき」を記録する習慣の重要性です。
この話、前に読んだ本とつながるな」と思ったら、ノートや本の余白に一言メモするなど
何にピンときたかを言葉で残すことで、
後から見返した時の記憶の鮮明さが格段に上がります。
また、難解な部分こそ丁寧に読む姿勢も大切だと著者は述べています。
つい飛ばしてしまいがちな抽象的な記述こそ、
著者の核心的な思想が宿っていると考えるべきであり、
そこで示される世界観を理解することこそが読書の本質なのだといいます。
たとえば、ドストエフスキーの『罪と罰』を読みこなすコツとして、
難解な哲学的部分を読み飛ばすのではなく
「著者がどんな世界観を描こうとしているのか」を読み解く姿勢が紹介されています。
知識を「知肉」として身につけ活用する(知の統合編)
第6章以降では、得た知識を自分の血肉とする「知肉化」のプロセスが紹介されます。
著者は、情報をインプットするだけで終わらせず、
使える知識として自分の中に取り込むための方法を段階的に解説しています。
まず、知識を保存する場所を「頭の中」と「頭の外」の二つに分けるという考え方です。
脳の容量には限界がありますが、概念化された知識、
すなわち「物語として再構成された知識」は、記憶に長く留まります。
点と点の知識をつなげて、線にし、さらに束にして一つの世界観として保存する。
これが“知肉”をつくるということです。
また、著者はこの過程を「知識の筋トレ」に例えます。
知識は読むだけでなく、自分で使って初めて身につく。
読み、理解し、自分なりの言葉にし、誰かに話す、あるいは書く
この一連のアウトプットによって初めて血肉化されるのです。
また、知肉化のステップは以下のように整理されています。
- 情報を集める(読書・記事・SNS等)
- 概念を抽出する(何が共通しているか?)
- 世界観を構築する(自分の考え方を組み立てる)
- 日常の意思決定や創造的作業に活用する
こうした知肉化された知識は、たとえ詳細を忘れても、
頭の中に「思考の軸」や「判断のフレームワーク」として残り続け、さまざまな場面で役立ちます。
脳のノイズを減らし、クリアな状態を保つ仕事術
第7章では、「情報を処理し続ける脳をどう休ませ、整えるか」という視点から、
日々の仕事の中で脳のノイズを減らす方法が紹介されています。
著者が提唱するのは、「脳のクリアリング(雑念の除去)」です。
たとえば、タスク管理をしっかり行い、「やること」を頭の中に溜め込まず外に出すこと。
これは、GTD(Getting Things Done)という時間管理理論にも通じるもので、
頭の中を空にしておくことで、思考の回転がスムーズになるという効果があります。
また、メールチェックや雑務などは「まとめて処理する時間」を確保して一気に片付ける、
あるいは自動化ツールを導入してルーチン作業を極力減らす、といった工夫も紹介されています。
著者は「脳をクリアに保つことは、集中力の源泉だ」と述べており、
そのためには日々の業務そのものをシンプルに保つ必要があると説いています。
この章では、実際に著者が活用している具体的なツール
(タスク管理アプリ、リマインダー、自動仕分けなど)も挙げられ、
読者が今日からすぐ取り入れられるTipsが満載です。
散漫力を味方につける仕事術
第8章では、冒頭のテーマに戻り、「散漫力」をどう活かすかが具体的に語られます。
ここで著者は、従来の「一つの作業に長時間集中するスタイル」を疑い、
むしろマルチタスク的な仕事術を推奨しています。
たとえば、短時間ごとにタスクを切り替えていく方法。
この手法を著者は「最適なインターバルで回すマルチタスクワーキング」と呼んでいます。
飽きっぽくなった脳の性質を逆に利用し、「飽きる前に別のタスクに切り替える」ことで、
新鮮な集中力を維持しつつ仕事が進められるという発想です。
具体的には、「25分集中して5分休憩する」というポモドーロ・テクニックを応用した方法や、
1時間のうち30分は執筆、20分はメール対応、
10分はニュースチェックといったスケジューリングも紹介されています。
また、こうしたやり方が有効なのは、
現代社会において一つのことだけをやり続ける時間がそもそも確保しにくいためです。
著者は「それならば、集中できないことを前提にしたスケジューリングをすればいい」と
提案しています。
最後に
ここまで本書について紹介してきました。
著者自身が10年以上にわたり実践してきた情報収集・整理・発信のスキルが
惜しみなく詰め込まれており、読むだけで
「知的に生きるとはこういうことか」と気づかされる内容です。
本書が気になる方は、是非手に取ってみてください!

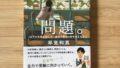
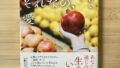
コメント