こんにちは!しょーてぃーです!
今回は、橘玲さんの
『上級国民/下級国民』について紹介をしていきます!
『上級国民/下級国民』について
本書の概要
本書はひとことで言うと
自由と平等がつくった、新しい格差を記した1冊です。
本書をオススメしたい人
・現代の格差社会や分断に問題意識がある人
・社会学・経済学・時事評論に興味がある人
・「なぜ自分は生きづらいのか」と感じている人
本書は、現代日本と世界で進行する
「見えない分断」を明らかにする社会分析書です。
日本の雇用制度の崩壊、教育格差、ひきこもりや非正規雇用の増加など、
「平成と令和の失われた時代」を通じて「下級国民」が生まれる構造を解説します。
さらに、「モテ/非モテ」など性愛における格差や、
「リバタニア」と「ドメスティックス」といった新しい階層対立が、
政治・文化・経済の分裂をもたらす様子を、グローバル視点から考察します。
最終的に著者は、知識社会がもたらした自由と格差の両面性に警鐘を鳴らし、
ポピュリズムの時代における「希望なき分断」を描き出します。
『上級国民/下級国民』のまとめ
序章:現代社会の「新たな分断」と向き合うために
本書は、これまでのような「貧しいけど幸福」「中流意識の共有」が
成り立たなくなった現代社会を背景に、
「上級国民/下級国民」という新たな階層構造が
静かに進行していることを論じたルポルタージュ的な社会分析書です。
著者の橘玲は、資本主義・民主主義・知識社会という大きな時代の枠組みのなかで、
人々がどのように「選別」され、「排除」されていくのかを、
国内外の事例を交えながら多角的に論じます。
PART1:「下級国民」の誕生
■ 平成で起きたこと
平成の日本社会は、バブル崩壊後の長期不況、
非正規雇用の拡大、生産性の低下など、経済的に右肩下がりの時代でした。
正社員の割合自体はさほど減っていないにもかかわらず、
女性や若年層において非正規が増加し、「雇用破壊」が進んだのは事実です。
また、ひきこもり人口が500万人に達している可能性など、
統計に現れにくい「見えない下層」が社会の中で膨張していることも問題です。
ITへの投資も、欧米に比べて「効率が悪く」「生産性が上がらない」など
日本型の構造が足を引っ張っていると指摘されています。
経済が長期にわたって低迷してきた最大の要因は、
「日本市場の魅力が失われた」こと。
つまり、国際競争においてイノベーション力や
人材の魅力で負けているということです。
■ 令和で起きること
日本は今後、「現役世代1.5人で高齢者1人を支える社会」に突入していきます。
「働き方改革」が始まった背景には、
非効率で高コストな昭和型会社システムの崩壊がありました。
団塊の世代と団塊ジュニア(バブル直後の就職氷河期世代)は、
格差の波に最も翻弄された世代といえます。
著者は、日本型雇用の限界、制度疲労、そして高齢者偏重の政治構造のなかで、
社会保障制度の持続可能性が限界に来ていると警告します。
PART2:「モテ」と「非モテ」の分断
■ 日本のアンダークラスと教育格差
現代日本社会には、見えにくい8つの階層が存在するとされます。
その分岐点となっているのが「学歴」と「家族環境」です。
とくに中年男性においては、大卒・正社員であるかどうかが
「幸福感」や「社会的承認」に直結しており、
フリーター・非正規では社会的孤立に陥りやすいです。
貧困層に多いシングルマザーの増加も含めて、
教育投資が可能か否かによって「階層の再生産」が起きており、
教育がむしろ「格差を拡大する装置」となっているという指摘は重いものがあります。
■ 性的市場における格差:モテと非モテの構造
「モテ/非モテ」の分断は、単に恋愛の話ではありません。
性や恋愛を「資本」として扱う観点から見れば、
これは階層構造そのものの延長線上にあります。
女性は若いうちは「エロス資本」を持ちますが、
男性の場合は年収や学歴、社会的地位などが
「モテ」の指標になりやすく、格差が顕在化します。
恋愛・結婚市場においても「事実上の一夫多妻化」が進んでおり、
ごく一部のハイスペック男性にパートナーが集中し、
その他の男性が結婚や恋愛から排除される傾向が加速しています。
このような「性愛の非対称性」は、単なる恋愛観の問題にとどまらず、
社会不安、さらには「非モテ男性による暴力的な言動や犯罪(非モテのテロ)」という形で
表出する危険性を孕んでいます。
PART3:世界を揺るがす「上級/下級」の分断
■ リベラル化する世界のパラドックス
欧米諸国では「能力主義」「自己責任」「自由意志」に基づくリベラル社会が広がる一方で、
その裏で起きているのは「選別の強化」と「弱者の排除」です。
イスラム系移民の排斥やポリティカル・コレクトネス(PC)の過剰化は、
「表面的な平等」を保つための偽善的構造とも言えます。
リベラルな理想とは、究極的には「全てを自分でコントロールせよ」という
無言の圧力でもあり、それに適応できない人々は、静かに落ちこぼれていきます。
■ 世界中で進行する「二極化」
知識社会・グローバル経済が進んだ結果、世界中の都市で「新上流階級」が集まり、
地方や郊外では「新下層」が孤立していく現象が起きています。
橘氏はこれを「リバタニア(知識・自由・多様性を尊ぶ都市的エリート)」と
「ドメスティックス(地縁・血縁・伝統に基づく保守的民衆)」の対立として捉え、
アメリカやイギリスの保守回帰(ブレグジット、トランプ現象)にもその断層を見出します。
エピローグ:知識社会の終わりとポピュリズムの時代
ポピュリズムとは、単なる政治的な反乱ではなく、
「知識社会への抵抗運動」であると著者はそう結論づけます。
サイバーリバタリアン(ITエリート)たちは自由主義の旗を掲げながら、
結果的に大多数の市民を置き去りにし、
その反発が「怒れる民衆」の爆発につながっているのです。
「お金は分配できても、性愛は分配できない」
この一言に、本書の根幹的な主張が込められており、
経済的再分配だけでは解決できない心の飢えや孤立が、
現代社会の最も深い断層なのだと訴えています。
最後に
ここまで本書について紹介してきました。
中流階級がなくなり、格差が広がる現実を
橘玲さん独自の視点で語られており、非常に学びになりました!
本書が気になる方は
是非本書を手に取ってみてください!
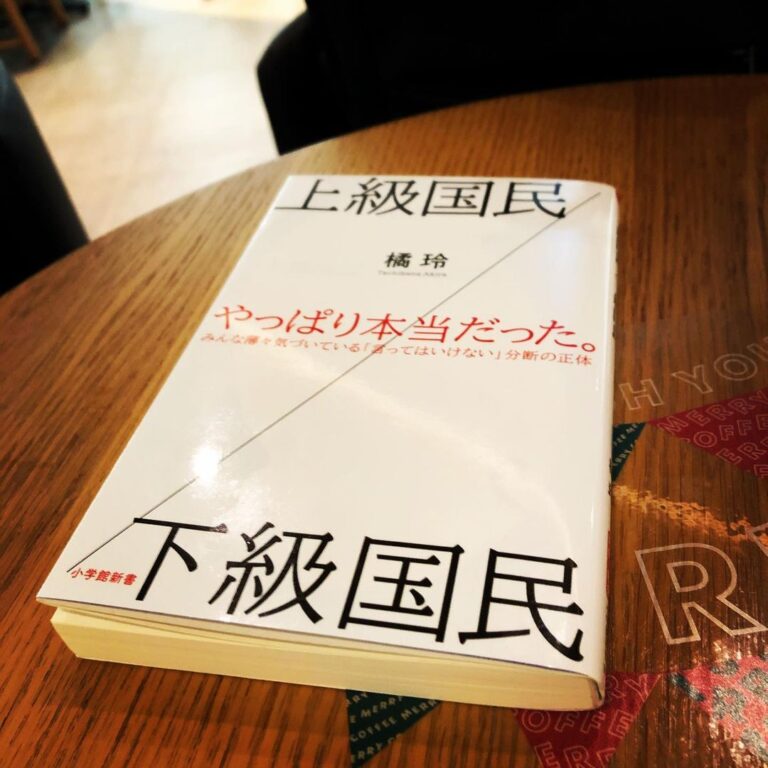
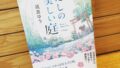
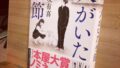
コメント